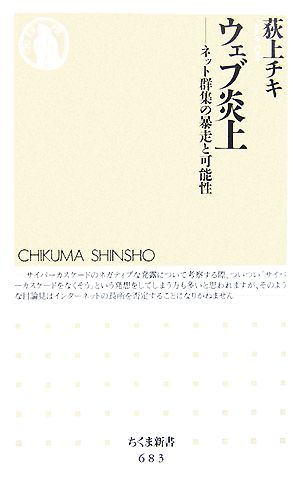ウェブ炎上 の商品レビュー
サイバーカスケード(ウェブ上の集団分極化現象)について様々な展開の仕方について論じられている。流言飛語(デマ)の広がる理論についても語られており、大変興味深く読んだ。この本を読み様々な事例を通しウェブの恩恵、危機管理を学び、リテラシーの向上に活かすことが出来ると感じた。参考文献を...
サイバーカスケード(ウェブ上の集団分極化現象)について様々な展開の仕方について論じられている。流言飛語(デマ)の広がる理論についても語られており、大変興味深く読んだ。この本を読み様々な事例を通しウェブの恩恵、危機管理を学び、リテラシーの向上に活かすことが出来ると感じた。参考文献を通し他の著者の書籍もぜひ読んでみたい。
Posted by
ウェブ炎上という事態が生じるのかをていねいに解き明かしている本です。 見るにたえないような「炎上」を嘆き、手っ取り早い処方箋を提示するのではなく、人びとのネット上での行為をキャナライズして炎上を作り出していく、インターネットという「アーキテクチャ」を冷静に分析することに、著者の...
ウェブ炎上という事態が生じるのかをていねいに解き明かしている本です。 見るにたえないような「炎上」を嘆き、手っ取り早い処方箋を提示するのではなく、人びとのネット上での行為をキャナライズして炎上を作り出していく、インターネットという「アーキテクチャ」を冷静に分析することに、著者の努力は注がれています。インターネットは、それぞれの利用者の選好に合致した情報を容易に集めることができますが、そのために人びとが同じ事件に接していながら、お互いに異なった現実を見ているという事態を生み出しやすい特徴を持っています。そしてこのことが、サイバー・スペースで各人が自由に情報を収集して議論や対話をおこなっていった結果、極端な言説や行動のパタンに流れ込んでいくという「サイバー・カスケード」と呼ばれる事態を作り出します。 オルタナティヴなハブ・サイトを作ることの重要性が論じられてはいますが、ウェブ炎上に対する具体的な対処法は示されていません。ですが、インターネットというアーキテクチャが、人びとのこうした行動を解発する特徴を持っているということをはっきりと認識することが、何よりも重要だというのが、本書から読み取るべき主張ではないかと思います。
Posted by
2007年の新書ですが、今でもネット上で起こっていることにあまり変わりはないです。mixiとかウィニーとか用語に時代を感じるくらい。ネットが人間の本質を色濃く反映するという意味では、ずっと変わらないんでしょうね。 でも、本書の表現を借りれば、ネタのベタ化はさらにすすんでいると感じ...
2007年の新書ですが、今でもネット上で起こっていることにあまり変わりはないです。mixiとかウィニーとか用語に時代を感じるくらい。ネットが人間の本質を色濃く反映するという意味では、ずっと変わらないんでしょうね。 でも、本書の表現を借りれば、ネタのベタ化はさらにすすんでいると感じます。本書ではたくさんのネット炎上案件がまとめられていてとてもわかりやすいのですが、本書が書かれた2007年ごろは書き込む側がまだ、アンダーグラウンドな立場にいて、それゆえに炎上といえどもかろうじて笑いになっていたような気がします。ネットユーザーでない人のほうがかなりのマイノリティになりつつある今、それらはもはや便所の落書きじゃなくなってきている。特に2ちゃんねる、年明けの人質事件から、極端な自己責任論が異常に流行したのを見るに、今の2ちゃんねるは完全にコミュニティとして閉じているように思える…。
Posted by
非常に影響力のあるブログがあります。残念ながら、他人のブログを読む習慣がないので、どんなサイトが人気があるのかわかりません。目安は、1日のアクセス数が万単位だそうです。正直、芸能人以外のブログで、そんな力のあるサイトがあることが想像も出来ません。前のブログも、このブログもブログ過...
非常に影響力のあるブログがあります。残念ながら、他人のブログを読む習慣がないので、どんなサイトが人気があるのかわかりません。目安は、1日のアクセス数が万単位だそうです。正直、芸能人以外のブログで、そんな力のあるサイトがあることが想像も出来ません。前のブログも、このブログもブログ過疎地帯にあるので、どうも想像できません。時代とずれているんですね。地元の図書館で読む。いい意味で、期待はずれでした。この手の本は閉じているのです。ある種の知識のある人を前提としています。しかし、新書の読者は、僕のように知識のない人もいます。知識がないからこそ、新書を読むのです。この新書は、この手の読者にも丁寧です。炎上について、具体的な事例を交えながら紹介しています。非常に親切です。また、非常に読みやすい文章です。著者が売れっ子になるのも当然です。今後注目したいライターです。そんなことを感じました。それだけです。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
あたりまえだがWEB上の現象に論を固めているので、荒唐無稽の感はぬぐえないが、マクルーハン以降でのメディア論としては、ようやく腑に落ちた一冊だった。田原も猪瀬も内田もなんだかかっこつけててそのぶんうさんくささがあった(吉本は「メディア論」に入れていない)。サイバーカスケード、アーキテクチャ、エコーチェンバー、クラスター化。用語はちゃらいが、わかりやすく、リアル。若いって素晴らしい!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ウェブによる社会全体の可視化とつながりが, 利用者に何をもたらすのか, そのことによって何が問題となるのか. なにに留意し,なにを意識しながら使うべきか. どこまでがウェブ社会の特徴で,どこからがそうでない事柄なのか. 今後,このインターネットというツールを私たちがより良い議論の土壌とするには, 何をすべきであるのか,何が求められているか? を論じていらっしゃる本です. 2007年の書籍. この時代から更に技術は進んで,2013年の今は より個人の言論が活発に, よりソーシャルコミュニケーションの場が多彩に, より他者の意見や行動が見やすく透明になっています. 書中で示されている ハブメディアの必要性, 新たなカスケードを提供するコンテクストマーカの作成, ネット環境を整備するアーキテクチャの構成, という提案は,さまざまなSNSやサイトの設立によって, その役割が果たされている(またはその役割を実験されている?)ように感じますが, ウェブの最大の特徴である「見える」「つながる」という部分から起こる 完全遂行の課題,過剰性の課題は, より加速しているように思えます. 異なるエコーチャンバーにいる人との衝突も ますます起こりやすくなっているようです.しかし, これらの「祭り」「炎上」は,もはや事件ではなく 日常化しているようにすら感じております. 序盤で,インターネットはまるで人の思いを糧に生きているようだ,とおっしゃった著者さんですが, どのように今後インターネット社会が進んでいくのか, それは確かに,生物や人間の成長と同じく,誰にもわかりません. 成長する環境を整備し,接し方に気を遣う, 我々のやり方次第である,ということを,改めてより実感しました.
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
報道におけるマスコミは法と倫理がある。それは社会的責任があるから。ネットでは私刑がごとく晒しが行われる。これは考えなければならない行為だよねという意見に賛成。 メディアには独特の法則があり、人の欲望をかなえる為の透明な道具ではなく、それぞれの仕方でアウトプットの屈折や社会への反射を起こします。 社会への反射=マッサージ
Posted by
最近、個人的に注目の荻上チキさん。 テレビとかでたまにお見かけするが、すごく頭が切れる印象。 ウェブ上で起こる「炎上」についての本。
Posted by
「サイバーカスケード」というものの成り立ちや、僕らがそれ加担しうる状況はままあるという現実を知り、インターネットに対して、ひとまず距離を置かせてくれるような著書。ネットに慣れてない人は読むといいかも。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最近、いよいよメディアの表舞台に出てきた荻上さんの著作を初読み。 ・「web2.0」とは、二〇〇五年九月、コンピューター技術書籍の出版や技術のフォローを行っているオライリー社の代表ティム・オライリーが「web2.0とは何か」という論文を発表し、それがきっかけで話題になった言葉です。従来のインターネットで提供されるサービスやユーザー体験を「web1.0」とし、それを超えて台頭しつつある新しいウェブ空間のあり方に対する総称として用いられています。 ・要するに「2.0」とは、「今までのウェブサービスよりも、さらにすごいウェブサービスたち」を意味する掛け声のようなもの。 ・ウェブは「みんなの意見」をデータベースに取り込み、履歴を積み重ねていくことで、より上質のサービスを個人に向けて提供してくれるというわけです。 ・ウェブは、あたかも独自の生態を持った生物のようなものだといえるでしょう。 ・政治的にリベラルな思想の持ち主はリベラルな本ばかり読み、政治的に保守的な思想の持ち主は保守的な本ばかり読む。両者は互いに論難しあうことが多いにもかかわらず、論敵の本をきちんと読み比べている人はごくわずかで、自分の思想にあった本ばかりを読む人が基本的には多いということです。 ・「これまではつながっていなかったものがつなげられる」ということは、「ウェブ以前」であれば時間的、空間的条件などによって隔てられていたはずのコミュニケーションが遭遇するということを意味します。例えば、普段であれば出会うはずのないまったく違う意見の持ち主のサイトを閲覧し、普段なら考えないはずの問いと遭遇する。ウェブでは、地理的、物理的、時間的な条件によって拘束されません。そのことが、「ウェブ以前」の社会では想定してこなかったようなコミュニケーションのパターンを生むのです。 ・ただし、「これまでつながっていなかったものがつなげられる」ことによって、「出会いたかった人」だけでなく、それまで「出会うはずのなかった人」や「出会いたくなかった人」とつながることも起こりえます。 ・オルポートとポストマンは、「流言の量は問題の重要性と状況のあいまいさの積に比例する」[R(流言 Rumor)=i(重要さ importance)× a(曖昧さ ambiguity)]という有名な公式を提示します。 スマホの普及とともに、「ネットの中に生活している」といっても言い過ぎではないような今の時代を生きていく上で、リテラシーを身につけるためにも抑えておきたい初歩の一冊という感じ。
Posted by