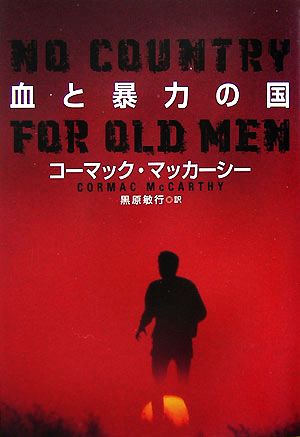血と暴力の国 の商品レビュー
未曾有の異常気象、或いは世界的パンデミックの様に、人類が経験したことのないほど強烈で、かつ不可解な「悪」に直面した時、人は何を感じてどう振舞うのか、何ができるのか。 いつまでも若さを保つ「悪」に対して、急速に老いて衰えるかに見える「善」「正義」の行く末を憂う作品、そう読みました...
未曾有の異常気象、或いは世界的パンデミックの様に、人類が経験したことのないほど強烈で、かつ不可解な「悪」に直面した時、人は何を感じてどう振舞うのか、何ができるのか。 いつまでも若さを保つ「悪」に対して、急速に老いて衰えるかに見える「善」「正義」の行く末を憂う作品、そう読みました。 そんな「悪」を排除する力は何か、という問への答えも、一応提示してはいます。が、正直、希望が持てるような答えではないですね。 あと、個人的にちょっと意外だったのですが、コーエン兄弟による映画化は、極めて原作に忠実と言って良いと思いました。映画を観たなら原作は読まなくていいかも。 ただ、最初に書いたような骨子を映画から「読み取る」ことが、自分には出来なかったので、自分が原作を読む意味はありました。原題(老人は住めない国)の意味も明確になったと思います。
Posted by
暴力の嵐だけど詩的。映画で見た時の印象はよくわからない感じで唐突に終わった、という感じ。本で読むとストーリーは追えるけど、相対としてのよくわからなさはChigurh の空虚な邪悪さが映画のように映像として現されない分余計に恐ろしく感じられる。説明不能の(時代によって生まれたように...
暴力の嵐だけど詩的。映画で見た時の印象はよくわからない感じで唐突に終わった、という感じ。本で読むとストーリーは追えるけど、相対としてのよくわからなさはChigurh の空虚な邪悪さが映画のように映像として現されない分余計に恐ろしく感じられる。説明不能の(時代によって生まれたようにも見える)邪悪さとその真空に周囲の人間たちが引き込まれていくような感触はドストエフスキーの悪霊につながるように感じた。
Posted by
単なるノワール小説かと思いきや難解な小説である。映画の方を先に鑑賞したが難解な所に追跡劇という娯楽要素が入っていたために分かりやすかった。原作はというと追跡劇はそこそこであとは登場人物の一人語りという形式が取られている。これは何度か読まないと理解できない。
Posted by
早川epi文庫で新装版が発売されるらしいです! でも、タイトルが原題どおりに… この「血と暴力の国」というタイトルは、正確ではなくても、原作の持つ迫力をよく伝えていて、気に入っていたので、ちょっと残念です… ただ、原題こそ作者の意図だと読むとわかるので、やむを得ず… またまた読...
早川epi文庫で新装版が発売されるらしいです! でも、タイトルが原題どおりに… この「血と暴力の国」というタイトルは、正確ではなくても、原作の持つ迫力をよく伝えていて、気に入っていたので、ちょっと残念です… ただ、原題こそ作者の意図だと読むとわかるので、やむを得ず… またまた読みたくなりました。 実は、積読15年越しで読んだのでした…死ぬまでに再読できるかな…
Posted by
老人たちの国にあらず。 映画2周くらい観てから、あまりにも好きすぎるので本を読んでみた。 こうして見ると映像化にあたって結構いろんな場面をカットしたり要約しなきゃなので、メディアミックスって相当理解とか技量とか要るなあ、脚本書く人大変だよなあって思う。 あまりにも淡々とした...
老人たちの国にあらず。 映画2周くらい観てから、あまりにも好きすぎるので本を読んでみた。 こうして見ると映像化にあたって結構いろんな場面をカットしたり要約しなきゃなので、メディアミックスって相当理解とか技量とか要るなあ、脚本書く人大変だよなあって思う。 あまりにも淡々とした語り口で、映画観てなかったら絶対何が起こったかもわからないまま読了してたと思う。 モスが死ぬ時、呆気なさすぎる…映画でもそうでしたね。 最新鋭の武器、最新鋭の悪意。 ピュア・エビル! ベルが最後に語る夢の話が、ベルの人生と重なっているところ、とっても好きです。 もう一回映画観たくなってきた! シガー、ハビエルバルデムがマジでありえないくらい完璧に演じてくれてたじゃないですか。 最高の映画でしたね。 その裏にこういう原作があったんだなーって思うと始まりは文章だったってところに感銘を受けたり感動したりする。 サイコパスって言葉も出てくるけどシガーが何者なのかについての描写は意図的に避けてあり、なんかバットマンのジョーカーを今思い出した。 神秘的なんですよね。 正しく生きていても、死はいつ理不尽に訪れるかわからない。 死を覚悟していても死ぬとは限らない。 不条理…この作品が持つもの悲しい雰囲気、それが本当に大好きです。
Posted by
映画『ノーカントリー』の原作。 犯罪小説風だけど純文学の要素が強くてちょっと難しい。 過激な犯罪が増え、昔とは変わったアメリカ、罪の有無に関わらず人を殺していく殺し屋のシュガーは、現代のアメリカで起きる理不尽な暴力の象徴? 以前映画を観た時もあまり面白さを理解出来なかったけど、も...
映画『ノーカントリー』の原作。 犯罪小説風だけど純文学の要素が強くてちょっと難しい。 過激な犯罪が増え、昔とは変わったアメリカ、罪の有無に関わらず人を殺していく殺し屋のシュガーは、現代のアメリカで起きる理不尽な暴力の象徴? 以前映画を観た時もあまり面白さを理解出来なかったけど、もう一度映画を観たら感想変わるかも。
Posted by
自分では選ばなかったであろうタイトル。ある書評で評価が高かったので読んでみたら面白かった。ゴールの手前まで。 最初は独特な文章、かつテンポが異常に早く、おもしろく次から次へとページをめくった。 しかし、4分の3くらいから、徐々に説教臭くなってきて、最後は。。。 読み終わってか...
自分では選ばなかったであろうタイトル。ある書評で評価が高かったので読んでみたら面白かった。ゴールの手前まで。 最初は独特な文章、かつテンポが異常に早く、おもしろく次から次へとページをめくった。 しかし、4分の3くらいから、徐々に説教臭くなってきて、最後は。。。 読み終わってから、もしかして、こういうことを言いたかったのでは?と、気づいた。 次にこの著者の作品を読むときは気をつけようと思った。 新しい世界観で良いと思った。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
ノワール小説みたいな味わいだったけどたぶんそうではないんだと思う 主人公はモス だと思う にもかかわらず最初から最後までをベルの独白とし、シュガーのバックグラウンドすら一切説明しないのは、そのモスの死すら無情で荒んだ世界のたった一片でしかないと思わせる… シュガーはただひたすらに自分の道理にしたがって人を殺す恐怖として描かれているけど、 モスすら殺していない ベルとも言葉すら交わしていない シュガーに追われつつ、あるいは対決の意志を密かにいだきつつも、別の要因に死に、対決できずに敗北する
Posted by
保安官の回想で終わるとは予測ができなかった。ベトナム戦争は背景ではあるが、主題ではなく、撃ち合いが主に印象に残るが、あっさりと殺されすぎる。
Posted by
所謂、ピューリッツァ賞作家が描いた犯罪小説。翻訳者のあとがきにあるように、本作には様々な解釈が可能だろう。まるで全てが幻影であるかのように、輪郭をぼかしたままに物語は進み、前後の流れをぶつ切りにして、屍の山だけが築かれていく。純粋悪を象徴するという正体不明の殺人者の罪と罰に触れる...
所謂、ピューリッツァ賞作家が描いた犯罪小説。翻訳者のあとがきにあるように、本作には様々な解釈が可能だろう。まるで全てが幻影であるかのように、輪郭をぼかしたままに物語は進み、前後の流れをぶつ切りにして、屍の山だけが築かれていく。純粋悪を象徴するという正体不明の殺人者の罪と罰に触れることもなく、無為なる殺戮を朧な文体でひたすらに描写するのみ。救済という概念すらない。 読後に残る虚無感の理由は、娯楽小説に徹することができない作者自身が絡め取られた文学という楔であろう。 これがノワールかと問われれば、否と言わざるを得ない。そもそも作者にその意図があったようには感じない。さらにいえば、哲学的な含みも浅い。あからさまな不条理は、なにものをも指し示すことはない。コインの裏表で命運を決める殺し屋は凡庸であり、人生を語る保安官の独白に心に沁む訓戒がある訳でもない。つまりは、格好付けたスタイルだけの小説という結論になる。最大の欠点は、血塗られた大国の有り様を嘆きつつも、遂に純粋悪と対峙することの無かった保安官の極めて薄い存在感である。 どんな文学でもいえることだが、作者はあれこれと説明を加える必要はない。理解できない部分は、如何様にも読者が脳内で補完するからだ。この作品に対する高評価は、それを表している。
Posted by