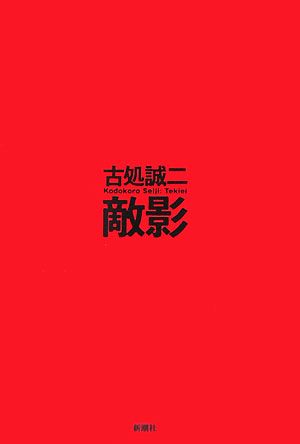敵影 の商品レビュー
戦争は決してエンタテインメントではない!… 戦後ちょうど70年、似非の零戦映画に感動しただの涙しただの言っている日本人にこの本格の戦争文学は果たしてどこまで理解され通用するのだろうか。 既に時遅しかもしれない、しかしあの不条理な出来事に命を投げ打った全ての人々の心情を敢えてこの時...
戦争は決してエンタテインメントではない!… 戦後ちょうど70年、似非の零戦映画に感動しただの涙しただの言っている日本人にこの本格の戦争文学は果たしてどこまで理解され通用するのだろうか。 既に時遅しかもしれない、しかしあの不条理な出来事に命を投げ打った全ての人々の心情を敢えてこの時代に描くことを使命とした古処さんには心から敬意を表したい。 「戦時に於いては生きる事も死ぬ事も己の意志ではなくそれは命令によるものである」…人が人でなくなる異常な世界を作り上げるのもまた人、同じ過ちを二度と繰り返すことなきよう祈るのみ
Posted by
戦争を体験していない年代の作家による戦争小説だが、かなりリアルな作品。読んでいて胸が引き裂かれそうな気がした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
もう少し、もう少し書き込みがある方が好きだなぁと。これは個人的な好みの問題。 吉村昭、遠藤周作、梅崎春生、島尾敏雄・・・彼らの作品は臓腑をえぐるように迫ってくるんだけれども。私の読解力が足らないのだろう。 汚いこと、理不尽、不条理、知っているから、あえて見せられても。 もっと怖いことはあって、それを見なければ、また繰り返す、そう思っている。
Posted by
捕虜収容所を舞台に、日本兵の挫折と矜持を描いた秀作。 あいかわらず古処作品の言葉はひとつひとつが重く、襟を正さずに読むことができない。柔道とボクシングとの対比に沖縄での戦況、ひいては日本とアメリカの構図をみてとるのは少し唐突な印象もあったが、クールな印象の羽島が損得勘定抜きで声を...
捕虜収容所を舞台に、日本兵の挫折と矜持を描いた秀作。 あいかわらず古処作品の言葉はひとつひとつが重く、襟を正さずに読むことができない。柔道とボクシングとの対比に沖縄での戦況、ひいては日本とアメリカの構図をみてとるのは少し唐突な印象もあったが、クールな印象の羽島が損得勘定抜きで声を荒げて応援に興じるシーンは感動的ですらあった。物語として特別に起伏があるわけでもなく、感情表現もひどく抑えられた筆致は、おそらくこの先も一般受けするものではないのだろうが、エンターテイメント要素の少ない、リアル感のある戦争文学を求める者の支持は決してなくならないであろう。 ラストにカタルシスがあるこの感じは、印象としては「七月七日」とダブるものが多かった。 僕たちは古処さんをもっと読まなければいけない。
Posted by
沖縄戦の物語である。『接近』で桜の花咲く頃の沖縄戦を、『遮断』で梅雨のさ中の沖縄戦を描いた古処誠二氏。本作では8月15日前後の沖縄を描いている。 日本軍の兵士だった近藤義宗は、沖縄での組織的戦闘が終わり、捕虜として米軍の捕虜収容所に収容されていた。捕虜収容所には毎日の使役は...
沖縄戦の物語である。『接近』で桜の花咲く頃の沖縄戦を、『遮断』で梅雨のさ中の沖縄戦を描いた古処誠二氏。本作では8月15日前後の沖縄を描いている。 日本軍の兵士だった近藤義宗は、沖縄での組織的戦闘が終わり、捕虜として米軍の捕虜収容所に収容されていた。捕虜収容所には毎日の使役はあるものの、食事も与えられ、ある種の倦怠感が漂う日々。そんな中、収容所内で義宗は二人の人物を捜していた。一人は病院壕で懸命に義宗を看護してくれた女学生・高江洲ミヨ、もう一人は阿賀野という軍曹。 なぜ義宗はこの二人の人物を懸命に捜しているのか?その謎が冒頭に提示されるが、答えは物語の中盤で明らかになる。それは意外な真相である。 この謎で全編を引っ張ることなく、ミステリ的な展開に落ち着かなかったのは、それ以外に描きたい事が多すぎたためか。 捕虜になってしまえば軍での上下の関係もなく、私怨を晴らす為に闇討ちに興じる捕虜たち。身分が明らかになるのを恐れて偽名を名乗る者たち。玉音放送後に捕虜としてやって来た者と、それ以前から捕らえられている者たちの確執―。 これまで沖縄戦を描いた小説ではあまり描写される事のなかった情景が緊迫の筆致で描き出されていく。 毎回、様々な視点から沖縄戦を描いてきた古処誠二氏。今回は捕虜、そして現地人ではない兵の視点で、しかも玉音放送後の沖縄を描くというのが面白い。 ただし、前2作では行間に沖縄の土着性というか地元の濃密な空気というか、そういうものが充満していたのに比べ、今作ではそんな空気が減少しているようにも感じた。登場人物の多くが沖縄人ではない人たちだからか。 終盤行われる、ある《闘い》のシーンは息を呑む緊張感。もちろんこの《闘い》のシーンが沖縄戦そのものを比喩していることは登場人物の口を借りて語られる。 前2作のタイトル『接近』『遮断』は、抽象的に作品内容を表現していたが、今作は直接的に作品のテーマを表現している。強大な敵の前に敗れた人々は、新たな《敵》を捜し始める。その事に意味があるかどうかは関係ない。本当は敵などどこにもいないのに、それでも存在しない《敵》の影を追い続ける。「憤怒が敵影を求める」(p43,p69)と本文でも触れられている。終盤の《闘い》のシーンは、《敵》を追い続ける意味その答えでもあるのだ。 「仇はカタキとも読み、カタキは敵とも書く」(p148) …なぜ人は敵を追い求めるのだろうか。 終戦後を舞台にする事で、沖縄戦の凄惨を逆に明確にするという手法に驚いた。義宗らの達観したような語り口は、終戦直後の捕虜たちの心情を痛いほど表現している。 義宗をはじめいろいろなキャラが登場するが、中でも日系二世で米軍にいる男は印象的なキャラだ。彼がラストで示す希望とも絶望とも取れるある光景が戦争の残酷さを浮き彫りにする。 前2作から同じ事を考えている。新たな感性で沖縄戦を描く世代が出現してきたのだなと。沖縄の若手作家ではこういう小説は書けなかったのかも知れない。 『接近』では白一色、『遮断』では黒一色に染められた単行本のデザインだが、今回は赤一色。律儀にそれぞれスピン(しおり用についているひも)の色も白・黒・赤である。 不穏な色、赤。それは戦死した兵士たちの血の色か、巻き添えをくらった住民たちの血の色か、それとも私憤で報復をうけた捕虜たちの血の色なのか。 もしかしたら我を失って《敵》を捜す者たちの血の気の色なのかも知れない。
Posted by
昭和二十年八月十四日、敗戦の噂がまことしやかに流れる沖縄の捕虜収容所 で、血眼になって二人の人間を捜す男の姿があった。一人は自らの命の恩人、 女学生の高江洲ミヨ。もう一人はミヨを死に追いやったと思われる阿賀野という 男。男の執念の調査は、やがてミヨのおぼろげな消息と、阿賀野...
昭和二十年八月十四日、敗戦の噂がまことしやかに流れる沖縄の捕虜収容所 で、血眼になって二人の人間を捜す男の姿があった。一人は自らの命の恩人、 女学生の高江洲ミヨ。もう一人はミヨを死に追いやったと思われる阿賀野という 男。男の執念の調査は、やがてミヨのおぼろげな消息と、阿賀野の意外な正体 を明らかにしていく。
Posted by
沖縄で、米軍の日本兵の捕虜収容所というのが、あまり聞いたことが無く、新鮮だった。ただ、終戦直後の沖縄といわれてても、ピンと来ない。他の国の話のよう。ずいぶん昭和は遠くなったんだなあ。何故今この話を書きたかったかが、判らなかった。
Posted by
実際の収容所がどうだったか分からないし、その記録に触れる機会もなかった。沖縄戦の末期を描いた何本かの映画でその一部を知っただけだ。この小説に描かれたその時の様子は確かに映画「沖縄決戦」の病院壕のそれと似ている。敗軍の将兵の闘いも悲惨だが、傷病兵はもっと悲惨だ。他国と陸続きで、歴史...
実際の収容所がどうだったか分からないし、その記録に触れる機会もなかった。沖縄戦の末期を描いた何本かの映画でその一部を知っただけだ。この小説に描かれたその時の様子は確かに映画「沖縄決戦」の病院壕のそれと似ている。敗軍の将兵の闘いも悲惨だが、傷病兵はもっと悲惨だ。他国と陸続きで、歴史上何度も戦争をして、負けたり勝ったりしている国々は、負け方も心得ている気がする。負けは国家の終わりじゃなく、戦争の終わりを意味するだけのこと。負けたら復興すればよい。そして復興のために人は生き残らなければならない。残念ながら戦争に於いても日本は長い鎖国状態で、戦い方も負け方も知らなかったようだ。先の戦争で、手痛い負けを学んだ日本は、次の戦争ではもっと上手く勝ったり負けたりしなければならない。もちろん戦争はしない方がよい。しかし喧嘩は片方の意志だけで始めることができるものだ。ならばもっと上手く闘わねばならない。現行憲法では、国家間の紛争を解決する手段として放棄しているが、放棄ではなく選択してはならない手段として残すべきだ。そして、戦争をもっと学び、被害や犠牲を最小限に止めて終わらせる方法を身につけるべきだと思う。戦争をしたくないなら、戦争によって苦しむ人を増やしたくないなら、悲惨な状況を広げたくないなら、戦争を嫌悪するならばこそ戦争から目を背けずしっかりと学ぶべきだ。この小説を読んでそんなことを思いました。ただ…。面白かったけど、ちょっと感傷的に流れすぎているような気がしました。
Posted by
今回は終戦してからがメインだからか他の作品より希望がある――というか先に(必ずしも前ではなく)進んで行こうという雰囲気がある。 個人がどうやって戦と折り合っていくか。 けどなあ…この人は、ひとりの女子も出さずに男だけしか出てこない戦場だけ書いてくれれば好きなんだけど。女の子に夢...
今回は終戦してからがメインだからか他の作品より希望がある――というか先に(必ずしも前ではなく)進んで行こうという雰囲気がある。 個人がどうやって戦と折り合っていくか。 けどなあ…この人は、ひとりの女子も出さずに男だけしか出てこない戦場だけ書いてくれれば好きなんだけど。女の子に夢見すぎ。
Posted by
沖縄で捕虜になった近藤義宗(阿賀野)軍曹。8月15日前後に起こるさまざまなこと。 憤怒が敵影を求める……いろいろな形の恨みのせめぎ合いで偽名を使わざるを得ない状況がある。「生者からは命令の実行をそしられる。死者からは命令の不実行をそしられる」泥沼状態が続く。 高江洲ミヨの...
沖縄で捕虜になった近藤義宗(阿賀野)軍曹。8月15日前後に起こるさまざまなこと。 憤怒が敵影を求める……いろいろな形の恨みのせめぎ合いで偽名を使わざるを得ない状況がある。「生者からは命令の実行をそしられる。死者からは命令の不実行をそしられる」泥沼状態が続く。 高江洲ミヨの生と死。収容所での自殺、私刑。所内でのボクシングと柔道の試合。山原に残る日本兵への投降勧告。そして、そこで見た「宝探し」の女学生の姿。 「収容所の人間を置き去りにして社会は移り変わっている」と捉える二世に対し「何も変わってなどいないし、変わる必要もない」と思う義宗だ。 作者は1970年生まれ。戦争を知らない若い作家のものとは思えない筆致だ。
Posted by
- 1