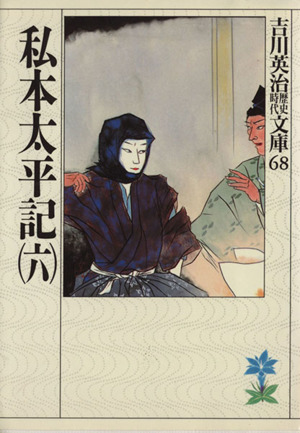私本太平記(六) の商品レビュー
建武新政成るが公家主導の政治に不満続出。大塔宮は尊氏を敵視。鎌倉では北条氏の残党が挙兵し直義を破る。尊氏は直義救援の兵をあげるが朝廷反逆となる。宮方新田義貞と朝敵尊氏の対決の構図となる。
Posted by
建武の新政が始まるが、内部対立ばかり。尊氏は後醍醐天皇の命令を受けずに鎌倉に戻り、さらに帝の命令で足利を打ちに来た新田義貞を退け、その勢いで上洛。しかし、義貞らの反撃を受け、いったん九州に引く。話の展開が早い。2020年4月からNHK BSプレミアムでやってる大河の「太平記」にや...
建武の新政が始まるが、内部対立ばかり。尊氏は後醍醐天皇の命令を受けずに鎌倉に戻り、さらに帝の命令で足利を打ちに来た新田義貞を退け、その勢いで上洛。しかし、義貞らの反撃を受け、いったん九州に引く。話の展開が早い。2020年4月からNHK BSプレミアムでやってる大河の「太平記」にやっと追いついて追い抜いた
Posted by
後醍醐天皇の元、集った将帥がついに袂を分かちます。 それにしてもこの時代の物事の進みの早さは凄いですね。
Posted by
建武新政への不満から、大塔宮を中心とする公卿方と足利尊氏は、対立を避けられなくなる。 大塔宮暗殺のあと、足利尊氏は、新田義貞を中心とする後醍醐帝の勢力に敗北を喫し、九州に逃れていく。 佐々木道誉の人を食ったような動きに圧倒されるとともに、足利尊氏と楠木正成らの互いに惹かれ合う関係...
建武新政への不満から、大塔宮を中心とする公卿方と足利尊氏は、対立を避けられなくなる。 大塔宮暗殺のあと、足利尊氏は、新田義貞を中心とする後醍醐帝の勢力に敗北を喫し、九州に逃れていく。 佐々木道誉の人を食ったような動きに圧倒されるとともに、足利尊氏と楠木正成らの互いに惹かれ合う関係が面白い。
Posted by
建武の新政は脆くも崩れさるわけだけど、人間の根源的な私欲が引鉄になるんだなぁ。そも皇室が二党になったのだって後醍醐が皇太子を自分で決めたかったからだし、新政を崩壊に向かわせたのは、阿野廉子が自分の産んだ子を皇太子に立てたかったから。 それにしても平安時代ならいざ知らず、自分では何...
建武の新政は脆くも崩れさるわけだけど、人間の根源的な私欲が引鉄になるんだなぁ。そも皇室が二党になったのだって後醍醐が皇太子を自分で決めたかったからだし、新政を崩壊に向かわせたのは、阿野廉子が自分の産んだ子を皇太子に立てたかったから。 それにしても平安時代ならいざ知らず、自分では何にもできない公卿ばらが、天下を我がものと思える感覚がまったく理解できないんだなぁ。
Posted by
(1991.06.28読了)(1991.05.16購入) 内容紹介 amazon 建武の新政が,早くも暗礁に乗りあげる――公卿は武家を蔑視し,武家は公卿を軽んじる.それが端的に論功行賞にあらわれ,武家の不満は爆発した.武家は不平のやり場を尊氏に求めたが,情勢は混迷を深める ☆関...
(1991.06.28読了)(1991.05.16購入) 内容紹介 amazon 建武の新政が,早くも暗礁に乗りあげる――公卿は武家を蔑視し,武家は公卿を軽んじる.それが端的に論功行賞にあらわれ,武家の不満は爆発した.武家は不平のやり場を尊氏に求めたが,情勢は混迷を深める ☆関連図書(既読) 「太平記の謎」邦光史郎著、光文社、1990.12.20 「私本 太平記(一)」吉川英治著、講談社、1990.02.11 「私本 太平記(二)」吉川英治著、講談社、1990.02.11 「私本 太平記(三)」吉川英治著、講談社、1990.03.11 「私本 太平記(四)」吉川英治著、講談社、1990.03.11 「私本 太平記(五)」吉川英治著、講談社、1990.04.11
Posted by
とうとう足利尊氏が活動開始。と言っても、彼自身が精力的に動いた訳ではなく、まずは弟の直義が護良親王を斬ることにより火蓋が落とされる。そしてそれでも頑として動かない尊氏。直義に散々説得されようやく重い腰を上げる。三国志の劉備しかり、吉川英治氏が書く英雄はこんな鈍な一面を持つ英雄が多...
とうとう足利尊氏が活動開始。と言っても、彼自身が精力的に動いた訳ではなく、まずは弟の直義が護良親王を斬ることにより火蓋が落とされる。そしてそれでも頑として動かない尊氏。直義に散々説得されようやく重い腰を上げる。三国志の劉備しかり、吉川英治氏が書く英雄はこんな鈍な一面を持つ英雄が多い。前巻までとは打って変わって流れるような話の展開であっという間に読めた。 一点だけ興味深かった点を列挙したい。 本作品ではあまり後醍醐天皇の心情は詳しく描かれないことが多いが、このセリフは中々粋だった。 「今の例は昔の新儀だった。朕の新儀はまた後世の先例となろう。藤房、そちには駸々たる時勢の歩が分からんとみえるな」 わかりやすく言えば、「前例は自身が作るものだ」というもの。皇族でこのようなセリフを吐いた人物は後醍醐天皇以外に知らない。隠岐に島流しに遭ったり、足利尊氏、新田義貞、楠木正成などの武士を良いように使ったりするさまは、まるでこの約150年前に幽閉されたり源氏と平氏などの武士を上手く使っていた後白河法皇とキャラクターが被る。
Posted by
尊氏と正成の同床異夢/中千代の乱と大塔宮殺害/尊氏朝敵へ/再上洛と都落ち。尊氏と直義の対立が少し浮き彫りになってくる。尊氏の深謀遠慮で不明確なところに業を煮やす直義の暴走、力技が自分の勤務先の状況と似ていて、ちょっと辛い。
Posted by
(全巻合わせた感想) 文章が読みやすく、状況描写が上手でその場の雰囲気や気持ちが手に取るように分かり、その文章の巧みさに感嘆した。内容は主人公尊氏及び周辺の人々に何らの魅力を見出せなかったので、少しつまらなかった。
Posted by
▼本を読んだ理由(きっかけ・動機) もともと吉川英治氏の作品は全て読破したいと思っていたため、いずれ読むつもりであった。 このタイミングで手をだしたのは、山岡荘八氏の『源頼朝』を読んで、鎌倉~応仁の乱を経て戦国に到るまでの歴史を改めて知りたいと思ったから。 「足利尊氏」という人物...
▼本を読んだ理由(きっかけ・動機) もともと吉川英治氏の作品は全て読破したいと思っていたため、いずれ読むつもりであった。 このタイミングで手をだしたのは、山岡荘八氏の『源頼朝』を読んで、鎌倉~応仁の乱を経て戦国に到るまでの歴史を改めて知りたいと思ったから。 「足利尊氏」という人物をぼんやりとしか知らなかったのも動機のひとつ。 ▼作品について 室町幕府を起こした足利尊氏を主人公に南北朝動乱の始まりから鎌倉幕府崩壊後の泥まみれの戦模様が描かれている。 これを読めば、室町幕府が早期に瓦解し、応仁の乱を経て戦国に突入した理由がよくわかる。 ▼感想を一言 切なくなった ▼どんな人におすすめ(気分、状況) 日常に疲れ、厭世観に付きまとわれている人。 「足利尊氏」の晩年の悲しさも最後の「覚一法師」の琵琶問答に救われる。 ▼作者について 歴史・時代作家としては吉川英治氏が描く作品は司馬遼太郎氏のリアリティとは違い、人間愛に溢れている。 作品は最後に”救い”があり、現実の厳しさの中にも一輪の花(希望)を咲かせるような 読む人を励まそうとするような一面があるように思える。
Posted by
- 1
- 2