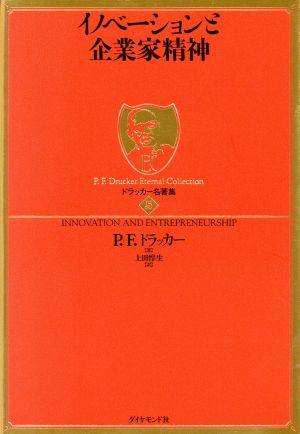イノベーションと企業家精神 の商品レビュー
1985年初版。イノベーションとは何か?というところから始まって、イノベーションを起こしうる7つの機会、「予期せぬ成功と失敗(=すでに起こった未来)」「ギャップ」「ニーズ」「産業構造の変化」「人口構造の変化」「認識の変化」「新しい知識」について、これらの機会をいかにイノベーション...
1985年初版。イノベーションとは何か?というところから始まって、イノベーションを起こしうる7つの機会、「予期せぬ成功と失敗(=すでに起こった未来)」「ギャップ」「ニーズ」「産業構造の変化」「人口構造の変化」「認識の変化」「新しい知識」について、これらの機会をいかにイノベーションに結びつけるかということを解説しています。イノベーションを創造するにはどうしたらよいか?を最初に解説した本と思ってください。歴史的には、この本の後に、クリステンセンの「破壊的イノベーション」やキム&モボルニュの「ブルーオーシャン」が出てくるのです。
Posted by
ドラッカーの著作の中で、経営者の条件の次に好きな本である。 予期せぬ成功に注目するが好きである。 リスクを適正に管理することが書いてある。 この本を読んで、そもそもリスクとは不確実性のことであり、リターンの源泉になることも学んだ。
Posted by
成熟市場においてイノベーションは易しくない。自前主義から脱却して異分野とのシナジーが必要。しかし、それを自ら知識として獲得し、活用し、実現しようとする企業家マインドをもっている人は少ない。
Posted by
変化の激しい時代になり、ドラッカーが挙げていたイノベーションの機会には溢れている。今はその一歩先、機会を捉えた上で、実現させる力の方が求められている。
Posted by
・予期せぬ成功は最もリスクが小さく、最も成果が大きいイノベーションの機会である ・予期せぬ成功を検討するために特別な時間を割き、分析すし、その利用法を徹底的に検討する仕事を誰かに担わさなければならない ・予期せぬ失敗もイノベーションの機会ととらえる ・アメリカのGEは財務畑の人物...
・予期せぬ成功は最もリスクが小さく、最も成果が大きいイノベーションの機会である ・予期せぬ成功を検討するために特別な時間を割き、分析すし、その利用法を徹底的に検討する仕事を誰かに担わさなければならない ・予期せぬ失敗もイノベーションの機会ととらえる ・アメリカのGEは財務畑の人物によってつくられた。知識のよるイノベーションの多くが、科学者や技術者よりも素人を父にもつ結果になっている ・イノベーションの三つの「べからず」――?凝りすぎてはならない?多角化してはならない?未来のために行ってはならない(現在のために行う) ・既存のものの廃棄は、企業がイノベーションを行うようになるうえで絶対に必要なことである ・イノベーションには予想以上の時間がかかり、予想を超えた努力が必要となる。また、最後の段階になって必ず問題や遅れが出るため、成果の規模を目標の3倍に設定することは初歩的な心得である ・多角化は市場や技術について既存の事業との共通性がない限りうまくいかない
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
・様々な気質の人が企業家として成功し得るが、確実性を求める人は企業家には向かない。 ・イノベーションは天才の閃きによってではなく、体系的に、計画的に行われるようになっている。 ・科学的な大発明より、些細な社会的改革の方が、市場で大きな成功を収める可能性が高い。 ・企業家はリスク志向ではない。むしろいかにリスクを減らすかを考える。彼らがイノベーションを行うのは、行わないことのリスクを避けるためである。 ・自分の製品が想定した目的と違うことに使われていることを機会として捉えよ。
Posted by
日本の競争力を回復するため、イノベーションの必要性が官民あげて叫ばれている。とくにIoT、AIを活用した業界を破壊するイノベーションが米国を中心に生まれていることから、彼らの手法に学べとデザイン思考、リーンスタートアップなどが大流行である。 このような流行は2010年ごろからだ...
日本の競争力を回復するため、イノベーションの必要性が官民あげて叫ばれている。とくにIoT、AIを活用した業界を破壊するイノベーションが米国を中心に生まれていることから、彼らの手法に学べとデザイン思考、リーンスタートアップなどが大流行である。 このような流行は2010年ごろからだろうか。 だが20年以上前に、あのドラッカーがイノベーションについて記したのが本書である。 イノベーションを体系的に行う手段として次のような内容が説明されている。 ・まず人口、経済、技術など7つの機会を分析する だがイノベーションは理論的な分析であるとともに知覚的な認識であるとして、 ・実際に外に出て、見て、問い、聞く という左脳と右脳の両方を使うことを強調し、実行する際には ・焦点を絞り単純な構造にする なぜならば新しいことは何が起こるのか分からないので単純でないと修正がきかないからだ。 表現は違うが、本質的には現代で言われていることと同じではないか。 本書はさらに、イノベーションのための組織、評価基準、ベンチャーの扱いなど多岐にわたって鋭い論考が述べられ、既存企業がイノベーションをうまく利用するための指針となる。 新しい本もよいが、この古典から学べることの方が多いと感じる。
Posted by
原文が難しいのか、翻訳が良くないためか、若干読みにくい部分はあるが、内容は非常に勉強になる。何度も読んで、できれば洋書版と照らし合わせて読みたい。
Posted by
ドラッカーのイノベーション論の集大成として知られる本書は1985年に出版されたものだが、30年以上経ってから読んでも学ぶべきところが多い。クレイトン・クリステンセンの「破壊的イノベーション論」、ジェフリー・ムーアの「キャズム理論」もその原型となる考え方は本書で既に述べられている...
ドラッカーのイノベーション論の集大成として知られる本書は1985年に出版されたものだが、30年以上経ってから読んでも学ぶべきところが多い。クレイトン・クリステンセンの「破壊的イノベーション論」、ジェフリー・ムーアの「キャズム理論」もその原型となる考え方は本書で既に述べられている。 名著と謳われ、既に古典となりつつある本書ではあるが、第1部「イノベーションの方法」に論じられている「イノベーションの7つの機会」については、いまだに重要性を認識していない企業が多いのではないだろうか。7つの機会のうち誰もが注目する「新しい知識の出現」についてはドラッカーは最もリスクが高いと指摘し、誰もが見過ごしがちな「予期せぬこと」を積極的に活用せよと説く。もし、ドラッカーの指摘を忠実に実践していれば、苦境に陥らずに済んだ企業も多かったに違いない。 第2、3部で論じられている「企業家精神」、「企業家戦略」にも現代の経営理論の原点となった考え方が散りばめられており、経営理論に精通した人にとっても、初学者にとっても有益だろう。 昨今のイノベーションブーム(?)の影響を受けたせいか、2015年に本書のエッセンシャル版も出版されている。こちらは内容を確認していないが、本書よりもページ数がやや少ない程度のようなので、個人的には本書の方をお勧めしたい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『マネジメント』のドラッカーがイノベーションについて書いた本。 どのような活動においてもイノベーションは必要である。 ただし、イノベーションは思いつきで起こすものではなく、ギャンブルでもない。理論に基づいて行うことが大切だということが、過去のイノベーションの事例からよく分かる。 企業家精神のある社員を育てるには、イノベーションの取り組みに対してマイナスの評価をしないこと。イノベーション自体リスクのあるものであり、失敗はつきものである。 一人一人が企業家精神を持って、柔軟に変化を起こしていける組織は強いと感じた。
Posted by