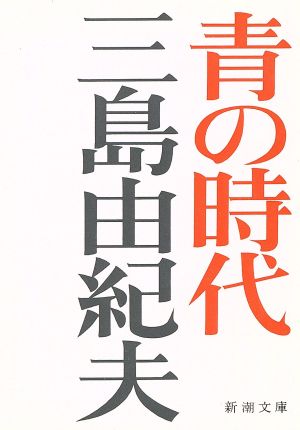青の時代 の商品レビュー
時代時代による違いは…
時代時代による違いはあるにせよ、参考にする点はかなりあった。
文庫OFF
「光クラブ」事件を題…
「光クラブ」事件を題材にした長編。必ずしも成功作ではありませんが、当時の感じが伝わってきました。
文庫OFF
硬質で流麗な芸術志向…
硬質で流麗な芸術志向の文章が、何よりも惹かれます。しかし、これは少しその魅力が少なかったです
文庫OFF
東大生が興した金融会…
東大生が興した金融会社の話。著者、世間の評価はイマイチだが、題材は結構面白いと思う。ライブドア事件が引き合いに出されるが、川崎誠と堀江は違う。川崎誠はどこまで進んでも欲望に対して清潔で行為に冷静な人間。堀江は俗っぽく、図太く、自殺などしない人間。
文庫OFF
「人生経験の胡桃のような硬い皮殻を割らずにただ掌で転がしている、そういう喜びに近かった」 「誠の唯物論と唯心論の総合とは、まず人間生活の物質面と精神論との区別から始める そもそも唯物論は金で買えないものはない、どんな形のものでも金で変えるというのが資本主義的偏見の私生児なのだ」...
「人生経験の胡桃のような硬い皮殻を割らずにただ掌で転がしている、そういう喜びに近かった」 「誠の唯物論と唯心論の総合とは、まず人間生活の物質面と精神論との区別から始める そもそも唯物論は金で買えないものはない、どんな形のものでも金で変えるというのが資本主義的偏見の私生児なのだ」 臆病 卑怯 弱虫 父親に脅かされて弱い自分への憐憫は他人の弱みを知ることで驚く速さでなくなっていくことを発見し皮肉や冷静さを育んでいく 再従兄の易が醸し出す純朴さなどに郷愁の念を持つ反面 センチメンタルと言われる縞柄は自分には似合わないとも考えている 感傷的でない英雄主義というものはないというかのようだ ストイックに未来を限定してその終着点を目指してがむしゃらに真面目にひた走る でもそれは限界を超えてない自分の出来る域を出ていない その結果 誰にも影響しない透明な存在になった 資本主義に対する皮肉が彼の厭世的な感情 物事を疑いながら自分の真理に固執 真理への探求が結局は他者からの理解や影響を遠ざけることになる またはそう求めている 誠の性格には幼少期から皮肉屋であることは他人より優れているという自負と または裕福であって他者を見下ろしているうちに彼にとって他人との比較は一種の自己防衛手段となる 満たされない優越感 誠が本当に求めているものなど描かれてない誠の人間像はそこに絶えず揺れ動く他人を凌駕したい欲望が渦巻いている 三島の懸念 戦後日本の道徳の変質や精神よりも物質に価値が置かれる風潮に疑問 計画的な人生を貫こうとする誠の姿勢 自分の考える真理以外は全て疑う 不自然さを伴う偽物の行動 疑いを持てば何処までも怪しく見えてくるもの それを誠は疑うものを限定している この犯罪めいた物語は今ではそう珍しい話ではない 金銭的な野心や成功を追い求める若者たちを三島は資本主義社会における道徳の崩壊や唯物論的な価値観が蔓延する社会に対する批評する
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
昔、光クラブ事件の再現ドラマを観て妙に印象に残ったのでこちらを手に取ってみた。 前半で語られる少年時代の成育環境が何とも言えず、大人になったらどうなるのだろうと興味深く読んだ。結局、誠の幸せは何だったのだろうかと、読後少し虚しくなった。 この本、たまに例え話の例え話を例え話するような形が出てきてややこしかったりする部分もあったけれど、三島由紀夫の男女縺れ合いな描写がとても好き。 誠がこの先自殺をする暗示めいた表現で書かれていたのみに終わっていたけど、最期のシーンも読んでみたかった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
「自身の過去=桎梏を、カネで塗り潰す」というテーマ。作中でも出てきた『金色夜叉』の、内面描写を強めた発展形だと個人的には位置付けたい。現代のテクノクラートや加速主義にまで射程が及びそうな、稀少かつ発展性のあるテーマ設定が好ましい。 『金と一緒に理解が通用する。堕落した時代だ。僕は金を楯にしてこの堕落から身を護らうとした。金が理解し~』……この作品の主題は、とにかくこれ。エリートの自意識なんて三島の自家薬籠中のモノで、まあ読ませてくれる。 金貸しになる経緯のところで川﨑の主体性があまり発揮されていないので、そこが受け入れ難いひとは多いかもしれない。自分はあまり気にならなかった。
Posted by
三島由紀夫がとある金融事件を元に書いたと言われる作品。 前半部分では主人公の人格の形成される過程がビビットに描かれており、ある種のジャーナリズム性さえも垣間見える。 極めて輪郭のはっきりしたエピソードで自尊心の強い異様な孤独を孕んだ少年の姿が思想そのものと共に示されていくが、六...
三島由紀夫がとある金融事件を元に書いたと言われる作品。 前半部分では主人公の人格の形成される過程がビビットに描かれており、ある種のジャーナリズム性さえも垣間見える。 極めて輪郭のはっきりしたエピソードで自尊心の強い異様な孤独を孕んだ少年の姿が思想そのものと共に示されていくが、六章の後半から一挙に六年を飛ばして戦後へ物語は紡がれていき主人公へ金融屋としての道へ歩を進める。 前半は物語ではない思想そのものが多く描かれ難解ではあるものの、その直接的な要素がこの小説の深度を深める要因となっていたように思える。 金融屋になってからの後半では、前半で描いた主人公の人格を元に小説もとい物語が紡がれていき、深度の沈み込みは緩やかとなり、展開的に話は進む。 三島由紀夫の描く戦後的なシニシズムな思考の主人公はその要素だけでも読み応えを持つのだと感じたが、前半の濃度を味わったからにはわずかな尻窄みを感じなくもない。 だが、三島の感情の論理を描くような文学センスは決して濁ることはなく、ややこしい青年心や自尊心はやっぱり混沌としていて面白い。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
(2023/07/05 2h) 解説読んで、なるほどアフォリズム!! 著者自身は納得いってないみたいだけど、 わたしは青の時代すきだなぁ。 ピカソも青の時代がいちばんすき。
Posted by
三島にも凡庸な作品がある。それでも戦後経済などに対する視点や描写は相当に鋭い。「明日をも知れぬものはかなげな紙幣の風情が、明日をも知れぬ欲望にとってふさわしい道連れのように思われた。」
Posted by