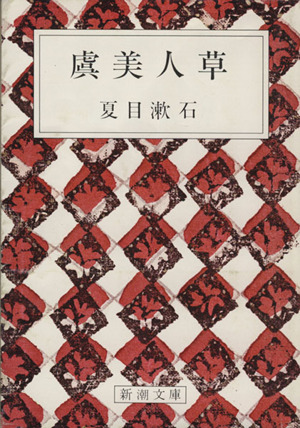虞美人草 の商品レビュー
シェイクスピア『ア…
シェイクスピア『アントニーとクレオパトラ』では二人とも死んでしまう。アントニーの死の原因には嘘がからむ。小野さんはどうか。藤尾はどうか。そして死という悲劇が訪れるとき、社会は「人生の第一義は道義にあり」、「第二義以下の活動の無意味なることを知る」。「悲劇は喜劇より偉大である」と...
シェイクスピア『アントニーとクレオパトラ』では二人とも死んでしまう。アントニーの死の原因には嘘がからむ。小野さんはどうか。藤尾はどうか。そして死という悲劇が訪れるとき、社会は「人生の第一義は道義にあり」、「第二義以下の活動の無意味なることを知る」。「悲劇は喜劇より偉大である」と漱石がいう理由である。 真面目になることは悲劇を生み出すこともある。でも悲劇はただ悲しむべき悲劇ではないのだ。そんなことを考えさせられる一冊。
文庫OFF
聡明で、美しく、自由…
聡明で、美しく、自由で、都会的だが俗世から離れ、詩人的に生きる女、藤尾を殺したのは、一体なんであろうか。漱石の「真面目に生きる」という哲学の表明ではなかろうか?「真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。遺っ付けるの意味だよ。遺っ付けなくちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味...
聡明で、美しく、自由で、都会的だが俗世から離れ、詩人的に生きる女、藤尾を殺したのは、一体なんであろうか。漱石の「真面目に生きる」という哲学の表明ではなかろうか?「真面目とはね、君、真剣勝負の意味だよ。遺っ付けるの意味だよ。遺っ付けなくちゃいられない意味だよ。人間全体が活動する意味だよ。」
文庫OFF
漱石のモラリストたる…
漱石のモラリストたる1面が表に出た、懲罰的なラストが印象的な1冊です。
文庫OFF
人名の呼称がコロコロ変わって場面を追うのが難しく、文章が少し難解で文量も多かったため読むのに時間がかかったが徐々に小野の煮え切らない性格のせいでどうしようもない袋小路に突き進んでいく様子は読んでて心が痛んだ。相手の気持ちを想像しすぎるあまり優柔不断になるのはよく分かる。道義が大切...
人名の呼称がコロコロ変わって場面を追うのが難しく、文章が少し難解で文量も多かったため読むのに時間がかかったが徐々に小野の煮え切らない性格のせいでどうしようもない袋小路に突き進んでいく様子は読んでて心が痛んだ。相手の気持ちを想像しすぎるあまり優柔不断になるのはよく分かる。道義が大切。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
中盤まで人物名が覚えきれず混乱したけど、覚えてからは割とすらすら読めた。 まず小野ーー!!という思い。小野が痛い目見るのかと思ったら藤尾さん死んじゃうし。小夜子と小野が結婚したとしても、一度は断っているわけで 宗近に諭されてはいっ真面目になります!小夜子と結婚します!って決めたとて、そんな二人がこの先幸せになれるのか?とか色々思った。 時代が時代だから今読むと、男側が勝手に女性をそっちにやるやらないとか男だけで話し合ったりしてて、うるせえ!と思ったり。笑 あとは映像が流れるような場面転換の仕方が印象的で美しかった。(人の前に風景や物の描写があって、そこに人がいるとあとで描かれたり) 甲野が今すぐ家を出ると決め、母がそれを止めている時の糸子の言葉がかっこよかった。 謎の女「だって、こんな雨が降って...」 糸子「雨が降っても、御叔母さんは濡れないんだから構わないじゃありませんか」
Posted by
「愛嬌と云うのはね、自分より強いものを斃す柔かい武器だよ」「それじゃ無愛想は自分より弱いものを、扱き使う鋭利なる武器だろう」 小野さんは自分と遠ざかるために変わったと同然である。 わが悪戯が、己れと掛け離れた別人の頭の上に落した迷惑はともかくも、この迷惑が反響して自分の頭ががん...
「愛嬌と云うのはね、自分より強いものを斃す柔かい武器だよ」「それじゃ無愛想は自分より弱いものを、扱き使う鋭利なる武器だろう」 小野さんは自分と遠ざかるために変わったと同然である。 わが悪戯が、己れと掛け離れた別人の頭の上に落した迷惑はともかくも、この迷惑が反響して自分の頭ががんと鳴るのが気味が悪い。 雷の嫌なものが、雷を封じた雲の峯の前へ出ると、少しく逡巡するのと一般である。只の気の毒とは余程趣が違う。けれども小野さんはこれを称して気の毒と云っている。 真面目と云うのはね、僕に云わせると、つまり実行の二字に帰着するのだ。口だけで真面目になるのは、口だけが真面目になるので、人間が真面目になったんじゃない。君と云う一個の人間が真面目になったと主張するなら、主張するだけの証拠を実地に見せなけりゃ何にもならない。•・・ 時代背景や価値観が違うから、全てを共感はできないけど、この行き場のなさはわかる気がする。高慢で魅力的な女は退場させられた。そんな時代。恋愛に限らないけど、恋愛の板挟みって神経すり減らす。まぁここでの板挟みは愛とか恋とかそんなのに拘うものではないのだけれど。 再読で、そう昔のことじゃないと思うんだけど全く覚えてなかった。漱石文学は展開に入るまでが難解だけど、いざ入ったらどことなく俗っぽくてすらすら読める。
Posted by
ようやく読みきれた『虞美人草』。前半部分は漢文調が続くので慣れるまで時間がかかりました。後半部分になって、登場人物の中でも話の要となってくる人物の正確や様子が分かってきて、徐々に作品に引き込まれていきました。それは男女間のもつれや師弟関係のしがらみがかかわってきているからだと思い...
ようやく読みきれた『虞美人草』。前半部分は漢文調が続くので慣れるまで時間がかかりました。後半部分になって、登場人物の中でも話の要となってくる人物の正確や様子が分かってきて、徐々に作品に引き込まれていきました。それは男女間のもつれや師弟関係のしがらみがかかわってきているからだと思います。このあたりから人の心にある弱い部分や傲慢が部分が感じられたのもあります。 また、虞美人草はひなげしのこと。花言葉は「心の平穏」「労り」「慰め」「思いやり」。作品の後半でようやくこのタイトルが登場人物の心の移り変わりを表しているようにさえ思えてきました。 宗近君が小野君にまじめに生きることを説く部分はすごいと思ったが、結末はすべてを藤尾さんに擦り付けたのでは?とおもえて仕方なかった。「労り」「慰め」「思いやり」を出しているように見える登場人物も、ちょっと自己中心的なものの考え方なのではと。 しかし、こういうところが、時代は違えど親近感があるようにも感じて興味深いと思いました。
Posted by
苦慮して作り上げた文体は正直なところ意味を掴めないが、美しさは伝わってくる。西洋的なハイカラな思想が昔ながらの考えにぶつかる、そこで起きる波紋というのも一つのテーマとして感じる。藤尾は美しく傲慢な女として描かれているが、こんな人は現実に実際いそうだ。自分の美しさを把握しているから...
苦慮して作り上げた文体は正直なところ意味を掴めないが、美しさは伝わってくる。西洋的なハイカラな思想が昔ながらの考えにぶつかる、そこで起きる波紋というのも一つのテーマとして感じる。藤尾は美しく傲慢な女として描かれているが、こんな人は現実に実際いそうだ。自分の美しさを把握しているから、人に対して小悪魔に振る舞ったりする。その我儘さが美しさに拍手をかける。みたいな。まぁ、こんな人には敵わない。なんだかんだで結局美しさに敵うものはないのではないか。と勝手に思ったりもする。 藤尾だけではなくて、この小説に出てくる人は皆現実にいそうだと感じる。それぞれが自立した性格を持っていて、そのもつれの中で結末を迎える。この小説の登場人物の内面が外界に働きかけることで小説が歯車のように回って、動いていく様は、少し離れたところで精巧で大きな機械仕掛けの時計を見ているような気持ちになる。 どう考えても、自他共に認める失敗作には思えなかった。
Posted by
本作は見事な美文調で書かれている勧善懲悪小説である。が、しかし正岡子規も指摘していたように、文章を飾ることに力を入れすぎていて、内容がおざなりになっていると感じた。物語のストーリーを期待して読むよりは、巧みな比喩表現や落語に則って描いた登場人物の言葉の掛け合いなどを味わって読む方...
本作は見事な美文調で書かれている勧善懲悪小説である。が、しかし正岡子規も指摘していたように、文章を飾ることに力を入れすぎていて、内容がおざなりになっていると感じた。物語のストーリーを期待して読むよりは、巧みな比喩表現や落語に則って描いた登場人物の言葉の掛け合いなどを味わって読む方がいいのかなと思った。
Posted by
「草枕」と同じく、とてつもなく難解な地の文。いやぁ、すごいですね。よくこんな文章が書けるものだと感心します。恐ろしい教養です。 それもすごいのですが、なんといっても会話がすごい。登場人物それぞれに何か秘めたるものがあり、自分の思惑に話を持っていこうとするが、相手はそうはさせじ意識...
「草枕」と同じく、とてつもなく難解な地の文。いやぁ、すごいですね。よくこんな文章が書けるものだと感心します。恐ろしい教養です。 それもすごいのですが、なんといっても会話がすごい。登場人物それぞれに何か秘めたるものがあり、自分の思惑に話を持っていこうとするが、相手はそうはさせじ意識的にか無意識にかする。そういったやり取りが、とてつもなくスリリングです。 登場人物の中ではやはり「藤尾」が魅力的です。おそらく漱石としては、藤尾を完全な悪女として描きたかったのでしょうが、思いのほかに筆が進んでしまったのでしょう。欠点があるのも人間らしさとして、また魅力の一つになっています。 その点で、最後の展開は納得がいかないです。浅井が孤堂先生に怒られる場面までは良かったです。その後の展開は作り事めいていて、なんかしっくりきません。おそらく同じように感じる人が多いと思います。 小野さんが孤堂先生のところに行って、ぼこぼこに怒られてへこんでしまい、その後藤尾が小野さんの様子を見て愛想をつかす、みたいな展開だったらめでたしめでたしだったのではないでしょうか。諸悪の根源は小野さんでしょう。 虞美人草は失敗作だという話もありますが、個人的には面白かったです。やっぱり会話シーンですね。全会話が名シーンです。小野さんと浅井とのあの馬鹿馬鹿しい会話ですら面白かった。
Posted by