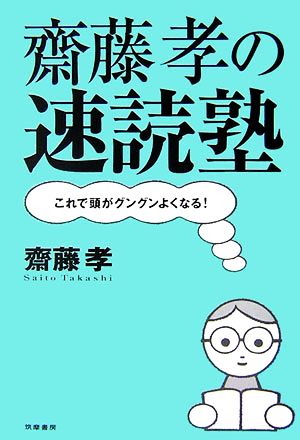齋藤孝の速読塾 の商品レビュー
本は偉人・著名人が自分のためだけに開いてくれる講演会。 (本内の192ページの個人的解釈です) 現代の知識人から、 ナポレオンなどの過去の偉人、 はたまた好きなアーティストなど、 話ができたら奇跡のような人物であっても、本を読むことでその人の視点や言動、考え方を知ることができる...
本は偉人・著名人が自分のためだけに開いてくれる講演会。 (本内の192ページの個人的解釈です) 現代の知識人から、 ナポレオンなどの過去の偉人、 はたまた好きなアーティストなど、 話ができたら奇跡のような人物であっても、本を読むことでその人の視点や言動、考え方を知ることができる。 この本でこのことに気がついて、 本をもっと読みたいと高揚しています。 他にも、本の読み方を ・どう考えて読むかといった意識的な所 ・印を付けたりキーワードを見つけながら読むといった 物理的な所 両面で具体例をたくさん交えながら教えてもらえます。 本は最初から最後まで読むべし。 という強迫観念から自由になろうとか、 右ページだけ読み進めて内容を把握していくとか、 なるほど!と思える発想がいくつも出てきますので 何かは、やってみたいことが見つかると思います。
Posted by
何度か読んでいる本であるが、久しぶりに再読した。 本書を読んだからと言って、速読の技術が身につく訳ではない。全体としては、本を早く読むための小ネタ集という感じだ。 本書で目指す速読は、単に早く読んだり、たくさん読むことではない。本の内容を把握した上に、新たな価値を付与して、オ...
何度か読んでいる本であるが、久しぶりに再読した。 本書を読んだからと言って、速読の技術が身につく訳ではない。全体としては、本を早く読むための小ネタ集という感じだ。 本書で目指す速読は、単に早く読んだり、たくさん読むことではない。本の内容を把握した上に、新たな価値を付与して、オリジナルなアイデアや提案、見方が出せることである。 本書の最重要箇所は、二割読んで八割理解する「二割読書法」である。まずは、「本は最初から最後まで読むものではない」という概念を頭に入れて、それから、読書を多くこなすことで、訓練的に身に付けるしかない。 速読系の本は十数冊以上は読んだが、本は全部読むものではないという概念は良く出てくる。本の内容にもよるが、実際には、2割拾って、8割を捨てるのは難しい。こればかりは、そういうものだと割り切って、多読して慣れていくしかない。 齋藤孝氏の本は総じて読みやすく、大きなハズレはないので、本を読むことに関心があれば、多くの人におすすめできる内容である。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2割だけよんで、8割の内容を理解する 多読する →知識が深くなる →一つにこだわりすぎない 表現するチャンス、アウトプットを逃さない →強制的な場を作れると尚良い →期限を決めてしまうのも良い 著者の考えになりきる →自分と違う考えでも受け入れる →著者の主張やテーマに違和感を感じたら注目 本の中の大事だったことを3つ挙げる →ベスト3方式も良い 本を読む時間がないと思うなら本当にダメが時間を挙げる →電車の中など案外読めるのに逃している
Posted by
内容は読書術の初歩から高度な評論家レベルまで。 2割を読んで8割捨てる。これは読書術でよくある公式。聞き飽きた。 本の中で引用したい文を持つといいらしい。人に話すと知的に見える。 読書は情報を得ることもだが読者の集中力を養うこともできるという。
Posted by
本に対してレベルの低い自分にはまだまだ足りないものが多い事を感じさせてくれる1冊です。 残された時間は少ないですが、照らし出された光の道筋に捕まり這い上がろと思います。
Posted by
速読、多読の効用について。 多読は読書の偏食を治す効果があることは納得がいった。 速読もキーワード拾いやベスト3を決めるという今までにない視点からの方法が紹介されており参考になった。 作者とちがい読者は順番通りに読まなくていい、全部を読む必要はないという意見は新鮮であった。...
速読、多読の効用について。 多読は読書の偏食を治す効果があることは納得がいった。 速読もキーワード拾いやベスト3を決めるという今までにない視点からの方法が紹介されており参考になった。 作者とちがい読者は順番通りに読まなくていい、全部を読む必要はないという意見は新鮮であった。 自分の読書は要約レベルでとまっていたので、より進めた自分の意見を述べるという段階を目標にしていきたいと思う。
Posted by
Aレベルの理解力とは、単に要約することではなく、新たな価値を付与して、オリジナルのアイデアや提案、見方が出せる力のこと。
Posted by
今までの読書の考えを少し改めさせてくれるような一冊。 単純に速読ができるようになりたいという思いで買ったが、いい意味で裏切られた。 自分は今まで、一冊の本を丁寧にみっしりと読んでいたが、ここでは何冊もの本を同時並行させながらキーワードに頼りつつ読み進めていくことが述べられており、...
今までの読書の考えを少し改めさせてくれるような一冊。 単純に速読ができるようになりたいという思いで買ったが、いい意味で裏切られた。 自分は今まで、一冊の本を丁寧にみっしりと読んでいたが、ここでは何冊もの本を同時並行させながらキーワードに頼りつつ読み進めていくことが述べられており、なるほどなと感じられた。 また、小説をはじめとした読書によって視点移動が生じ、包容力が生まれるだとか、新しい切り口を得られるだとか、そういう箇所で鼻かなり頷けた。 少しいやそれはないだろと思う箇所もあったが、それも含めて良い本だなとも思えた。
Posted by
読書で得た内容を実生活に活かすことを目的として読み方を述べている。 本は全文を読むのではなく大事な部分を選び取ることを基本とする。 要約の為になる。
Posted by
「言葉のブラウン運動」を起こす! 読書のスピード、スパンが速くて早いほど常に頭の中で言葉と言葉という粒子が乱舞し、動き続ける。言葉と言葉がぶつかり合う速度が高いほど何か刺激を与えたときに熱が高まり化学反応を起こす(新しい何かが生まれる)。 つまり多読は大事。
Posted by