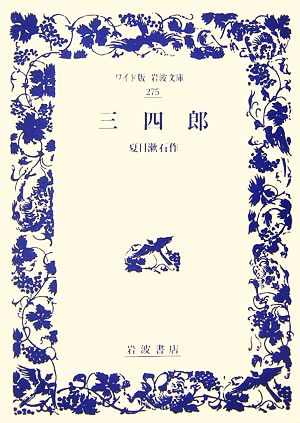三四郎 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
猫に続き三四郎。 明治41年9月から12月の新聞小説。 熊本から東京の大学に通うことになった三四郎の青春。 小川三四郎。 みねこさんがいろんな男の人の心を掴む。 当時の大学生の様子や生活もうかがえる。 そして、ほんとはみねこさんだれに心があったのかな?野々宮さんかな?振り向かないから振り向かせたかっただけかな? その2 熊本から東京の大学へ。 100年前の話とは思えないほど新鮮。 みねこさんの生き方は家と家との結婚で悩んでいるようにみえたけど、いまでも男尊女卑の考えは根強くあって、表向きは平等になったかもしれないけど明治の頃とかわってはいないのかも?とおもったり。 ヘリオトープ、ストレイシープ。やら聖書の言葉やら当時の人はどんなふうに読んだのかしら。
Posted by
漱石の前期三部作の一作目を読了。漱石が結局、何が言いたかったのかわからずじまいで終わってしまった。 ただ明治の時代の、地方から状況してきた若者の生活や成長の過程はよくわかった。明治の時代の高揚感のようなものも何か羨ましさを感じた。 さ、次は「それから」にいってみよう。
Posted by
情景の描写がとてもうまく、現代とは比べ物にならないほどゆっくり過ぎていく時の流れを感じながら読みました。
Posted by
朝日新聞の連載で読みました。当時の雰囲気もよみがえって、いい感じ。 三四郎のうじうじ感が現代でも違和感ない要因でしょうか。 上沼恵美子ブッククラブで取り上げて欲しい。もう、取り上げられてるかなあ。
Posted by
国語の教科書のようで敬遠してたが。。。読み始めるとどんどん進み、あっという間に完読。恋愛小説だったんだ。。。
Posted by
なるべくなら古地図がよいけれど、現代のものでもよいから、本郷あたりの地図を見ながら読んでみるととても楽しい。 外国語をそのまま訳したのであろう、当時の新鮮な言葉があちらこちらに感ぜられてとても感慨深い。 三四郎の雰囲気を与次郎が「世紀末」というところや、ぼそっとフランス語で「悪...
なるべくなら古地図がよいけれど、現代のものでもよいから、本郷あたりの地図を見ながら読んでみるととても楽しい。 外国語をそのまま訳したのであろう、当時の新鮮な言葉があちらこちらに感ぜられてとても感慨深い。 三四郎の雰囲気を与次郎が「世紀末」というところや、ぼそっとフランス語で「悪魔がついている」と皮肉る学生がいるところなど、胡椒のようにピリッと効いたユーモアも明治時代のものとは思えないほど古臭くなく、洒落ている。 よく小説家や漫画家が「頭の中で登場人物が勝手に動き回った結果です」みたいなことを言っているが、この作品もそのような考えのもと作られたものらしく、登場人物たちがとても生き生きしていて魅力的である。 夏目漱石の文章はなかなかリズムがつかめなくてあまりよい印象をもっていなかったが、この作品でかなり克服できた気がする。
Posted by
三四郎ぼんやりしすぎで、その間の抜けた感じに笑ってしまった。日常を描いてるけど、どんどん読み進めたくなる。
Posted by
美禰子さん! 登場人物が皆危うい感じ。 触れたら壊れる微妙な空気というか・・ 三四郎はうじうじと悩んでおります。恋愛小説なのかな? 暗いなあ・・と思いながら読みました。
Posted by
きちんと読んだのは初めてかもしれない。初の新聞小説『虞美人草』は美文すぎて投げ出しているのだが、この『三四郎』は新聞小説だと意識して読むと特におもしろい。冒頭部分なんかすごくうまい。汽車の中で相乗の女と絡ませ、広田先生と出会わせる発想は新鮮だ。漱石は女性を書くのは下手と聞くが、ど...
きちんと読んだのは初めてかもしれない。初の新聞小説『虞美人草』は美文すぎて投げ出しているのだが、この『三四郎』は新聞小説だと意識して読むと特におもしろい。冒頭部分なんかすごくうまい。汽車の中で相乗の女と絡ませ、広田先生と出会わせる発想は新鮮だ。漱石は女性を書くのは下手と聞くが、どうしてどうして達者なものだ。 野々宮よし子、里見美禰子に三輪田のお光さん……。 鷗外が刺激をうけて『青年』を書いたのもうなずける。 『漱石をよむ』と『悩む力』と併読した。
Posted by
- 1