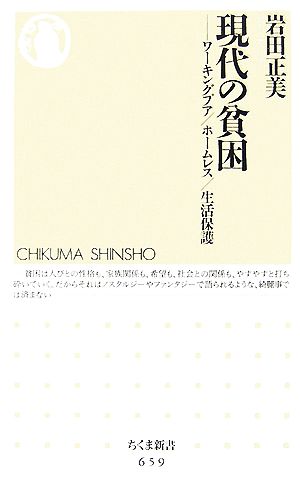現代の貧困 の商品レビュー
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480063625/
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
マクドナルド・プロレタリアート。 貧困と格差は違う。 格差とは、ある層とある層の開きなど状態を表す言葉であるが、貧困とは、社会的に解決すべきであるという価値判断が込められている。 統計上のサンプルだけでなく、幾つかの実例を紹介してくれたら、共感も呼び、より深く読めたのにと残念に思う。
Posted by
貧困問題が昨今になって注目されだしたのは、中流階級が下層へと下がっていくことで起きつつある格差の拡大に伴ってのことだ。しかし、貧困は格差とは関係なしに存在するところには存在していた。高度経済成長期の日本は国全体が裕福であれば貧困も自然となくなると考えていたようだが、実際は目をそら...
貧困問題が昨今になって注目されだしたのは、中流階級が下層へと下がっていくことで起きつつある格差の拡大に伴ってのことだ。しかし、貧困は格差とは関係なしに存在するところには存在していた。高度経済成長期の日本は国全体が裕福であれば貧困も自然となくなると考えていたようだが、実際は目をそらされていただけだ。 こういった貧困の問題は自分のことと重なるので読んでて絶望的な気分になる。 持つものはさらに恵まれて、持たざるものはさらに奪われる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2007年刊行。著者は日本女子大学教授。湯浅誠「反貧困」にも繋がるフレーズもあり、貧困問題の全体像を掴まえるには適している。格差社会、ワーキングプア、パラサイトシングルというようにバラバラに論じられていた貧困問題を全体的に整理した嚆矢とも言うべき書と思われる。特に貧困概念の整理は丁寧で、OECD採用にかかる「相対的貧困」の意味を知るには適切な書。加えて、疾病、特に生活習慣病と貧困の関係を指摘している点は注目すべきか。
Posted by
貧困とはなんだろうという点がまず重要です。貧困は、社会的に「あってはならない状態」であるとし、価値判断を含むもの、そして、社会的に解決しなければならないものとしています。 その貧困の例として、ワーキングプア、ホームレス、シングルマザー、生活保護を挙げ、その要因を分析しています。 ...
貧困とはなんだろうという点がまず重要です。貧困は、社会的に「あってはならない状態」であるとし、価値判断を含むもの、そして、社会的に解決しなければならないものとしています。 その貧困の例として、ワーキングプア、ホームレス、シングルマザー、生活保護を挙げ、その要因を分析しています。 最も興味深かったのは、貧困のバスの比喩で、貧困のバスには「常連さん」がたくさんいて、貧困層が特定の層に固定化されているということ。現代のわが国の福祉国家の政策が貧困層の固定化をもたらしているというのです。 では、改革案はというと、終章で説明されているのですが、こちらは新書レベルということで、定性的な説明であまり参考にはならなかった。
Posted by
国内の統計情報から貧困にまつわる数字に着目し、社会の傾向を読み取っていく一冊。ひとくちに「貧困」といっても大きく2つ、一時的なものか定常的なものかという分類とその中にいくつものパターンがあること、貧困に陥らないための抵抗力として最も効果を持つものが「家族」であることなどが数字の裏...
国内の統計情報から貧困にまつわる数字に着目し、社会の傾向を読み取っていく一冊。ひとくちに「貧困」といっても大きく2つ、一時的なものか定常的なものかという分類とその中にいくつものパターンがあること、貧困に陥らないための抵抗力として最も効果を持つものが「家族」であることなどが数字の裏付けとともに確認でき、納得感のある一冊でした。自分の身は自分で守るだけでなく、家族ね、そろそろ考えないとね、とか。
Posted by
ホームレスや生活保護受給者へのフィールドワークは頭がさがるが保証人になってくれと求められると遠回しに断るしかない。せつない。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
高度経済成長期のような「豊かな」時代において貧困は存在しないのだろうか。いや、貧困が存在するか否かは社会が豊かか否かとは関係ないのである。日本は戦後の経済が急速に発展する時代において、「貧困」はもはや存在しないものとして目を背けてきた。大切なのは、その時代において「貧困」を発見しようとする「声」や「目」があるか否かだ。 「貧困」と一口で言っても、どこからが貧困か、というラインの設定によって異なってくる。国際的な相対貧困基準や、制度によってラインが設けられる場合など様々な設定方法があるが、その歴史的背景を見ると、貧困ラインは社会の価値判断によって変動していると言える。そのため、社会にどのくらいの「貧困」が存在しているかを把握するのは難しい。また、本当に把握すべき対象こそがこの調査から漏れやすいという特徴もある。 そこで、「貧困」の増減ではなく、「貧困」を「経験」として見ることで、どれくらいの人々が「貧困」と言われるような時期を経験しているのか調べ、その経験が長期化している者(つまり、貧困層に固定化されている者)や、「貧困」とその少し上を定期的に上下している者(いわゆる低所得層など)こそが、本当に救わなければならない対象であるということを明らかにしている。この結果から、「貧困」と結びつきやすい項目(低学歴、非正規雇用、パート・アルバイトなど)の存在も指摘している。 また、本書ではホームレスに関して、統計結果やインタビュー調査などを用いて詳細な分析を行っているが、ホームレスなどはまさに「貧困」が目に見える形で社会に表れている最たる例である。しかし、いわゆる「ホームレス」で想像されるような路上生活を行っている者のように目に見える形だけではなく、例えば職場の宿舎で住み込み労働をしている未婚の単身者などは、万が一職を失うことがあれば家をも失いホームレスになる可能性も高い。このように、目には見えない形での隠されたホームレスも多く存在しているに違いないと著者は述べる。 貧困の要因は様々であるが、そこには一定の傾向があり、貧困に陥りやすいリスクを抱えた「不利な人々」の存在もまた、見逃せない。本書で述べられているものとしては、低学歴、未婚や離婚、転職や離職、そして資産や実家の経済力などの、貧困に対する「抵抗力」の弱さだ。これらの条件が必ずしも「貧困」につながるわけではないが、多くの調査結果などを分析すると、「貧困」との深い関連は無視できない。 「貧困」は、児童虐待や病気、自殺などの原因にもなりやすく、「貧困」だけで終わる問題ではない。著者はこのような現状に対して1つの解決策を提示している。 まず、現代日本の「保険大国」の現状は、本来不利な状況にある人々を救うべき福祉制度が、逆に不利な人々を不利な状況に固定し、有利な人々に働きやすいようになってしまっている。なぜなら、保険は保険料を払う必要があり、納める保険料の額によっても給付額が変わる。つまり、低所得者にとっては、負担になる上に十分な額の支給を受けることができないのだ。母子家庭への支給の不十分さも問題視されており、子供に対する手当も十分でない。そこで著者が挙げるのは、そのような不利な人々への「積極的優遇政策」である。国家が福祉政策に力を入れるのは、社会統合・連帯の必要性からであり、彼らの人権ばかりがクローズアップされるから不公平だという議論を退けている。 この本が書かれたのは2007年のことだが、7年経った現在と比べてどうだろうか、ということを考えた。ホームレスがどれだけ存在しているのかは、本書でも述べられていたように、把握するのが難しそうだが、1番思うのは、母子家庭への手当の不十分さは変わっていないし、また自分の実感としては、ワーキングプアの存在は前より目に見えるようになってきたと思う。また貧困の要因の1つに「低学歴」が挙げられていることは、社会全体が高学歴志向になってきていることの現れのように感じた。それは即ち、「中卒で専門的技術を身につけ働きに出る」といったような生き方は社会によって否定され、「受験を経験し、高学歴としての教養を手に入れてから職に就く」といった生き方を社会全体が強いているということではないかと思うのである。
Posted by
貧困は、それをどういうものとするかによって、変わりうる。日本は高度経済成長を経て貧困がないものとされたが、それは発見しようとしていなかったためであって、存在していた。 貧困が続している層というのは存在するが、それを見ようとしない、そしてそれに対しての適切な再分配がない。 貧困は学...
貧困は、それをどういうものとするかによって、変わりうる。日本は高度経済成長を経て貧困がないものとされたが、それは発見しようとしていなかったためであって、存在していた。 貧困が続している層というのは存在するが、それを見ようとしない、そしてそれに対しての適切な再分配がない。 貧困は学歴などが関係しており、連鎖する。
Posted by
ひとくちに貧困といっても、その程度はさまざま。大卒フリーターと中卒日雇いなど、今や多様なケースがありうる。 契約で宿舎住まいともなると、仕事がなくなった途端にホームレスである。 こうした人々は貧困のなかでもさらに不安定な生活を余儀なくされ、さらには社会から除け者にされた状態で生命...
ひとくちに貧困といっても、その程度はさまざま。大卒フリーターと中卒日雇いなど、今や多様なケースがありうる。 契約で宿舎住まいともなると、仕事がなくなった途端にホームレスである。 こうした人々は貧困のなかでもさらに不安定な生活を余儀なくされ、さらには社会から除け者にされた状態で生命の崖っぷちを彷徨っている。 格差社会というのは「貧富関係なく全ての」人々にとって悪影響を及ぼすことが分かっている。 しかも、本当の貧困は隠れたところにこそあるのだ。 「統計にすら入れてもらえない人」の存在を抜きにしていては、解決しない。
Posted by