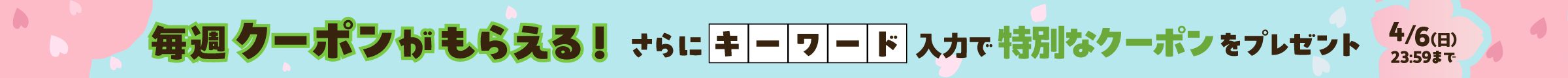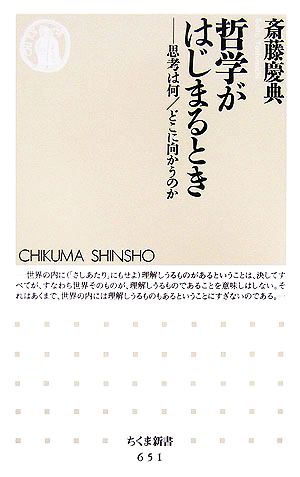哲学がはじまるとき の商品レビュー
著者が、「哲学」と呼ばれる思索の営みの始まりから、「存在」そのものを問う形而上学への歩みを読者の前で実演して見せた本です。 著者は、世界に対する当惑から「どうして?」という問いが始まるとき、「哲学」と呼ばれる営みが開始されることになると論じています。「どうして?」という問いは、...
著者が、「哲学」と呼ばれる思索の営みの始まりから、「存在」そのものを問う形而上学への歩みを読者の前で実演して見せた本です。 著者は、世界に対する当惑から「どうして?」という問いが始まるとき、「哲学」と呼ばれる営みが開始されることになると論じています。「どうして?」という問いは、理由や根拠、意味や本質への問いかけを含んでいますが、とりわけ「存在とは何か」という世界全体への問いかけがおこなわれるとき、われわれはそれを「形而上学」と呼ぶと著者はいいます。 その上で著者は、「存在とは何か」という問いは果たして可能なのだろうかと、改めて問いかけます。ライプニッツは「なぜ世界は存在するのであって、むしろ無ではないのか」と問いましたが、パルメニデスが主張したように、「あるものはある、ないものはない」のであれば、「無とは何か」と問うことができないように、「存在」そのものを問うこともできないように思えます。しかし著者は、そのような仕方でわれわれは「存在」の外部の「無」に触れてしまっているのではないかと反問します。 さらに著者は、パルメニデスにしたがうならばけっして移ろうことも分割することもない「存在」の中に、時間と空間、さらには概念の象りによって「距離化」ないし「疎隔化」が生じて、「あるものはある、ないものはない」という空虚な充満でしかない「存在」の中に「何か」が生まれてくる機序を解き明かします。そのうえでカントの「超越論的統覚」に関する思索を手がかりにして、そうした「何か」が生まれてくる場に居合わせる「私」のあり方を論じ、西田幾多郎の「場所」の思想を手がかりにして、「何か」が「私」や「他者」たちによって述語づけられることでそれが「何か」を十全に示すようになることについて考察を展開しています。 本書を通じて、「存在そのもの」を問う思索の「途方もなさ」に触れることができたような気がします。
Posted by
【目次】 1. 思考 1-1. 当惑 1-2. 問い 1-3. 哲学 1-4. 形而上学 2. 世界 2-5. 存在 2-6. 時間 2-7. 私 2-8. 真理 2-9. 場所 【概要】 哲学とは個々人が日々行っている思考そのものであり、一般理論や基礎概念などない。 したがっ...
【目次】 1. 思考 1-1. 当惑 1-2. 問い 1-3. 哲学 1-4. 形而上学 2. 世界 2-5. 存在 2-6. 時間 2-7. 私 2-8. 真理 2-9. 場所 【概要】 哲学とは個々人が日々行っている思考そのものであり、一般理論や基礎概念などない。 したがって、哲学の世界に入りたいのであれば、個々の思考に出会い、自分で思考してみなければならない。 本書は、思考から哲学へと展開する過程を説明した上で、筆者自身の思考を提示することで、読者の思考を奮起させるものである。 以下、自分なりのまとめ。 前半は、思考が生まれて狭義の哲学である形而上学へと展開する過程を説明する。 すなわち、世界の偏差に驚くことから思考が生まれ、その思考が偏差の根拠を追い求める過程で、特定の対象について特定の形式で根拠をもとめる個別学(例:幾何学、自然科学)と、全ての対象に共通する「存在すること」について問う形而上学とに発展していく。 後半は、筆者自身が思考してきた哲学をまとめる。 まず、存在と無とは裏表の関係であり、「存在とは何か」という問いは、「無とは何か」という問いと同様、ナンセンスであると述べる。 次に、時間と空間との隔たりを導入することにより、存在ではなく存在者が生成消滅するという形で、何かが存在するといい得ることを述べる。 そして、そのような異なる時空間で生成消滅するそれぞれの存在者が同一のものであるというためには、想像力と概念の力とが必要であり、複数の対象に同一の想像力がはたらいていることの根拠として私が規定されることを述べる。 (真理、場所については要約不能) 【感想】 結局個人の中で閉じてしまう思考に、何の意味があるのだろう。 哲学が個々人の日々の思考そのものなのだとしたら、プロの哲学者と僕たちとは何が違うんだろう。 デカルトやらカントやらハイデガーやら、それぞれの思想はお話としては知っているけど、その思想が歴史上どんな役割を果たしたのか、よく知らない。 その辺の影響について、もうちょっと調べみたい。 内容そのものについて。 後半2章は意味不明。 全編通じて(特に第2部)、言葉遊びとしか思えない。 「存在とは何か」という問いについて、最近読んだ2冊は好対照だった。 (1)そもそもこの問いは意味をなさないとした上で、思考が意味を持ち得る限界を探る本書。 (2)この問いにこたえるには、「ある」「いる」「てにをは」といった日本語の意味内容を理解し、日本人が物事を理解する仕組みを把握するところから始めなければならないとする、「日本語の哲学へ」。 どちらも「で、結局なんなの?」という尻切れとんぼな感じもなかなか。 この手の本の好きになれないところをいくつか。 (1)推論に推論を重ねた結論がいつの間にか定理扱いされる様。 例:AはBであるとはいえないだろうか。 もしそうだとすると、BはCといえるのかもしれない。 すなわち、AはCに他ならないのだ。 (2)根拠不明または実証不可能な断定。 例:AはBである。 なぜなら、AはB以外ではありえないからだ。 本書の最終章など、そんな断定ばかりで理解できない。 (3)以後の論証において何の役にも立たない用語の定義。 例:本書の「真理」の定義。 最終章では真理について一切触れられない。 (4)間違った、または、理解の役に立たない科学思想の引用。 例:本書において、重力の根拠は「地球の自転」だそうです。 『「知」の欺瞞』、そのまま。
Posted by
哲学するということ。問うこと、考えること。存在の話につなげたのは納得だが、有無だけではなく「ゼロ」も必要では。
Posted by
思考とは反復であり、反復の中核をなすのは偏差(ずれ)である。 「思考とは何であるか」と問うことに始まり、哲学の意味、存在や時間などの形而上学について細分化され書かれている。 最初は具体的な例も挙げられていて内容を理解することが出来たけど、徐々に抽象的な話になってきて完全に...
思考とは反復であり、反復の中核をなすのは偏差(ずれ)である。 「思考とは何であるか」と問うことに始まり、哲学の意味、存在や時間などの形而上学について細分化され書かれている。 最初は具体的な例も挙げられていて内容を理解することが出来たけど、徐々に抽象的な話になってきて完全に消化出来なかった。 ぼんやりと考えていたこと言語化すると、こんな風になるのかなぁと思った。 でもやっぱり今の私には少し難解なので、もう少し哲学に深く踏み入れることが出来るようになってから再読してみたいと思う。
Posted by
- 1