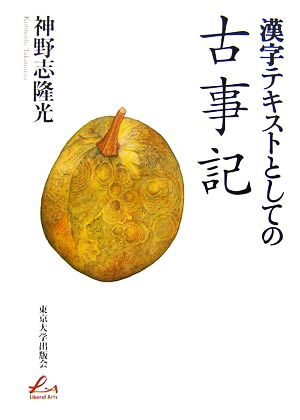漢字テキストとしての古事記 の商品レビュー
外来の文字である漢字を使うことで、ようやく『古事記』という作品が成立したことの意義を、さまざまな実例を通じて解説している本です。 著者はまず、7世紀から8世紀の日本において、漢字を用いて文を記すということが、どのようなしかたでおこなわれてきたのかということを説明します。そこでは...
外来の文字である漢字を使うことで、ようやく『古事記』という作品が成立したことの意義を、さまざまな実例を通じて解説している本です。 著者はまず、7世紀から8世紀の日本において、漢字を用いて文を記すということが、どのようなしかたでおこなわれてきたのかということを説明します。そこでは漢文とともに、著者が「非漢文」と呼ぶ漢字テクストが存在しており、そうした文字環境のもとで『古事記』という作品が誕生したことが指摘されます。つづいて著者は、『古事記』の漢字テクストの実例を紹介し、その検証を通して、漢字を用いて表記することが『古事記』というテクストそのものの本質的な性格を規定していることを明らかにします。こうした議論を通じて著者は、漢字テクストである『古事記』の向こう側に、古くから伝承されてきた物語を見ようとすることが困難であると主張します。 さらに著者は、散文と歌の表記のちがいに注目します。両者が異なる叙述をもつということが意味しているのは、これら二種類の叙述を並行したままに含んでいる『古事記』というテクストそのものが、伏線的な構造をもっていることだと著者は論じています。こうした議論を通じて、『古事記』というテクストそのものが「多声的」な読みかたをなされなければならないという考えが示されます。 著者が東京大学で、入学したばかりの学生に向けた講義をもとにしているということで、読みやすい文章でつづられています。また、著者の『古事記』解釈の基礎になっている多くの具体例が示されており、著者の本のなかでは比較的わかりやすい内容だったように思います。
Posted by
- 1