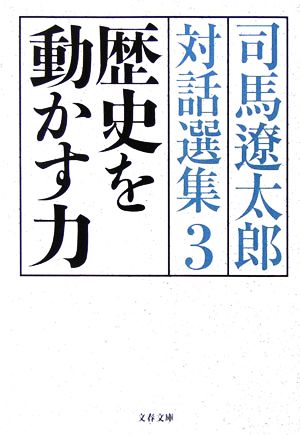司馬遼太郎対話選集(3) の商品レビュー
勝海舟を幕末・維新の織田信長扱いするのはいいとして、田中角栄を秀吉に見立てて評価し、福田赳夫を明智光秀扱いするのはどうなんだろうか?ちなみに三木が細川、大平が家康らしいが。今太閤っていうぐらいだから田中角栄は人気があったんだろうし、そういう時代だったのだろう。ただし、その後秀吉が...
勝海舟を幕末・維新の織田信長扱いするのはいいとして、田中角栄を秀吉に見立てて評価し、福田赳夫を明智光秀扱いするのはどうなんだろうか?ちなみに三木が細川、大平が家康らしいが。今太閤っていうぐらいだから田中角栄は人気があったんだろうし、そういう時代だったのだろう。ただし、その後秀吉がどうなったかを考えれば、田中角栄がどうなるかも想像がつきそうなものだが、そういった洞察力がないのは気になるが仕方のない事か?歴史とは過去に学んで、現代や未来を考えるためのものだと思っているが、一流の歴史作家と言われる人であっても現代や未来を的確に考える事が難しいという事を痛感させられる。司馬も時代のムードに流されてしまったという事だろうか? 作家の役割は物語を創作する事であって、歴史上の人物に関しては好き勝手に想像力を膨らませて自由に語ればいいと思うし、その想像力と文体が作品の面白さを左右するんだろう。実際、司馬の人物評は読んでいて面白い部分もある。しかしながら、政治史や経済史に関してはやはり学者の方がしっかり研究しているので、作家の想像力で適当な事を言うのは間違いが多く有害であり、読み手はその辺をきちんと区別していく必要はあるだろう。
Posted by
司馬遼太郎対話選集3 対談相手は、海音寺潮五郎、子母澤寛、江藤淳、奈良本辰也、大江健三郎等々。 特に、海音寺潮五郎、江藤淳との対談が面白かった。 海音寺潮五郎は司馬の文壇デビューに際して、早くから司馬を評価し、処女作の「ペルシャの幻術師」の講談社倶楽部賞受賞や2作目の「梟の城」...
司馬遼太郎対話選集3 対談相手は、海音寺潮五郎、子母澤寛、江藤淳、奈良本辰也、大江健三郎等々。 特に、海音寺潮五郎、江藤淳との対談が面白かった。 海音寺潮五郎は司馬の文壇デビューに際して、早くから司馬を評価し、処女作の「ペルシャの幻術師」の講談社倶楽部賞受賞や2作目の「梟の城」の直木賞受賞に繋がっている。司馬も「路傍の私に、氏が声をかけてくださらなかったら、私は恐らく第3作目を書くことをやめ、作家になっていなかったであろう」と巻末に書いている。謂わば文壇で最初に司馬を見いだしてくれた恩人。 その二人が「天皇制とはなにか」「西郷と大久保」等々、縦横無尽のやりとりは他に類がないほど面白い。二人とも歴史の巨人というに相応しい。 「応仁の乱前後、京都で盗賊が横行し、あらゆる物持ちの家や蔵は常に脅かされているが、盗賊は塀一重の御所だけには入らない(司馬)」「(明治維新での天皇制を)今になって、何だかんだと批判しても、当時のあらゆる条件を考えての批判ではなく、一握りか二握りの条件で論じている(海音寺)」のくだりは面白かった。 江藤淳との対談の展開はスリリングで楽しい。司馬遼太郎と江藤淳は同時代に活躍しているが、この対談を読むまでは、接点がないまますれ違っていたと思っていたが、それなりに接点はあったのは驚きだった。江藤は司馬より9歳年下で、考えれば生意気(きっと生意気だっただろう)と思われるが、司馬の寛容さがそれを受け入れている。結果二人の知識の幅、深さの凄さを知る喜びにも繋がる。 江藤は(慶應出身なので)近親憎悪と言っているが、福沢諭吉への冷徹な視線は新鮮。二人で勝海舟と福沢諭吉とを対比するやりとりは面白い。 司馬が「坂の上の雲」を書く時に陸戦については苦労した経緯を述べて「(日露戦争の)陸戦資料はうそをついている。真相をつかみ、それを復元してみたら、陸戦は勝ち負けなしで、やっと日本海海戦で締めくくっただけ・・(略)・・勝った国の陸軍というものは都合のいい戦史を作る・・(略)・・日本が勝っていなかったということを知れば、きっと太平洋戦争をせずにすみましたよ。そこを突かなかったマスコミの責任もある」 司馬遼太郎が「坂の上の雲」で、最も言いたかった事であったと思う。
Posted by
吉田松陰と正岡子規の共通点に関する話ひとても興味を惹かれました。至極明晰な言葉と文章。対等な後進との友誼と一人一人を見切った熱心な教育。そして何にも勝る思想、志し。橋川文三氏と奈良本辰也氏は当時の松陰研究を牽引されていたと言う。 奈良本辰也氏の葉隠の話も面白い。18世紀初めに佐...
吉田松陰と正岡子規の共通点に関する話ひとても興味を惹かれました。至極明晰な言葉と文章。対等な後進との友誼と一人一人を見切った熱心な教育。そして何にも勝る思想、志し。橋川文三氏と奈良本辰也氏は当時の松陰研究を牽引されていたと言う。 奈良本辰也氏の葉隠の話も面白い。18世紀初めに佐賀県鍋島藩の家士山本常朝のしるした武士道哲学。仏グウルモン「思想の偉大さは常に極端論の中にのみある。」 三島由紀夫のすすめ、とともに確認する。 江藤淳氏との対談部分は最も展開が自由でスリリングで楽しい。結果両氏の知識の幅、深さ思い知る。慶應の教授の福沢諭吉への冷徹な視線は新鮮。勝海舟と福沢諭吉への対比論も面白い。織田信長と勝海舟を国際関係の中の日本を感覚として理解したものとして共通に語るのも楽しい。 芳賀徹氏との坂本龍馬の手紙論も楽しい。読んでみます。文中引用の亀山俊介氏の幕末文学の傑作龍馬の手紙はAmazonに見つけられず。 大江健三郎氏との対談は、お二人の思考空間の確かさ厚さ深さに圧倒される。最も好きです。憧れます。 子母沢寛、海音寺潮五郎お二人は本当に司馬遼太郎氏が好きで応援しています。朝尾直弘氏の奉公と言う言葉との解釈から武士の教育の大衆化、一般普及の解説も納得。 司馬遼太郎さん本当に凄い。改めて敬服
Posted by
ロシア人は貴族が士官をやっていたが、日本は平民が士官をやっていた、これで日露戦争に勝利した。トルコも同じ。 ソ連の国旗が主義の象徴であるように、アメリカの星条旗はアメリカ人にとってアメリカ的社会の方式、思想の象徴。だから共産主義については国益問題を離れて宗教的感情というべき嫌悪...
ロシア人は貴族が士官をやっていたが、日本は平民が士官をやっていた、これで日露戦争に勝利した。トルコも同じ。 ソ連の国旗が主義の象徴であるように、アメリカの星条旗はアメリカ人にとってアメリカ的社会の方式、思想の象徴。だから共産主義については国益問題を離れて宗教的感情というべき嫌悪感を持っている。 沖縄は戦略的に重要なところで、それが悲劇の原因になっている。
Posted by
---------------------------------------------- ▼ 100文字感想 ▼ ---------------------------------------------- 司馬遼太郎と海音寺潮五郎、江藤淳、大江健三郎、子 母澤寛らとの歴史...
---------------------------------------------- ▼ 100文字感想 ▼ ---------------------------------------------- 司馬遼太郎と海音寺潮五郎、江藤淳、大江健三郎、子 母澤寛らとの歴史対談。吉田松陰や坂本龍馬、幕末な ど興味深いテーマがそろった一冊。こんなにも難しい話 をすらすら〜と対談できるという点が、いちばんの驚き。 ---------------------------------------------- ▼ 5つの共感ポイント ▼ ---------------------------------------------- ■吉田松陰、坂本龍馬もずいぶん旅行している。歩い ていると、会いたい人や会えば自分を啓発してくれる 人などに無数に出会う ■「立派な武士になるには、まず歴史をやれ。そして 旅行せよ」(荻生徂徠)歴史をやって時間的に過去 にさかのぼって広い世界を知り、旅行をして空間的 に広い世界を知れば、目が開かれるようになって 人生を知る、社会を知る ■史料はクソでもミソでも手の届く限り漁れ。品別は やっているうちに自然にわかってくる ■新聞だけは信用できる。新聞が野党を構成してい て、作用反作用のバランスをとって、視点を水平に 保つ機能をはたしていたと思っている ■意識するかしないかは大きな違い。一挙手一投足 を気にして見ている人間とそれを知らずにいる人間 では、宿命的な開きがでる
Posted by
個人的には、海音寺潮五郎との対談が一番興味を持てました。普段生活している中で漠然と感じる「日本人とは?」という問いに、考え方のヒントを与えてくれたかと。1969年に行なわれた対談ということだが、時代を超えて共感できる内容。 勝海舟の人間性についての議論with江藤淳もおもしろい...
個人的には、海音寺潮五郎との対談が一番興味を持てました。普段生活している中で漠然と感じる「日本人とは?」という問いに、考え方のヒントを与えてくれたかと。1969年に行なわれた対談ということだが、時代を超えて共感できる内容。 勝海舟の人間性についての議論with江藤淳もおもしろいです。海舟の100万分の1でいいので見習っていきたいなとおもいますた
Posted by
幕末、明治維新で活躍した人達を中心にして、日本人の根底にある精神とは何か、当時活躍した人達がどのような人物だったかということを余すことなく語られている。大局的にものを見る力や本質を見抜く力が大事だと感じた。
Posted by
- 1