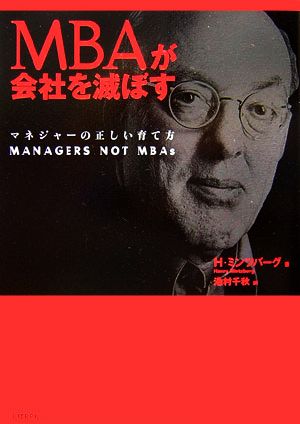MBAが会社を滅ぼす の商品レビュー
MBA取得者の成功率がひどい。人として学ぶべきことを学ばず、小賢しいテクニックばかり身に付けた小人の顛末なのだろう。
Posted by
マネージャーとしてのキャリア・スキルアップ目指す人向けではなく、経営者(もしくは日本企業の人事部)がいかにして有能なマネージャーを育成もしくは獲得すべきかという目線で役に立つ本。 これからマネージャーを目指す人は、表題どおりに「MBAではマネージャーとして育つことができない」とM...
マネージャーとしてのキャリア・スキルアップ目指す人向けではなく、経営者(もしくは日本企業の人事部)がいかにして有能なマネージャーを育成もしくは獲得すべきかという目線で役に立つ本。 これからマネージャーを目指す人は、表題どおりに「MBAではマネージャーとして育つことができない」とMBA行きを辞めるのではなく、「みんながMBAが役にたつと勘違いしているなら敢えて箔付けにいこう」ぐらいでよいのではないか。少なくとも、MBAで教えられるような科目はよきマネージャーの必要条件(基礎知識)ではあるのだから。
Posted by
150411 中央図書館 若者に、自分が経験したわけでもないケースを何百と読ませたところで、即、マネジメントができるようになるわけでないのは、その通り。会社の現場の仕事にうんざりしてMBAでもとろうか、と考えている若い人は、この本をぜひ読んでほしい。マネジャーたることの必要条件は...
150411 中央図書館 若者に、自分が経験したわけでもないケースを何百と読ませたところで、即、マネジメントができるようになるわけでないのは、その通り。会社の現場の仕事にうんざりしてMBAでもとろうか、と考えている若い人は、この本をぜひ読んでほしい。マネジャーたることの必要条件は経験値である。ケースで学んだ「広範なものの見方」は、ビジネススクールを出た後、何年も実務をやって初めて効果を現すだろう。MBAで学ぶことは財務や価値分析の役には立つだろうが、マネジメントには関係がない。
Posted by
ようやく読破できた。 会社を滅ぼすかどうかは分からない(他にも滅ぼす要因がたくさんあるから)が、これまでMBAホルダー(特に若い人)に対して漠然と抱いていたネガティブなことを結構可視化してくれた気がする。 日本と欧米とはおそらくかなり違うのだろうけれど。
Posted by
MBAが役に立たない、と言うだけに止まらず、色々と考えさせる本。深い。 これ、2006年発刊なんだね。リーマンショックを経て、世界は全く変わってないように見える。 「株主価値は、反社会的なドグマだ。民主主義社会に居場所はない。それ以上言うことはない。」 ・・・喝破されとるな。同...
MBAが役に立たない、と言うだけに止まらず、色々と考えさせる本。深い。 これ、2006年発刊なんだね。リーマンショックを経て、世界は全く変わってないように見える。 「株主価値は、反社会的なドグマだ。民主主義社会に居場所はない。それ以上言うことはない。」 ・・・喝破されとるな。同感ですが。 8章、企業のマネージャー育成、は一読に値する。日本企業のOJT、米陸軍のシミュレーションプログラム、GEのワークアウトなど。やるべきことはたくさんあって、かつ企業別に独自に作り上げるしかないようだ。 現在のMBAプログラムの批判に多数のページを割いているが、門外漢には理解できないし、ある意味どうでも良い。ビジネススクールに洗脳されない、or 洗脳を解くには必要かもしれないが。
Posted by
長い・難解・長い。。。 読み終わるのに、多分3カ月以上かかりました。 経営学者の超有名な著者がマネージメントに関する所謂大家で ポーター等の古典派(経済学ディシプリン)であり、戦略策定コンテンツ派と大局をなす人だそうです。 難解で読むのが大変でしたが、書いてあることは非常に 有...
長い・難解・長い。。。 読み終わるのに、多分3カ月以上かかりました。 経営学者の超有名な著者がマネージメントに関する所謂大家で ポーター等の古典派(経済学ディシプリン)であり、戦略策定コンテンツ派と大局をなす人だそうです。 難解で読むのが大変でしたが、書いてあることは非常に 有用でためになることが多いと思います。 将来的には、著者が書いてあるマネージメント教育を受けてみたいと 思っています。そういう機会があれば。 会社の人事担当の偉い人にも読んでほしいと思いました。 また、経営学ってそもそも学問なのかというのは感じました。
Posted by
マネジメント教育の方法論だったので難解。でもマネジメント教育プログラムのデザイン意図を知ることは教育を受ける者にとっても有効と思えることもある。
Posted by
恐らく、自分はこの本を読むべき対象読者層ではなかったのだろうな、と思う。今般の教育(勿論表題にあるMBAを含む)への嘆きと、べき論について滔々と述べられていた。 一先ず、この本を読んでMBAに行きたい気持ちが強くなる人は多くはなさそう。教育制度の見直しに強い関心がある人には参考...
恐らく、自分はこの本を読むべき対象読者層ではなかったのだろうな、と思う。今般の教育(勿論表題にあるMBAを含む)への嘆きと、べき論について滔々と述べられていた。 一先ず、この本を読んでMBAに行きたい気持ちが強くなる人は多くはなさそう。教育制度の見直しに強い関心がある人には参考になるかも。
Posted by
経営には、サイエンス(分析、MBAで学ぶ)だけでなく、アート(直観、ビジョン)、クラフト(経験、実務)も必要で、それらのバランスが取れていることが望ましいですよ。 しかし、MBAではサイエンスしか学べないので、それだけでマネジメントできると思うのは恐ろしいことですよ。 それでは、...
経営には、サイエンス(分析、MBAで学ぶ)だけでなく、アート(直観、ビジョン)、クラフト(経験、実務)も必要で、それらのバランスが取れていることが望ましいですよ。 しかし、MBAではサイエンスしか学べないので、それだけでマネジメントできると思うのは恐ろしいことですよ。 それでは、どのようなマネジメントスクールがいいでしょうか、こういうものがいいですよ、という内容。 実務から離れたところで分析手法学んでも、それをうまく活かすことはできないだろうし、しかし、理論的なものを知っていると知らないとで、実務でのパフォーマンスは大きく違うだろうし。 学ぶことに意味がない、とは思わないけど、「それから生まれることのない博学は、知識のコレクション」と言う通り、知識は活かしてこそ意味があるわけで。 関与型マネジメントが非常に興味深かった。単に「偉くなりたい」ために学ぶのはいかがなことかと思うが、こういう形でのマネジメントを行うために学びに行くのは素晴らしいことだと思う。
Posted by
先に結論を言っておくとすごくいい本です。しかし、限りなく諸刃の剣的な取り扱い注意の本。 基本的な論調は、現在のMBAは極めて分析偏重であり、その上個々の業務機能に分化しすぎでありその統合がなされておらず、結果非常に現実離れしたカリキュラムとなっているというもの。百歩譲ってもマネ...
先に結論を言っておくとすごくいい本です。しかし、限りなく諸刃の剣的な取り扱い注意の本。 基本的な論調は、現在のMBAは極めて分析偏重であり、その上個々の業務機能に分化しすぎでありその統合がなされておらず、結果非常に現実離れしたカリキュラムとなっているというもの。百歩譲ってもマネージャーを育てるためのカリキュラムにはなっていない。確かにそのとおり。ケーススタディは本物の実践には程遠いし、経営をするということはさまざまな業務機能をバランスよく統合して行うことであるわけだし。 この統合という言葉、戦略サファリでも出てきたけど、非常に重要なコンセプトだと思うわけです。そのひとつの結実としてIMPMという新たなパラダイムが出てきているわけですな。これはまさにさまざまなマインドセットの統合。そして僕もかねがね主張しているインプットとアウトプットの輪廻。このIMPMの手法の中には、人に物を教えるため、いろいろなことを自ら学んでいくための大事なエッセンスが詰まっていると思うのです。これ自体をやれというつもりはないけど。ああ、でもこれ参加したいな。最初のほうはうちの御大もかなり深く携わっていたみたいだし。 さて、その上でこの本の取り扱い注意たる部分について書いておく。 気をつけるべきなのは日本企業に対する著者の評価の甘さ。甘さというより、若干補正がかかっているというべきか。MBA的な分析偏重の教育手法に対し極めて批判的な態度をとっているために(さらに言うとこういったMBAの姿勢はポーター的な戦略の流派に通ずるものがあるので余計に)その真逆にある日本企業に対する評価が甘くなっている。実際にはアメリカ以上に日本企業は若手マネージャーを千尋の谷に突き落としているわけだし、(ミンツバーグの想像以上に)極端にクラフト重視である。そこに分析的思考が加わりにくいために得てして無秩序型のマネージャーが生まれやすいというのが残念ながら日本のマネージャーの現状である。 余談だけどミンツバ-グが非常に評価していて「戦略サファリ」でも取り上げたホンダのアメリカ進出の事例はすでに30年前の話であり、あの時の責任者なり管理者なりは戦後の混乱を潜り抜け生き抜いてきた人たちであり、そういう人たちと(言い方悪いが)今の団塊のおっさん共ではポテンシャルが違いすぎる。というわけで日本に対するミンツバーグの評価自体はちょっとずれていると思う。 そういうことをわかった上で、しっかりこの本が示す理想のマネージャーのあり方・マネージャー教育のあり方を読み取れたとき、この本は必ず役に立つ。間違いない。教育論の本だが、この本の応用できる範囲はかなり幅広い。
Posted by