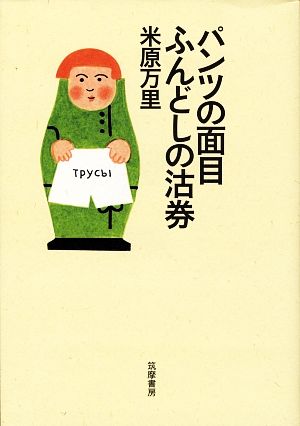パンツの面目ふんどしの沽券 の商品レビュー
【動機】タイトルと著者の組み合わせに惹かれたため ふんどしについて知りたかったので手に取った。少し思っていた本と違ったため後半は飛ばし読みしてしまったが、歴史や社会問題に関する著作を引用したり、他言語の単語をくらべたり、広い範囲を扱っているところがおもしろかった。
Posted by
2001年〜2003年にちくまで連載した、パンツ、褌、下着に関するエッセイに加筆修正し単行本化した一冊。 巻末に収録させている参考文献は複数言語で、なんと8ページにも及び、最早論文と言えるのではないかと思えるほどの量である。実際、連載直後から方々から情報提供があり、著者が想像し...
2001年〜2003年にちくまで連載した、パンツ、褌、下着に関するエッセイに加筆修正し単行本化した一冊。 巻末に収録させている参考文献は複数言語で、なんと8ページにも及び、最早論文と言えるのではないかと思えるほどの量である。実際、連載直後から方々から情報提供があり、著者が想像していたよりも遥かに奥深く途方もない広大な世界だと感じたそう。 しかし、米原万里らしく、幼少期の経験を交えた軽快なエッセイも忘れていない。 イエスキリストの下着は腰巻かパンツか、ワイシャツの丈が長く黄ばんでいるのは何故か、女性用生理用品の歴史などなど、、
Posted by
パンツと褌についての、結構探求的なエッセイ。というか吃驚仰天、彷彿絶倒の下のものの楽しい本。 著者は小4から中2までチェコにいたそうで、いきなりチェコの小学校の家庭科がパンツの縫い方から始まるなんて書いてあって驚く。まだソビエトがあったころで、どうも共産圏ではパンツを生産していな...
パンツと褌についての、結構探求的なエッセイ。というか吃驚仰天、彷彿絶倒の下のものの楽しい本。 著者は小4から中2までチェコにいたそうで、いきなりチェコの小学校の家庭科がパンツの縫い方から始まるなんて書いてあって驚く。まだソビエトがあったころで、どうも共産圏ではパンツを生産していなかったそうなのだ。シベリヤの収容所に入れられた日本人が困ったのは、トイレに紙もないし水道もなかったということだった。ソビエト兵たちは、うんこをしても尻を拭かないし手も洗わないのだ。そしてパンツもはいていなくて、長いシャツの前後が黄色だった。収容所の日本人たちがその衣類の洗濯をさせられたそうな。 著者が日本のミッション系の幼稚園で、十字架のキリスト像を見て、履いているのはパンツなのか褌なのか腰巻なのかとあれこれ考えたり、天地創造の紙芝居で、アダムとエバの局所を覆っているイチジクの葉がどうして落ちないのかと疑問を口にすると、俄かに園児たちが、セメダインで止めているだの糊だのセロテープだのと盛り上がるのが最高だった。先生も紙芝居を取り落として苦しそうに俯いたとか。園児たちはこの後、家でどれがいいか試してみたって。 最後の方は結構まじめに騎馬民族のパンツ(ズボン)が先か腰巻や褌が先かを追求している。どうもエスキモー型のズボンが先駆だったようだ。
Posted by
古事記からオデュッセイア。日本、モンゴルから中東、欧州まで、縦横無尽に文献を横断しつつの下着考察集。エッセイ色は控えめにだが、いつもの米原節は健在。疑問すら覚えなかった下着なるもの、目から鱗は必至。出典も記してあるので、興味あれば知識も広がると思う。
Posted by
大和男子のふんどしは日本独自のものか?パンツをはかない人々とは?キリストの腰にあるのはパンツか腰巻か?等々、下半身にかかわる不思議な幾多の謎を探求した書である。
Posted by
1950年生まれ、米原万里 著「パンツの面目 ふんどしの沽券」、2005.7発行です。面目がないのか、沽券にかかわるのかはわかりませんでしたがw、パンツとふんどしについて、古今東西、よく調べられています。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
『パンツの面目ふんどしの沽券』という書名からして、なんじゃこれ、と興味を引かせる。 米原万里という作家のエッセイ集。没後10年になる。 「少女時代をチェコで過ごし、受け継いだ中欧知識人のDNA。ソ連という対立軸を失った米国の一元論の危うさを、知性的にも、感性的にも見抜いている人だった」と朝日新聞文芸面の「今こそ」シリーズで、彼女を評する。「父は日本共産党の衆議院議員だった米原昶(いたる)。9歳のとき、父の仕事の関係で、一家でプラハへ。14歳まで現地のソビエト大使館付属学校で学び、国際的感性と語学力を磨いた。日本に戻り、大学院卒業後はロシア語通訳に。的確かつときに大胆な移しかえで、エリツィンやゴルバチョフら要人から、余人をもって代えがたい信頼を得る。1992年、報道の速報性に貢献したとして、日本女性放送者懇談会賞を受賞。華やかな容姿と存在感は、黒衣だった通訳のイメージも変えた。」というのが、彼女の経歴。 本書は、「ちくま」に連載したもの。連載を始める際には、「グローバル・スタンダードに押しつぶされそうな、ナショナル・アイデンティティー、要するに日本こゆうの価値や拠り所をみなおしてやろう、ちょっと応援してやろうというような気楽な気持ちで引き受けたのだった。(中略)そして、人間の下半身を被う肌着に関する考察をするという試みは、進めば進むほど途轍もなく奥深く途方もない広大な世界であることを思い知らされるのだった」と、著者が「言い訳だらけのあとがき」に記す。 書き始めの「四十年来の謎」であるとか、「よい子の四つのお約束」など、パンツをめぐる文明論のようで、著者が育ったころの東欧圏の経済や文明に関して、読み進めて「へえぇ」といった話の連続だ。 「四十年来の謎」というのは、彼女が9歳から14歳まで通った在プラハのソビエト学校での家庭科履修の風景。「その裁縫の授業で、最初に教わったのが、スカートでもなく、下着のパンツの作り方だった」。日本の立体とは無縁の雑巾の作り方ではなく、「二次元の布で複雑に入り組んだ三次元体(しかも動くから四次元体)を包まなくてはならない。(中略)人体の複雑さを認識させ、立体に対する理解を深める。きっと、そういう崇高な教育的目的があるのね、と宿題のパンツ作りにつき合わされて辟易していた母は、おそらく費やした時間と労力に何とか意味をもたせたかったのだろう、そう解釈した。」ところが2か月後の6月、母の解釈が必ずしも当たっていないいのではないか、と思わせることを目の当たりにした。夏休みの林間学校で、2年先輩のダーシャというソ連人の女の子が、雨続きで洗ったパンツがなかなか乾かず、スペアがたりなくなったときに、スーツケースの中から布きれを取りだして、方が見も使わずに素早く裁断すると、あれよあれよという間に目の前でぱんつを縫いあげたのである。母が父の越中フンドシを製作するときよりも素早い気がした。手慣れた手つきに見とれていた」という謎。 日本の抑留されていた人たちの手記などから、収容所を通じて、ソ連兵たちがルパシカの下には下着、つまりパンツは着けていなかったらしい、という「ルパシカの黄ばんだ下端」という章の話……。計画経済が進んでいたソ連で、パンツの製造というのは、後回しにされていたらしい。そして、ソ連に入って来る輸入品のなかでは、中国からの羽毛入りの下着が貴重品であったらしい……。 そのうち話は、イエス・キリストの磔の像で、局部を被うものが、パンツであるのか、単なる布であったのか、の図像学的な考察にまで、話は広がり、キリストさんの像を作り上げる作家たちの下着、さらには広がって文明論の世界の違いをも感じさせる。 そして「羞恥心の迷宮」「羞恥心の誕生」などの章では、文化によって「羞恥心の基準」が異なること。チェコから日本に戻って筆者が、日本人が感じ、演ずる羞恥の仕草に違和感を抱く実相や、外国人が日本の浴場でする仕草などに話が及ぶ。 同じものを見ながら、視点を変えると、モノの見方がいかに変わるか。そんな全編ではある。
Posted by
旧ソ連では裁縫の授業で最初に習うのはエプロンやスカートでなく下着のパンツを作ること!下着に関する比較文化論。ラテン圏で目にしたビデ。その意味やウンコの後尻を拭かない国があることも。これを読んでからワイシャツを見る目が変わったという人多数出現! ブログに衝撃的な感想文が…! 「ルパ...
旧ソ連では裁縫の授業で最初に習うのはエプロンやスカートでなく下着のパンツを作ること!下着に関する比較文化論。ラテン圏で目にしたビデ。その意味やウンコの後尻を拭かない国があることも。これを読んでからワイシャツを見る目が変わったという人多数出現! ブログに衝撃的な感想文が…! 「ルパシカの黄ばんだ下端」 http://zazamusi.blog103.fc2.com/blog-entry-705.html
Posted by
日露通訳者として有名な米原万里さんの晩年期のエッセイ。 ソビエト学校に通っていた頃、家庭科の授業でパンツを縫う課題があったのはなぜなのかという素朴な疑問は、調べていくうちに次々と新たな疑問をよび、結果アンネフランクの日記や秘密警察の制服、はたまたゲルマン民族の大移動、さらには日...
日露通訳者として有名な米原万里さんの晩年期のエッセイ。 ソビエト学校に通っていた頃、家庭科の授業でパンツを縫う課題があったのはなぜなのかという素朴な疑問は、調べていくうちに次々と新たな疑問をよび、結果アンネフランクの日記や秘密警察の制服、はたまたゲルマン民族の大移動、さらには日本書紀や創世記にまで話は及び、エッセイは壮大なスペクタクルの様相をおびてきます。 疑問解消のために大量の文献を読み漁る米原さんの根性と、ややもすると教科書的になってしまいそうな内容を面白おかしく書き上げる筆さばきには、ただただ脱帽です。 パンツとふんしどしの歴史を知ったところで今後の実生活には何の役にも立たないなと思うけれど、役に立つことばかりに時間を割く人生なんてつまらなすぎると思うので、そういう意味でも米原さんはとってもかっこいい。 米原さんをさして誰もが言われることですが、本当に早世が惜しまれます。
Posted by
図書館で米原万理の本と言うだけで手にしたのだけど、ソビエトに住んでいた頃の下着の話からその歴史まで面白く書いてある。 この本を書いている時にガンに侵され1年後に亡くなられたがとても残念だ。
Posted by
- 1
- 2