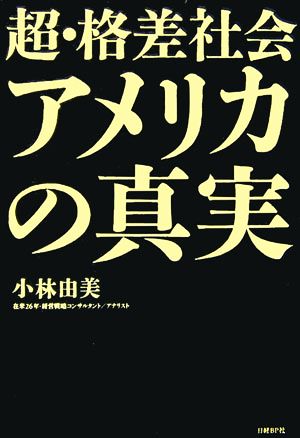超・格差社会アメリカの真実 の商品レビュー
データも豊富で、論理的で非常によくまとまった本。アメリカで格差社会が構成された歴史的な流れを分かりやすくまとめてくれている。個人的な経験から独断的に書くのではなく、データを参照しつつ、歴史に流れを説明してくれている。 そんな訳で本書に対して非常に高く評価しているのだが、1点、筆者...
データも豊富で、論理的で非常によくまとまった本。アメリカで格差社会が構成された歴史的な流れを分かりやすくまとめてくれている。個人的な経験から独断的に書くのではなく、データを参照しつつ、歴史に流れを説明してくれている。 そんな訳で本書に対して非常に高く評価しているのだが、1点、筆者が序文に述べている「アメリカで26年暮らして見えてきたことについて、自らの経験と知見を元に記した」という表明との乖離が気になった。
Posted by
一生懸命数字を出して裏付けようとするのだが、解釈が雑で、何事も単純化して勢いだけのパーティートークの延長
Posted by
アメリカに26年暮らした著者が、アメリカの格差社会、階層別社会について、データなどを交えて解説した本。
Posted by
冒頭で著者は、現在のアメリカはかつて多数をしめた中流ミドルクラスは存在せず、富裕層、プロフェッショナル層、落ちこぼれ層、貧困層の4つに収斂しているという。ミドルクラスの存在が揺らいでいるのは、否定できないものの、のっけから暴論という印象を受けた。しかし、その後に展開される様々な視...
冒頭で著者は、現在のアメリカはかつて多数をしめた中流ミドルクラスは存在せず、富裕層、プロフェッショナル層、落ちこぼれ層、貧困層の4つに収斂しているという。ミドルクラスの存在が揺らいでいるのは、否定できないものの、のっけから暴論という印象を受けた。しかし、その後に展開される様々な視点からのアメリカ社会の分析には一考に値する議論であふれている。 格差という言葉を耳にすることが多い昨今であるが、それは日本という国が資本主義・市場経済の先輩であるアメリカの後を追いかけている結果なのかという疑問が本書に関心を持ったきっかけである。 そもそも、アメリカという社会は格差ということに対するとらえ方が異なるのであろう。日本では、格差という言葉の語感には、不平等で理不尽というような否定的な要素が含まれているように思える。一方、アメリカではそのような日本語の格差に相当する言葉ななく、むしろ社会階層という言葉でそれが語られている。 本書では、そのとらえられ方について最終章で語られている。日本においての格差は、「職業選択と労働報酬」の問題であるのに対して、アメリカのそれは「資産」の問題であると。日本では、就労機会を阻む社会的構造が問題であり、不合理な既得権益を排除することが直近の課題であると。そしてより価値を生み出すことの出来るスキルを獲得するための教育、そしてさらに就労機会へと課題が移っていく。本書では、著者は教育の問題を初等教育として提起していたものの、どちらかといえば日本は国際的に初等教育は充実しているというべきであり、むしろ問題は就労問題へと直結する大学をはじめとする高等教育の問題であろう。遊んでいても卒業できると揶揄される日本の大学教育が、価値創造の手段となる知識やスキルの習得に貢献せず、人材の教育はもっぱら採用した企業が行うことを何十年も同じ状態で放置してきたことが、現在の競争力の低下の一因であるのではないだろうか。終身雇用と年功序列を柱とした日本の雇用形態は、著者の言葉をかりるならば、それは日本社会の「思い出」であり、それを基準として現状を嘆く格差論はノスタルジーであって建設的とはいえない。 一方、米国ではストックとしての資産が偏在していることでの、社会階層の固定化が問題であり、粗末な公共初等教育しか提供されないアメリカでは、日本よりも問題の解決はより困難であろう。 格差というのは、その是非はともかくとしても、人間の社会的活動の結果として必ず生じる必然であり、共産主義を選択しなければ、あがなうことの出来ないものであるといえる。アメリカでは、そいういういわば割り切りともいえる感覚で、それをあたりまえのものとして容認しているようにも思える。 では、日本以上に格差社会であるアメリカでなぜそれが容認されているのかというところが本書の読みどころの一つでもある。建国の成り行きから、奴隷制度、移民と西部開拓、南北戦争など時代時代の政治的、社会的、経済的背景を織り交ぜながら、社会階層がどのように変遷していったのかが具体的なデータを交えながら提示されている。
Posted by
歴史、政治、教育に触れてアメリカ社会の実像をわかりやすく解説。それでもなぜ居心地が良いのかも。リーマンショック前の出版。検索したら2017年3月に著者の新刊が出るらしいので楽しみ。おわりに、の英語と日本語の言語体系による表現のしやすい部分、しにくい部分も興味深かった。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2006年刊行。元長銀エコノミストでウォール街証券アナリストたる著者が、アメリカの実情・アメリカンドリームの歴史的経緯・教育制度等について叙述したもの。アメリカ的な資本主義礼賛は、公共的には狭い範囲の向上しかもたらさないことを指摘し、他方、自由で住みやすい面はあるが、その自由は実は、自己責任を建前としつつ貧困層にあえぐ多数の人々から搾取されたものと規定しているようだ(共和党支持層に多い)。そして、これが顕著なのは教育。なお、1990年代のアメリカのジョブ・ロス好景気は2000年代前半の日本と同じか?
Posted by
アメリカ建国において、彼らはヨーロッパの貴族の、特権を許さないという思いがあったはずである。たしかに、才能豊かな人には、門は開かれているが、競争社会で落ちこぼれた人達との、所得格差が開くばかりである。とはいえ、キリスト教国のアメリカは、ボランティアの奉仕活動が活発なため、教会がセ...
アメリカ建国において、彼らはヨーロッパの貴族の、特権を許さないという思いがあったはずである。たしかに、才能豊かな人には、門は開かれているが、競争社会で落ちこぼれた人達との、所得格差が開くばかりである。とはいえ、キリスト教国のアメリカは、ボランティアの奉仕活動が活発なため、教会がセフティーネットの役割を担って、底辺に暮らす市民をささえる。近年同様に、アメリカ型の競争社会になりつつある日本の将来は暗い。
Posted by
これも、書評ではなく、メモ。 2006年出版の本。著者は在米26年・経営戦略コンサルタント/アナリスト、という肩書き。75年に東京大学を卒業後、長信銀に入社ののち、渡米。スタンフォードでMBAを取得し、82年からは証券アナリストやコンサルとしてアメリカで職を得ているという。 ...
これも、書評ではなく、メモ。 2006年出版の本。著者は在米26年・経営戦略コンサルタント/アナリスト、という肩書き。75年に東京大学を卒業後、長信銀に入社ののち、渡米。スタンフォードでMBAを取得し、82年からは証券アナリストやコンサルとしてアメリカで職を得ているという。 『ルポ 貧困大国アメリカ』と比べると、インタビューの要素はなく、そのかわり著者の26年間の実感が挿入されている。グラフや表組など図版要素が豊富に使ってあり、分析的。また、歴史的な観点からアメリカ社会のなりたちを考察するという要素もある。 また、格差社会を憂えるという論調ではないことにも特徴がある。歴史的に見ても、アメリカは建国当初から金権体質だったし、階級社会だったし、格差社会だったし、これからもそうなのだと指摘する。戦後に日本が憧れた「豊かな中産階級社会」のアメリカは歴史的にみれば例外的な時期であったという。 アメリカは99%の犠牲の上に、トップ1%に恩恵を与える国である。大統領の目が特権階級を向いている。なぜなら、選挙で勝つための最大の武器は選挙資金だからだ。アメリカの富の多くは、政府と一部企業の所有者やトップマネジメント(経営者)間で、巧みに誘導されている。 にもかかわらず、機会平等の幻想を国民は捨てない。アメリカ社会はすべての人に対して経済的に成功することを期待している。「メイキング・マネー」だけが共通の価値観である。アメリカ型の競争社会は、階層社会の徹底化と、相互の(地域的・社会的な)隔離によって維持されている。格差は社会の与件となっていて、解消される見込みもない。、
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
【格差拡大】 1980〜 レーガノミックス:上限付き社会保障税(年金、老人医療)とガソリン税を増やす→貧乏人への税負担増+富裕層にとっては大幅減税 クリントン政権:株価、不動産価格の上昇→富裕層は一層豊かに 情報革命→技術革新によるジョブロス、単純労働の増加 ブッシュ政権:政治家と富裕層の癒着→階層の固定化が進む 【教育を通した格差の固定化】 公立学校→娯楽性高い 私立学校→学費高い(月2〜3万ドル) 【まとめ】 低コストで質の高い基礎教育を国家が維持することが重要
Posted by
東大経済卒・スタンフォード大学でMBA取得の後、経営コンサルタントとして在米26年の著者が記した本。 戦後の中流階級がなぜ貧困層へと転落してしまったのか、富の60%が5%の人々に集中する格差社会に何故陥ってしまったのかを説明する。 戦後の各大統領の政策を具体的に説明し、富の偏在...
東大経済卒・スタンフォード大学でMBA取得の後、経営コンサルタントとして在米26年の著者が記した本。 戦後の中流階級がなぜ貧困層へと転落してしまったのか、富の60%が5%の人々に集中する格差社会に何故陥ってしまったのかを説明する。 戦後の各大統領の政策を具体的に説明し、富の偏在の経緯を暴くだけでなく、ヨーロッパから開拓者がアメリカに現れた時からの富の移行の流れを歴史を通じて説明してくれる。 アメリカ史の勉強にもなる さらに教育制度と関連づけてアメリカ社会を論理的に記し、それでも何故アメリカは魅力的なのかを記している。 making money こそがアメリカの価値であり、かつそこから生まれる活気こそがアメリカの魅力であるとしつつ、自由と平等は同時に進行しないという筆者の意見を結びにおいている。
Posted by