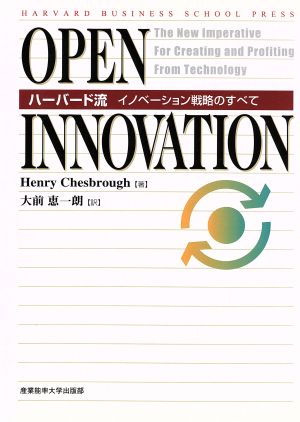OPEN INNOVATION の商品レビュー
どこかで紹介されていたのを見て、2017年11月24日に登録した本。 7年も放置したらダメですよね…。 出版されたのが20年ほど前なので、今でも有効なのかどうかはわかりませんが、自分としては納得できる記述の多い本でした。 OPEN INNOVATIONの対義語は、CLOSED ...
どこかで紹介されていたのを見て、2017年11月24日に登録した本。 7年も放置したらダメですよね…。 出版されたのが20年ほど前なので、今でも有効なのかどうかはわかりませんが、自分としては納得できる記述の多い本でした。 OPEN INNOVATIONの対義語は、CLOSED INNOVATION。 20世紀においては、新技術は、大企業のもつ研究所内で生まれ、その企業で活用されていましたが(CLOSED INNOVATION)、21世紀になる頃には、他企業で生まれた技術を自社で活かす、あるいは、自社で生まれた新技術が他企業で活かされるようになりました(OPEN INNOVATION)。 その流れに逆らうことなく、むしろその流れを利用して、イノベーションを進めていくべき、というのが本書の主張だと思います。 そして、その主張を補完するための事例や反例が、本書にはいろいろと記載されています。 ただ、自分が所属している企業においては、OPEN INNOVATIONを活用する、というよりは、CLOSED INNOVATIONへの流れが強まっているように思います。 本書の出版から20年が経過し、再びCLOSED INNOVATIONが重要になったからなのか、時代に逆らっているからなのか、自分には判断がつきませんが。
Posted by
内容的には、序章のみで事足りる。この部分は、満点評価。残りのケースの部分は現在となっては古ぼけたものも多いので、読み流す程度でよい。翻訳本としては下位のレベル。本文の訳はそれほど読みにくいものではないが、人名や企業名がアルファベット表記のままで、日本語と混在すると引っかかる。カタ...
内容的には、序章のみで事足りる。この部分は、満点評価。残りのケースの部分は現在となっては古ぼけたものも多いので、読み流す程度でよい。翻訳本としては下位のレベル。本文の訳はそれほど読みにくいものではないが、人名や企業名がアルファベット表記のままで、日本語と混在すると引っかかる。カタカナ表記に不安がある場合は、かっこ書きでローマ字を補っておけばよい。訳者の手抜きである。英語自体平易なので、勉強を兼ねて、原書を紐解いたほうがよい。
Posted by
◾️概要 オープンイノベーションとは何か知るため、読みました。最も印象的だったのは「研究部門の役割は知識創造のみならず、知識結合も担当する」です。オープンイノベーションは、企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造することです。新価値を0→1で作るだけがイノベーション...
◾️概要 オープンイノベーションとは何か知るため、読みました。最も印象的だったのは「研究部門の役割は知識創造のみならず、知識結合も担当する」です。オープンイノベーションは、企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ、価値を創造することです。新価値を0→1で作るだけがイノベーションではない。 ◾️所感 VUCAの時代、一企業が自前の研究開発で将来への種まきをするのは限界があります。研究部門の役割を再定義する必要を感じました。「社内の研究員には、自社のビジネスモデルや将来のロードマップについてよく理解してもらう必要がある。これによりテクノロジーをマーケットに出す方法が社内外で見つかる場合があり、研究員の欲求を結果的に満足させることができる」というのは示唆に富むフレーズでした。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
現代におけるイノベーションのあり方は、Closedではなく必然的にOpenでなければならないということを、様々な企業(IBM、Xerox、Intel、等)の事例を介して説明されていると思われます。 私の理解としては、端的に時代の変化から必然的にイノベーションの在り方が変わってきており、みんなそれに気づいていますか?という点を論理的根拠に基づいて説明してくれておりますが、少々アカデミックな記載が多いと感じました笑。私の読書能力の問題かもしれませんが笑。 イノベーションの形は変われど、やはり重要なことはビジネスモデルを含めた「事業戦略」ではないかと思います。事業環境が大きく変わっている中、事業としての勝ち筋を見出すためには、必然的に今までの企業内の知見だけを活用する座組みでは、スピード感と多様な技術に淘汰されてしまう。結果として、オープンイノベーションが必要と私は理解しました。自社のテクノロジー自体に価値はなく、やはりビジネスモデルがあって初めてテクノロジーに価値が生まれるということが書かれていますが、これは納得の論理だと感じました。特許戦略、社内ベンチャーの活用、ベンチャーキャピタルからの投資、他企業との連携、etc…、これら全て戦略を実現する手段ですね。今の自社にとっての戦略をしっかりと捉えて、自身にとってのオープンイノベーションを実現する方法論として何が最適なのか考えていきたいと思った次第。
Posted by
社内で起こすイノベーションをクローズド、社外発のイノベーションをオープンと呼ぶ。オープンイノベーションを企業の研究開発に有効利用するべきであるというのがこの本の趣旨のようだが、あたりまえすぎていやになった。このような本が2千円以上することが、オープンイノベーションのリスクであるこ...
社内で起こすイノベーションをクローズド、社外発のイノベーションをオープンと呼ぶ。オープンイノベーションを企業の研究開発に有効利用するべきであるというのがこの本の趣旨のようだが、あたりまえすぎていやになった。このような本が2千円以上することが、オープンイノベーションのリスクであることはわかった。
Posted by
すでに10年以上前に刊行された書物ながら、企業の研究開発が如何にあるべきか、という観点では古さを感じない。働き方改革や副業の許容などで、人材流動性の問題は徐々に解決に向かっているように感じる。 一方で、オープンイノベーションでどう儲けるか、という点では若干の物足りなさを感じる。F...
すでに10年以上前に刊行された書物ながら、企業の研究開発が如何にあるべきか、という観点では古さを感じない。働き方改革や副業の許容などで、人材流動性の問題は徐々に解決に向かっているように感じる。 一方で、オープンイノベーションでどう儲けるか、という点では若干の物足りなさを感じる。Free、ロングテールなどのビジネスモデルが一般化した今、企業の研究開発が果たすべき役割は何だろうか?
Posted by
研究開発~生産販売までの「クローズド・イノベーション」に対して、オープン・イノベーションは他社や大学などの研究成果を取り入れていく。このオープン・イノベーションに関してビジネスモデル、特許戦略、説明した本。 良かった言葉:テクノロジーそれ自身に価値はなく、ビジネスモデルによって...
研究開発~生産販売までの「クローズド・イノベーション」に対して、オープン・イノベーションは他社や大学などの研究成果を取り入れていく。このオープン・イノベーションに関してビジネスモデル、特許戦略、説明した本。 良かった言葉:テクノロジーそれ自身に価値はなく、ビジネスモデルによって商品化されて始めて価値が出るのと同様に、特許それ自体には価値はなく、ビジネスモデルに依存する まさに自分が日頃感じてることだったので、読んでて楽しかった。 でも、「ハーバード流イノベーション戦略のすべて」というサブタイトルは大げさ。ちょっと内容薄いと思うし、事例もそこまで多くない。期待が高かっただけに、期待以下で星3つ。
Posted by
ICT技術と知識の普及が創り上げた現代社会の多くの要因について理解できる本だと思う。この本が出版されたのが2004年。自分が産学連携の世界に足を踏み入れたのも2004年。もっと早くこの本を読んでいれば、しなくてもいい経験を減らすことができたかもしれない。でもその経験があるからこそ...
ICT技術と知識の普及が創り上げた現代社会の多くの要因について理解できる本だと思う。この本が出版されたのが2004年。自分が産学連携の世界に足を踏み入れたのも2004年。もっと早くこの本を読んでいれば、しなくてもいい経験を減らすことができたかもしれない。でもその経験があるからこそ、この本の価値がわかったのかもな。
Posted by
Henry ChesbroughのOPEN INNOVATIONに関する3作のうちの1作目。 もともとオープン・ガバメントに興味があり、そこからオープン・イノベーションに興味が派生し、研究室の関係も考え、夏にノリで3冊まとめ買い。 やっと1冊目を読了。。 PARC、IBM、Int...
Henry ChesbroughのOPEN INNOVATIONに関する3作のうちの1作目。 もともとオープン・ガバメントに興味があり、そこからオープン・イノベーションに興味が派生し、研究室の関係も考え、夏にノリで3冊まとめ買い。 やっと1冊目を読了。。 PARC、IBM、Intel、Lucentの4つの事例についてそれぞれ1章ずつ割き、オープン・イノベーショの概念を用いて説明している。 キーセンテンス、感想をいくつか。 ・高等教育の普及・VCの誕生などによって知識の独占が難しくなった現代においては、企業の中央研究所に代表される、全て自前で研究開発する、というクローズド・イノベーションはもはや難しい。 ・アイディアやテクノロジー自体には固有の価値はなく、その価値は用いられるビジネスモデルに依存する。 ・4章「ビジネスモデル」における、ビジネスモデルの概念定義は役に立つ。(……自分が勉強不足で無知だっただけかもしれないけれど。。) 少なくとも、自分の中で、ビジネスモデルの概念がより確かなものになったと思える。 ・事例がほとんどハイテクIT企業(MillenniumPharmaceuticalsの事例が8章にあり)なので、他産業においてはオープン・イノベーションの事例はない?(P&Gの事例は有名だけど。。他には?) ・特許周りの話はちょい少ない。次巻に期待。 テクノロジーとビジネスモデルの関係は、2冊目、3冊目に引き継がれる話題だと思われるので、それらが楽しみ。……読むのはいつになるか。
Posted by
- 1