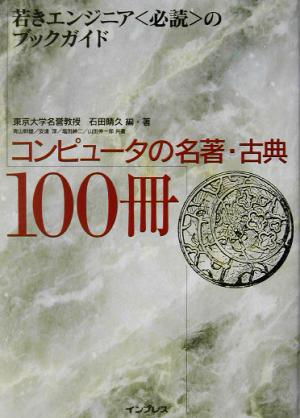コンピュータの名著・古典100冊 の商品レビュー
2回も改訂版が出ているのか、知らなかった。 この初版でも、冒頭に10年後でも通用する様にと書いているが、一部を除いて十分通用しそうな気がする。 もう絶版になってしまったものが多くて少し残念。
Posted by
☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆http://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BA64329837
Posted by
エンジニアのための、と銘打たれているが、歴史、社会、思想面での本の紹介もありなじみやすい。コンピューターに関する名著がこれほどまでに蓄積しているとは知らなかった。 LINUXの考案者トーバルスの本の題名「それが僕には楽しかったから」 が楽しかった。
Posted by
もう若くはないが、どんな本が挙げられているのか、興味があったので読んでみた。自分の本棚にある本は32冊だった。 それは置いておいて、日頃から疑問に思っていた「英語の教科書はなんであんなに分厚いのか」について、何カ所かで触れられていたので、メモしておく。 (1)英語の本は世界中に...
もう若くはないが、どんな本が挙げられているのか、興味があったので読んでみた。自分の本棚にある本は32冊だった。 それは置いておいて、日頃から疑問に思っていた「英語の教科書はなんであんなに分厚いのか」について、何カ所かで触れられていたので、メモしておく。 (1)英語の本は世界中に売れるから、分厚い本も出せるが、日本の出版社は分厚いオリジナル本は出しにくい状況にある。 (2)アメリカは、タイプライタ文化で、授業で話したことがそのまま教科書になっている感じ。日本では、原稿を書くだけでも大変なので、どうせなら図や写真を入れてわかりやすく工夫しようとする。 (3)アメリカの教科書の特徴は、分厚く、書き方が冗長、演習問題や参考書リストが多い、(もちろん売れる本は)何回も改訂している。日本の教科書は、概念や定理をトップダウンで説明するケースが多く、簡潔で要領がよいものが多いが、アメリカの教科書は、簡単な事例やたとえ話が多く、それを導入としてボトムアップで深い説明に入っていく。
Posted by
- 1