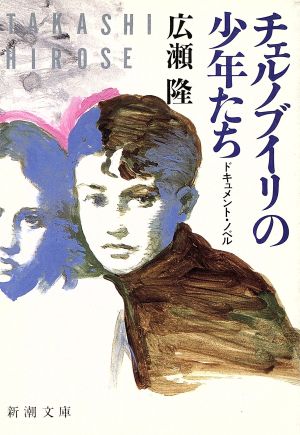チェルノブイリの少年たち の商品レビュー
(2014.03.19読了)(2011.11.03購入) -ドキュメント・ノベル- 【東日本大震災】 単行本は、1988年2月に太郎次郎社より刊行。 東日本大震災で、福島原発事故が起こるまでは、チェルノブイリは、遠いよそのできごとだったのですが、いまや身近な話になってしまいました...
(2014.03.19読了)(2011.11.03購入) -ドキュメント・ノベル- 【東日本大震災】 単行本は、1988年2月に太郎次郎社より刊行。 東日本大震災で、福島原発事故が起こるまでは、チェルノブイリは、遠いよそのできごとだったのですが、いまや身近な話になってしまいました。 本の題名から、チェルノブイリの原発事故によって放出された放射線を浴びた少年少女が、放射線を浴びたことによって徐々に身体的影響が現れ、健康がむしばまれて生活している様子を描いたものかと思っていました。 読んでみると、もっとすさまじいものでした。 ドキュメント・ノベルとなっていますので、多分こんなふうなことだったのだろうという推測に基づいて書かれた物語です。 チェルノブイリの原発事故に始まって、事故から一カ月までのことが書いてあります。 【目次】 運命の金曜日 大草原の惨劇 第二夜の訪れ 危険地帯からの脱出 孤独な少年 検問 病棟 捜索 キエフの空の下 イワンの脱走 チェルノブイリ現地の真相 イワン 主人公・15歳 原発の爆発を肉眼で見たので、二日後に失明 アンドレー・セーロフ 父親・発電所職員 消火作業で原発へ ターニャ 母親 脱毛 イネッサ 妹・11歳 昏睡状態 ●農村(84頁) いきなり原子炉が爆発し、たった今まで住んでいた所から立ち退けと言われても、羊と牛はどうすればよいのか。(中略) それをすべて放り出して退避しろ、と軍隊が叫んでいるのだ。銃口を突き付けながら。 ●出血(88頁) 楽に半数を超える人間が、体のどこかに異常な出血を起こしていた。ある男は耳に、ある女は歯ぐきに、ある子供は全身に、不気味な出血が見られた。なかでも内臓の出血が最も顕著で、これが彼らの衣服を汚していた。それを我慢し続け、誰もが他人に気づかれないように必死で隠していたのである。 ●医師団(91頁) いろいろと体に苦痛が出ているはずだが、それはまったく心配ない。医師団が解析したところ、一時的な症状であることが分かっている。手当ての方法さえ誤らなければよい。したがって、この検問所で指示を受けた者は、忠実に、医師の言葉を守って欲しい。 ●白血球の減少(122頁) 誰もが、白血球の著しい減少を示していた。造血組織に致命的な影響を受けた子供は、すでに全身が蒼白な状態となり、免疫作用も失って末期的な発熱症に突入していた。 ●事故見物(186頁) 多くの住民が原子炉の爆発現場を見ようと自動車を走らせ、死の雲がすっぽりと包む中に突っ込んでいった。信じられないことだが、放射能について何も教えられたことがなかった彼らは、まるで花火か火事でも見るように、燃えさかる原子炉を眺めていた。 ●死者一万五千人(189頁) 事故のあと移住したウクライナの原子力技術者が語ったところによれば、彼の友人(複数)が、キエフの二つの病院で働いていた。この友人たちは、「事故から五カ月の間に、少なくとも一万五千人のチェルノブイリの被害者がこれらの病院で死亡した」と訴えていたという。 ☆関連図書(既読) 「恐怖の2時間18分」柳田邦男著、文春文庫、1986.05.25 「食卓にあがった死の灰」高木仁三郎・渡辺美紀子著、講談社現代新書、1990.02.20 「チェルノブイリ報告」広河隆一著、岩波新書、1991.04.19 「ぼくとチェルノブイリのこどもたちの5年間」菅谷昭著、ポプラ社、2001.05. 「朽ちていった命」岩本裕著、新潮文庫、2006.10.01 「福島原発メルトダウン-FUKUSHIMA-」広瀬隆著、朝日新書、2011.05.30 「原発の闇を暴く」広瀬隆・明石昇二郎著、集英社新書、2011.07.20 (2014年4月29日・記) (「BOOK」データベースより)amazon 1986年4月25日深夜、巨大な爆発音がウクライナの闇に轟いた。チェルノブイリ原子力発電所で重大な事故が発生したのだ。何万人もの人々が住み慣れた街を強制避難させられていった。体じゅうを放射能に餌まれた彼らはどんな運命を辿るのか?今なお世界中で影響が残るあの原発事故の被害を、避難の途中バラバラにされていったある家族をモデルに描く迫真のドキュメント・ノベル。
Posted by
1986年4月25日深夜、巨大な爆発音がウクライナの闇に轟いた。チェルノブイリ原子力発電所で重大な事故が発生したのだ。何万人もの人々が住み慣れた街を強制避難させられていった。体じゅうを放射能に餌まれた彼らはどんな運命を辿るのか?今なお世界中で影響が残るあの原発事故の被害を、避難の...
1986年4月25日深夜、巨大な爆発音がウクライナの闇に轟いた。チェルノブイリ原子力発電所で重大な事故が発生したのだ。何万人もの人々が住み慣れた街を強制避難させられていった。体じゅうを放射能に餌まれた彼らはどんな運命を辿るのか?今なお世界中で影響が残るあの原発事故の被害を、避難の途中バラバラにされていったある家族をモデルに描く迫真のドキュメント・ノベル。
Posted by
1986年4月25日、あれからすでに四半世紀が過ぎました。今だからこそ、この本を読んで、事件の風化がないようにしていただければと切に願います。 僕がこの本を手にするきっかけになったのは先日、この本が漫画になったものを偶然、読む機会があって、原作となったこの本がないかと探していた...
1986年4月25日、あれからすでに四半世紀が過ぎました。今だからこそ、この本を読んで、事件の風化がないようにしていただければと切に願います。 僕がこの本を手にするきっかけになったのは先日、この本が漫画になったものを偶然、読む機会があって、原作となったこの本がないかと探していたらあったので、読んでみる事にしました。現在、この本は絶版のようですので、よろしければ、というか、興味を持った方は何とか手に入れて、もしくは図書館かどこかで探していただけるとありがたく思います。 この本に描かれているものは、フィクションという形をとっていますが、あのチェルノブイリ原発事故によって、引き裂かれた家族の運命を描いたものです。原発技師のアンドレー、妻のターニャ、長男のイワン。長女のイネッサ。彼ら彼女たちを中心として、チェルノブイリで災害に会った人たちの過酷な姿が描かれていて、今、原発事故の現場である福島で避難生活をおくっていたり、住み慣れたところや、わが子同然に育ててきた家畜や農作物を捨てて生活をしている方々のことを思わずにはいられませんでした。 その中で僕が一番心に残っているのは上司の命令で、アンドレーが二度と生きて帰ってこれないと知りつつ、家族を守るために『人柱』として、何の防護服すら着ないで、事故現場で復旧活動を行っているところでした。結局彼は死んで、イワンやアネッサも放射線を大量に浴びたために、死んでしまいます。 今、福島はどれくらいの情報が明らかになっているか僕には見当がつかないので、こういうものを参考にしてその後を類推するしかありませんが、過酷な運命が待っていることだけは容易に想像がつきます。その事実に僕はただただ暗澹とするばかりです。
Posted by
先週、『We』171号で話を聞いた古橋りえさん主宰のへのへのもへじ文庫へ行ったときに借りてきた一冊。裏表紙にある「ドキュメント・ノベル」というのが、ドキュメント?ノベル?と思ったけど、読み終えて、ドキュメント・ノベルというのが分かる。1986年の4月、チェルノブイリ原子力発電所の...
先週、『We』171号で話を聞いた古橋りえさん主宰のへのへのもへじ文庫へ行ったときに借りてきた一冊。裏表紙にある「ドキュメント・ノベル」というのが、ドキュメント?ノベル?と思ったけど、読み終えて、ドキュメント・ノベルというのが分かる。1986年の4月、チェルノブイリ原子力発電所の事故が起こったあとのことを、「誇り高い発電所の職員」で、「一点の曇りもない自信を抱いて、設計から運転作業のすみずみに至るまで監督してきた男」アンドレー・セーロフとその家族をモデルに描いた小説。視点の中心はアンドレーの息子・イワン。 読み始めると途中でやめられず、借りてきた日に読んでしまった。 深夜に爆発したチェルノブイリ発電所を前に、アンドレーの息子・イワンは恐怖心を爆発させる。「本当だ。嘘じゃない。爆発しちまったんだ。もう駄目だ。何もかも終りだ。みんな叫んでるぞ。俺は全部見てたんだ」(p.10) アンドレーの妻・ターニャは激しい怒気がこもった言葉を吐く。「これが、私たちの信じてきた世界一安全な発電所だったのね」(p.11) 朝になって(爆発からすでに何時間も経っている)、世界一の原子力基地をめざしてきたプリピアーチの町から、ようやく避難の車が数珠つなぎにうごきはじめる。イワンの妹・イネッサはその車のなかですでに身体に異変が出始めていた。 10キロほど先の農場で、アンドレーたち重要な13人とその部下たち百数十人は、爆発した原子炉の処理にあたる突撃残留組として選びだされた。ほどなく、その決死隊と家族とのあいだを上司が引き離してまわった。 アンドレーの妻・ターニャはこう叫ぶ。 「あの偉い連中は、こういう時には原子炉のなかに入らないんだわ。命令だけして、あとは自分の家族と夕食をとるのよ!」(p.34) その叫び声で、アンドレーは決死の覚悟を抱く。「自分がまだ"偉い人間"でなくてよかった、若い男たちを死地に赴かせて自分だけが生きているぐらいなら、いっそ死を選んだほうがよい、これでよいのだ」(p.34)と。 決死隊が、折り返し原発にむかって戻っていった直後、避難してきた生後8ヶ月の子が息をひきとった。避難していくうちに、羊たちが死んでいるのと行き会い、イワンの両眼は見えなくなった。その先で、ターニャと、子どもたちは離され、さらにイワンとイネッサも別々の病院へ収容される。 イネッサは、一緒に入院していた子どもたちと同じように、赤い斑点の浮きあがった腕になり、口から血を吐いて死んだ。いちどは同室の少年たちと脱走をこころみたイワンも、苦しくなり、体が自分のものではないように力が入らなくなり、死んだ。 子どもたちがすでに死んだことも知らず、二人をなんとか探し出そうとする母のターニャ。自分の忘れられない記憶を思う。 ▼夫はチェルノブイリで働いていた。ターニャ自身もそれを誇りにしていた。 何とおそろしい職業だったのだろう。自分は、なぜそれに気づかなかったのだろう。このような結末は分っていたはずなのだ。あるいはイワンとイネッサに今日の不幸をもたらしたのが自分たちだったかも知れないと思うと、ターニャは気も狂わんばかりに、自分を責めたてた。 しかし、ターニャが知っている以上に、この原子炉事故は重大な意味を持っていたのである。 犠牲者はイワンとイネッサだけではなかった。大地に根を下ろした"死の灰"が静かに襲いかかったのは、全世界の子供たちであった。(pp.175-176) チェルノブイリの事故が起きたとき、私は高校2年だった。死の灰がとか牛乳がとざわざわしていたことをぼんやりとおもいだす。
Posted by
チェルノブイリ原発事故のことをほとんど知らなかったので、読んでみました。 読んでいて本当に衝撃的でした。 今だからこそぜひ読んでもらいたいです。 チェルノブイリの事故は20年以上も前のものですが、集結したように見えて、地球に影響を与え続けていることにもぞっとしました。
Posted by
チェルノブイリ原子力発電所で、起こった大爆発の事故の被害を、避難の途中ばらばらにされていったある家族をモデルにしたドキュメント・ノベル。 チェルノブイリ、チェルノブイリって言われても、実際良く知りませんでした。 時は1986年4月25日深夜。 当時のソビエト連邦共和国。...
チェルノブイリ原子力発電所で、起こった大爆発の事故の被害を、避難の途中ばらばらにされていったある家族をモデルにしたドキュメント・ノベル。 チェルノブイリ、チェルノブイリって言われても、実際良く知りませんでした。 時は1986年4月25日深夜。 当時のソビエト連邦共和国。ウクライナ。 首都キエフから200キロも離れていない。 ウクライナといえば、旅で出会った奴が、ウクライナの人は美人だ!って言ってたのがすごく印象に残っていた。…自分アホ過ぎる。。。 原発で事故が起こるとどういうことが起こるのか、恐怖を増幅させるためではなく、事実を知るために読むべきだと思う。 信じられないのは、今日がこの悲惨な事故からたったの25年しか経っていないこと。
Posted by
チェルノブイリの原発事故 家族離散の悲劇 読んでいるうちに、これはノンフィクションだろうと思い始める。 最後にハッピーエンドを期待しつつも、結局はやりようのないむなしさだけが残る。救われない願いが、そこにはたくさんあったのだろうと思った。 原発を抱える国として、同じようなこ...
チェルノブイリの原発事故 家族離散の悲劇 読んでいるうちに、これはノンフィクションだろうと思い始める。 最後にハッピーエンドを期待しつつも、結局はやりようのないむなしさだけが残る。救われない願いが、そこにはたくさんあったのだろうと思った。 原発を抱える国として、同じようなことが起こりうると思うと怖いという感情よりも絶望のほうが先立つ。
Posted by
廃墟に漂う不気味な空気。 鈍色の雲が押し迫り、黒い灰がせきそうする地上。 何基も原発があるにもかかわらず、日本という安全な国に住んでいるという錯覚の元生活している私は、しばしば退廃した世界に魅了されることがある。 本書はありきたりな家族を中心にストーリーを進めることにより、この悲...
廃墟に漂う不気味な空気。 鈍色の雲が押し迫り、黒い灰がせきそうする地上。 何基も原発があるにもかかわらず、日本という安全な国に住んでいるという錯覚の元生活している私は、しばしば退廃した世界に魅了されることがある。 本書はありきたりな家族を中心にストーリーを進めることにより、この悲劇と平和ボケした私たちとの距離をぐっと縮めてくれている。しかし、物語としてきれいに成立することにより、どこか真実味を書いているようにも感じてしまう。結果、私はこの本を物語として楽しんでしまった。 残念なことに、本書の結びに当たる章で、大人は変わらないと作者は述べている。この本は、子供に読んでもらうことに意味があるのだろう。感情豊かな子供はもっと物語を自分の世界とリンクできる。 頭の固い想像力が貧困な大人が、原発の恐ろしさを理解するには、物語でないものが必要だ。目に見えるごく近い距離で起こる真実。 だが、それが見えてからでは遅すぎる。
Posted by
- 1