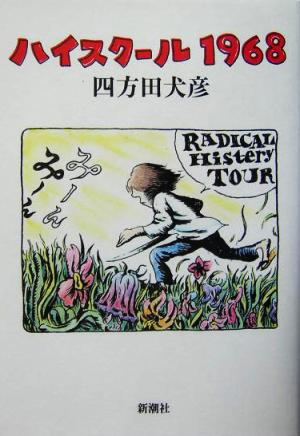ハイスクール1968 の商品レビュー
1968年 確かに激動の時代であったのだろう 私自身は まだ幼過ぎて その時に起きている社会的な事象を 全く理解できていなかった しかし 大人になって その世代の友だち(知り合い)が できたときに その「当時」のことが その人の人生設計の上に かなり影響していることは なんとな...
1968年 確かに激動の時代であったのだろう 私自身は まだ幼過ぎて その時に起きている社会的な事象を 全く理解できていなかった しかし 大人になって その世代の友だち(知り合い)が できたときに その「当時」のことが その人の人生設計の上に かなり影響していることは なんとなく肌身で感じることはできた 勢い、「書籍」「ドキュメンタリー・フィルム」で 追体験することになっていた そんなこともあり ものすごく興味深く 最後まで読ませてもらえた まさに 「歴史のドキュメント」として読ませてもらえました 蛇足ですが 「Magical Mystery Tour」 をもじった 「Radical Histery Tour」 には 座布団三枚です
Posted by
全然知らない人の小説を読むならともかく、全然知らない人の自伝?を読むというのもなかなかにエキサイティング。何故にこの本を読もうと思ったかは今となっては謎だけども、ともかくも読んでみるわけで。 1968年のエリートの話なのである。高校の名前とか、既に天上人レベルなんで、おうおう、い...
全然知らない人の小説を読むならともかく、全然知らない人の自伝?を読むというのもなかなかにエキサイティング。何故にこの本を読もうと思ったかは今となっては謎だけども、ともかくも読んでみるわけで。 1968年のエリートの話なのである。高校の名前とか、既に天上人レベルなんで、おうおう、いきなりすげーですよ。そんな人たちが文学やら芸術やら、時には学校にバリケードを築いて頑張ってみたりしながら、というかそんな事ばっかしてないか、ってレベルなのに怒涛のように東大に入っていくという。会社でも東大の人はやっぱ一味違うわって感じる事は多いんだけど、本物だからこそ東大に行くんだな、やっぱり。 しかしこの本を読んで、才能にも金銭的にもそれなりに恵まれていたんだぜ、っていう世の中の格差を目の当たりにし、で、どうしようかって言われると、うん、どうしようかね。とりあえず表紙の絵は好きよ。
Posted by
この人の書くものは何でも好きだ。 何か読みたいけど、あれもこれも目はいくものの、「これ」といった決め手がないような時、読んでいないこの人のものを買います。ハズレがないから。 本書は、著者の読書や趣味の遍歴をカタログ的に楽しめる。というより、いつも半分はそれを期待している。最も信...
この人の書くものは何でも好きだ。 何か読みたいけど、あれもこれも目はいくものの、「これ」といった決め手がないような時、読んでいないこの人のものを買います。ハズレがないから。 本書は、著者の読書や趣味の遍歴をカタログ的に楽しめる。というより、いつも半分はそれを期待している。最も信頼できる読み手・受け取り手のレビューの集成というか。 辺境とされる地に好んで赴く著者ですから、足で拾った情報というか、商業マーケティングを通じて流れてくる情報ではなかなかひっかからないような、ともかくも、世界を広げてくれます。 行き詰まった時、読みます
Posted by
育ちが違いますね。それはしょうがないし、本人の責任ではないし、私自身が努力不足だと言われればそれまでだし。でも、世の中、もっともっと格差が大きくて、しかも私はそれを一概に否定する気もない。こういう人たちも必要だと私は思うのです。
Posted by
先に『先生と私』で大学時代を振り返った四方田犬彦はその前に、書くことによって高校時代からの解放をめざす作品を書いていた。それが本書である。それは彼自身の青春への回顧であると同時に、若くして死んだ二人の友人への鎮魂の書でもあった。そのうちの一人に対し四方田はこういう「ぼくが書かなけ...
先に『先生と私』で大学時代を振り返った四方田犬彦はその前に、書くことによって高校時代からの解放をめざす作品を書いていた。それが本書である。それは彼自身の青春への回顧であると同時に、若くして死んだ二人の友人への鎮魂の書でもあった。そのうちの一人に対し四方田はこういう「ぼくが書かなければ、十九歳だった彼女の人生の輝きのことは、地上で誰も記憶している人がいなくなってしまうわけだろ」と。それにしても、ここで描かれている四方田の高校時代のなんと早熟なことか。かれが読んだ本、みた映画のリストをみているだけで目眩がしそうになるほどだ。かれが高校に入ったのはぼくが大学に入った1968年である。ほとんど同時代に生きながら、かれが読んだほとんどの本に興味がいかなかったのはなぜか考えさせられてしまう。しかも、そうした読書経験を四方田は高校時代にすでにすませてしまっているのである。驚くべきことである。東京ではこうしたことが高校生の世界でも当然のこととされていたのだろうか。
Posted by
- 1