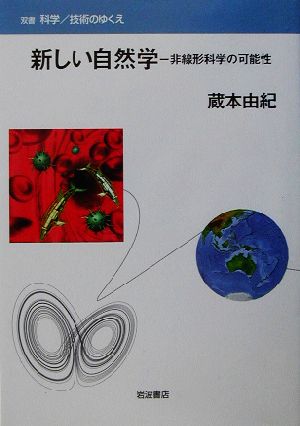新しい自然学 の商品レビュー
自然法則にも超ミクロからミクロ、マクロ、超マクロそれぞれのレベルで成り立つ法則群があるが、一般にミクロな法則ほど高い対称性をもつと考えられている。▼『新しい自然学─...
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
集英社新書「非線形科学」の前著にあたるが、小誌ながら、新しい科学知の世界の啓蒙書としては、簡潔にして高邁によく語りえており見事。 ’03年版。
Posted by
蔵本氏はストロガッツの「SYNC」でその研究の先進性が紹介されていて知った。その蔵本氏による自然科学の方法論に関するエッセー。 「これまでの自然科学が要素還元的なところに集中していて、全体を理解しようとしていない、極めて偏ったいびつなものになっている」といった主張。これ自体は...
蔵本氏はストロガッツの「SYNC」でその研究の先進性が紹介されていて知った。その蔵本氏による自然科学の方法論に関するエッセー。 「これまでの自然科学が要素還元的なところに集中していて、全体を理解しようとしていない、極めて偏ったいびつなものになっている」といった主張。これ自体は、あまり目新しい主張ではなく、複雑系をまとめ読みしている私にとっては、もはや「自明」(?)のところ。が、この本の新しいところは、そうした単純な要素還元主義批判に終わるのではなく、「周辺制御の原理」と「述語的統一」という2軸を考える事によって、問題を整理しようとするところである。つまり、これまでの要素還元的科学はものが何でできているかという「主語的統一」を目指しているのに対し、それらの主語がどのようにあるのかという「述語的統一」というのが必要である。そして、自然現象には、ミクロレベルと様々な階層的なマクロレベルがあって、その階層間では働く原理が異なっている。そしてマクロレベルでは述語的統一ということが大切である。という話。 ということで、いわば、単純に「全体は部分の和より大きい」といった神秘主義に傾きがちなアプローチではなく、主語と述語というアプローチを提言しているわけで、誠実な科学者だな、と思った。 また、科学は、物事を「予測」することも大切だが、それ以前にまずは物事をちゃんと「記述」するということができていなければならない。という指摘があって、文系的な人間として、「まずは記述が先決」論には多いに共感した。 個人的には、「SYNC」で、「線形は複雑な現実に接近するための近似であり、自然は線形ではできていない。非線形とは何かと聞かれても、動物園で象以外の動物は何かと聞かれるようなものだ」といったフレーズに刺激を受けて、「非線形科学」についての入門書を期待していたのだが、その点に関しては、やや消化不良ぎみ。というのは、著者の非線形の定義は、「大雑把に言えば、非線形現象とは何らかの形でフィードバックが働く現象であるといってよいであろう。フィードバック機構、つまりあるプロセスが進行すればそれによって生じる事態がそのプロセスの進行を促進したり阻害したりするような機構、それを内蔵しているシステムを非線形系とよんでよい」とのこと。これって、システムの定義(つまり、システムという言葉は使うときには、フィードバックがあることが暗黙の前提になっている)じゃ、ないんだろうかと思った。素人的には、非線形とは、そういうシステムのフィードバック効果が、線形ではなく、非線形的、例えば相転移みたいな非連続性や指数関数的、あるいはベキ法則的に働く世界、というイメージだったので、まだその辺がすっきりしない。 あと、散逸構造、カタストロフィー、カオス、フラクタルといった、複雑系に関連するキーワードについて、簡潔なレビューがあって、勉強になった。 ということで、大変、勉強になったのだが、全体としては方法論に関する試論という感じで、文系の人間としては、入門書的にもう少し詳しく事例等を解説していただけると良かったということと、ページ数にくらべて価格が高い気がするので、満足度評価は真ん中くらいで。
Posted by
第1章の「はじめに」で投げ掛けられる問い掛けには首肯させられる。14年後の小惑星接近が正確に予測出来る一方、風にあおられる風船の10秒後の位置を予言できない。 ベルーソフ・ジャボチンスキー反応系は、文章だけでは到底イメージ出来ないので、動画を見た方が良い。
Posted by
述語統一的な現象の記述ということであるが、これが広く用いられる言葉である「普遍性」とかuniversalityという言葉とどう異なる意味で使っているのか、気になってしかたなかった。 後半に入るにつれ思想的な記述が多くなり、読むのをやめてしまった。そういうのが好きな人には薦められる...
述語統一的な現象の記述ということであるが、これが広く用いられる言葉である「普遍性」とかuniversalityという言葉とどう異なる意味で使っているのか、気になってしかたなかった。 後半に入るにつれ思想的な記述が多くなり、読むのをやめてしまった。そういうのが好きな人には薦められる。個人的にはもう少し個別のケースに踏み込んで議論をしていると思ったのだけど…
Posted by
現代の科学を捉えるのに良い本です. 学部学生にお薦めです. なにか卒論のテーマを見つけられるかもしれません.
Posted by
カオスや複雑系の先にある領域。 数学と生物学のコラボ。判るところをつまみ読み。 イメージ読みになりそう。(笑)
Posted by
- 1