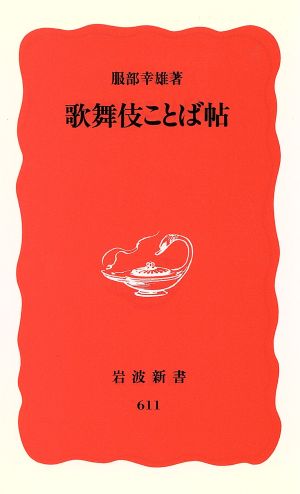歌舞伎ことば帖 の商品レビュー
歌舞伎が語源の様々な…
歌舞伎が語源の様々な言葉について紹介されています。
文庫OFF
『歌舞伎のキーワード』(1989年、岩波新書)の姉妹編で、42の項目について解説がなされています。 著者は「あとがき」で、「江戸時代以来歌舞伎とそれを取り巻く多くの人々が作り出し、育て、伝承してきた数々の「ことば」について、それぞれの成り立ち、正確な概念とその変遷、ことばの背景...
『歌舞伎のキーワード』(1989年、岩波新書)の姉妹編で、42の項目について解説がなされています。 著者は「あとがき」で、「江戸時代以来歌舞伎とそれを取り巻く多くの人々が作り出し、育て、伝承してきた数々の「ことば」について、それぞれの成り立ち、正確な概念とその変遷、ことばの背景になっている江戸文化の特質などをめぐって、自由に書き綴ったエッセイである」と説明しています。たとえば、舞台の仕掛けについて解説しているところでは、「回り舞台は舞台の照明を暗くせず、明るいままでゆっくりと回すのが原則である」と述べられ、「近年、舞台を薄暗くしたり暗転にすることがあるのは、近代人好みの合理主義の結果で、古風な歌舞伎の楽しさをそこなう」と論じられているところなどは、著者自身の歌舞伎に対する考えがストレートに語られており、エッセイとしての性格が強く出ています。 前著同様、日常生活のなかで用いながらも、その意味がどのような由来をもっているのかということを知らなかったことばについて学ぶことができました。
Posted by
- 1