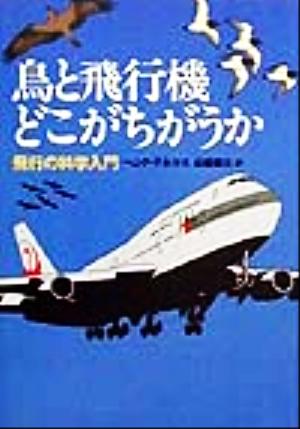鳥と飛行機どこがちがうか の商品レビュー
「この本は、ある航空宇宙工学の助教授による復讐として書かれたものである」と言う、とてもわくわくしてしまう書き出しの本。 飛ぶとはどう言う現象なのか、鳥類や昆虫などの飛翔のメカニズムから旅客機の飛行原理を説明する。 その中には鳥類でも昆虫類でもない翼竜の姿もあり、数値と...
「この本は、ある航空宇宙工学の助教授による復讐として書かれたものである」と言う、とてもわくわくしてしまう書き出しの本。 飛ぶとはどう言う現象なのか、鳥類や昆虫などの飛翔のメカニズムから旅客機の飛行原理を説明する。 その中には鳥類でも昆虫類でもない翼竜の姿もあり、数値としてのプテラノドンと言う視点に面白みを感じた。 翼が不釣り合いに大きく、体の大きさの割に対気速度が遅いプテラノドン。 巡航速度はビューフォート風力階級5より下だと言う。 強風だと巣に戻れなくなるかもしれない巡航速度で大丈夫かと思ったら、白亜紀は極地に氷冠が無く、赤道と極地の温度差が現在よりも小さかったと読み、それならね、と納得。 コンコルドが何故追い求めたものの割に不釣り合いな翼を持っていたのか(可変翼に何故できなかったか)。 三グラムを境に内骨格か外骨格かチョイスが分かれる謎。 内骨格-外骨格、そして更に大きく旅客機になれば再び外骨格になるのだが、その選択に関係しているものは何だろうかと言う問いかけ。 読み終わる頃には何よりも自然はコストにシビアなのだと思わざるを得ない。 生き物が飛翔する地点も、時間も季節も、そのフォルムも習性さえも費用対効果で、6月半ばに掲載された魚に関する論文を思い出した。 魚は考える必要がある時に脳を大きくさせ、逆につかわない時は小さく出来ると言う内容で、わずか数ヶ月の間に脳容量を増減できるらしい。 野生と養殖、季節などから見えてきたのは、変化の多い複雑な環境にいる時は増大する傾向がある事。 脳はランニングコストが非常に高いことから、脳の使用が促される時には増え、陸地から遠くにいる季節などは小さく変化する。 飛翔もまさにそんなコストとのせめぎ合いなのだなと面白かった一冊。
Posted by
航空力学。野鳥の飛翔に関してこれは参考になる。初列、次列のそれぞれの風切羽が上から落ちてくるときのスピードと回転の違いもよく理解できる。
Posted by
- 1