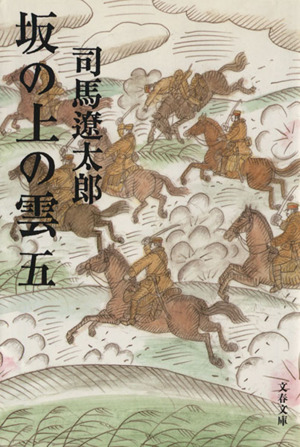坂の上の雲 新装版(五) の商品レビュー
ロジェストウェンスキ…
ロジェストウェンスキー率いるバルチック艦隊がやってきますが、日英同盟のイギリスの協力もあり、艦隊の動きは非常に鈍く、士気も上がりません。世界的にまだまだ後進国であるアジアの小国日本を応援しようとする雰囲気が一部にあったことが良く分かります。
文庫OFF
二百三高地の状況が、(何と無くの知識だったが)本当に凄まじくひどいものだったこと。日本人のある意味異常な精神力を改めて知る。良い方向に行けば… 司馬遼太郎が、ドラマ化映画化に反対していた気持ちがわかる気がする。
Posted by
もうそろそろ読むの疲れてきた。さすがに長いな。 旅順の攻防が描かれていたが、乃木率いる陸軍が周りの意見を無視し正面突破を続けた結果大きな損害を出していたことに苛立ち児玉源太郎が自ら指揮をしたことであっさりと203高地を奪うことができそれに伴い旅順全体も陥落することができた。あまり...
もうそろそろ読むの疲れてきた。さすがに長いな。 旅順の攻防が描かれていたが、乃木率いる陸軍が周りの意見を無視し正面突破を続けた結果大きな損害を出していたことに苛立ち児玉源太郎が自ら指揮をしたことであっさりと203高地を奪うことができそれに伴い旅順全体も陥落することができた。あまりにもあっさりと奪えてしまったことが伊地知たち参謀の無能さが際立つ。 また、バルチック艦隊が喜望峰を回りながら日本に向かうシーンも同盟国だったフランスがロシアの敗戦により非協力的になりなかなかうまくいかないのも今後の海戦に大きく影響するんだろうな。
Posted by
ようやく司馬遼太郎さ(?)というか歴史小説を読むということに慣れてきた感。 ここまで苦しかった…!(笑) 新しい名前や艦隊の名称(とくに外国)が出てくるとその説明や現状についての記述が多くなるので(自分は)だれてしまう。 戦闘時の人々の描写になると、サクサク読めた。
Posted by
坂の上の雲、5巻。 いよいよ二〇三高地の決戦。 旅順攻略がこんなにも困難を極めた原因は、司馬遼太郎の筆から見るに、どうしても第三軍司令部の、とくに参謀長の無能さによるところが大きいと思えてしまう。それに見合う資料をもとに書いているのでしょうが、ここまでけちょんけちょんだとちょっ...
坂の上の雲、5巻。 いよいよ二〇三高地の決戦。 旅順攻略がこんなにも困難を極めた原因は、司馬遼太郎の筆から見るに、どうしても第三軍司令部の、とくに参謀長の無能さによるところが大きいと思えてしまう。それに見合う資料をもとに書いているのでしょうが、ここまでけちょんけちょんだとちょっと気の毒になるくらいだ。 それに対して、児玉源太郎に対する書き方のカッコ良いこと。 黒溝台の章で少しだけ秋山好古がでてきたが、5巻のヒーローは児玉源太郎だった印象が強い。 それからバルチック艦隊の航行。 想像以上に大変だったんだな。 そして想像以上に日英同盟が効いてたんだな。 全編わりと細かすぎるぐらいの描写や、その後やその周辺について余談がめちゃくちゃ多くて、この巻はなかなか読み進まなかった。 1次資料、どれだけたくさん当たって書いたんだろう…。 凄いけど、正直ちょっと退屈だったな。 ともあれあと3巻、 そして日露戦争も佳境中の佳境。 シンプルに戦闘のしんどい表現も多いけど、頑張って読むぞ。
Posted by
【30年ぶりに読む「坂の上の雲」】 第五巻は「二〇三高地」「水師営」「黒溝台」など。甚大な死傷者を出しながらようやく二〇三高地を奪還した日本軍。乃木が詠んだ「爾霊山」の漢詩が染みる。バルチック艦隊は様々な妨害を受けながらアフリカ喜望峰を回り日本に向かっている。 組織、特に官僚機構...
【30年ぶりに読む「坂の上の雲」】 第五巻は「二〇三高地」「水師営」「黒溝台」など。甚大な死傷者を出しながらようやく二〇三高地を奪還した日本軍。乃木が詠んだ「爾霊山」の漢詩が染みる。バルチック艦隊は様々な妨害を受けながらアフリカ喜望峰を回り日本に向かっている。 組織、特に官僚機構の退廃を現代のHRMに置き換えながら令和に読み返す「坂の上の雲」。六巻に進もう。
Posted by
黒溝台途中まで。乃木大将は指揮官としては無能(頑なに自分の意見を曲げず、多数の兵士を死に追いやった…)極まりなかったが、児玉との関係性を見るに人間的にはなかなか魅力的な人物であった。ただ彼らの関係は軍の司令部としてみた場合、私情を挟みすぎたと思う。 戦争の中身というか、武器戦艦他...
黒溝台途中まで。乃木大将は指揮官としては無能(頑なに自分の意見を曲げず、多数の兵士を死に追いやった…)極まりなかったが、児玉との関係性を見るに人間的にはなかなか魅力的な人物であった。ただ彼らの関係は軍の司令部としてみた場合、私情を挟みすぎたと思う。 戦争の中身というか、武器戦艦他、兵士の士気、運などいろんな要素を含んだ上での勝敗なんだなぁとよーく分かったような気がする…。 (※この感想は"司馬史観"を知る前のことなので…(^^;
Posted by
軍人としての乃木の能力が本当にいまいちなのか否かは置いておいて、同世代の軍人仲間から慕われたり心配されたり、敵将を敬ったり敬われたり、無口だけど漢詩などの表現のセンスに長けていたり、といった人としての魅力に富んだ人だったのかな、そしてその点は司馬も認めていたのかな、ということが感...
軍人としての乃木の能力が本当にいまいちなのか否かは置いておいて、同世代の軍人仲間から慕われたり心配されたり、敵将を敬ったり敬われたり、無口だけど漢詩などの表現のセンスに長けていたり、といった人としての魅力に富んだ人だったのかな、そしてその点は司馬も認めていたのかな、ということが感じられた。
Posted by
舞台は激戦の203高地。遼陽の満州軍総司令部から旅順にやってきた児玉が、第三軍司令部にて涙ながらに叱責するシーンが印象的でした。
Posted by
▼旅順が落ちない。なんともストレスである。ただ、通読3回目にして、司馬さんの「なんとなくの小説的意図」に気づく。司馬さんは旅順描写がストレスであろうとわかっていて、加減してはる。でも後でスカッとするためにはある程度ストレスも与えねばならぬ。▼司馬さんの取材もすごいが、それ以上に語...
▼旅順が落ちない。なんともストレスである。ただ、通読3回目にして、司馬さんの「なんとなくの小説的意図」に気づく。司馬さんは旅順描写がストレスであろうとわかっていて、加減してはる。でも後でスカッとするためにはある程度ストレスも与えねばならぬ。▼司馬さんの取材もすごいが、それ以上に語り口がすごい。何かといえば「前代未聞」、「古今に例がない」、「史上初であろう」、みたいな文句が手を変え品を変え。それくらい、つまりは「面白いんだよこれ〜、ね?面白いでしょ?」、「この人物のこのエピソード、最高なんだよね〜、ね?最高でしょ?」ということ。▼これが逆に非難する場合も同じくになる。旅順の作戦司令部とか。▼というわけで語り口に引きずられ引き込まれ、とにかく面白ぇ。
Posted by