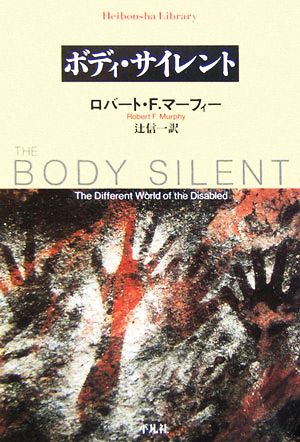ボディ・サイレント の商品レビュー
みずからの病い体験を切り口に社会学的・人類学的な考察を展開する点において本書は当事者が生活体験を綴る従来の闘病記や非当事者がまとめた質的研究と一線を画している。文体もこなれていて読みやすい。
Posted by
脊髄に出来た腫瘍によって徐々に身体麻痺が進んでいくという状態に置かれた人類学者が、自らを取り巻く他者との関係性や制度的な困難さ等々について記述したもの。一人称のエスノグラフィ、ということだろうか。 この書籍からは色んな示唆を得ることが出来そうだけれど、個人的には「フィールドと...
脊髄に出来た腫瘍によって徐々に身体麻痺が進んでいくという状態に置かれた人類学者が、自らを取り巻く他者との関係性や制度的な困難さ等々について記述したもの。一人称のエスノグラフィ、ということだろうか。 この書籍からは色んな示唆を得ることが出来そうだけれど、個人的には「フィールドとは何ぞや?」という疑問が浮かんできたことが発見だった。人類学的フィールドであるところの「異文化」は、病いの進行とともに、暮らし慣れたはずのアメリカ社会のなかに見出されることになる。著者の言葉を借りれば「異郷」である。 これはなかなか面白い話で、空間的には同質な(と信じて疑わない/疑えない)はずの場が、病いの進行とそれに伴う関係性の変化によって「フィールド」として立ち現れてきたという事態を示している。つまり、フィールドワーカーにとってのフィールドは、空間的な場であるだけでなく、他者との関係論的な場でもあるということを意味している。 こうした変化が症状の進行、すなわち身体変化と密接に関係している点は特に重要なのではなかろうかと思う。著者マーフィーの場合、病いの急激な進行、身体変化があったからこそ顕著に見えているだけであって、人は誰しも身体的変化と共に生きている。それを「発達」と呼んだり、「老化」と呼んだりするのだけれど、こうした変化を指し表すのに適した言葉がない場合には、つまるところ判らない。でも本当は、周囲の環境との調節を絶え間なく行って生きているはずで、これが見えていないか、あるいは見えなくするような「文化」が私たちのなかに存在していることが示唆されている。 著者が体験した困難さ、トラブルといったものは「障害」という形で原因が見えている(ように見える)。しかし障害を持たない人々の間で生じるアレコレの出来事の背後にも、実はこうした「異郷」が生じている可能性があって、実際の生きるプロセスというものは普段意識しているよりももっと多様で、ダイナミックなものなのだろうと考えさせられた。 病いや障害にまつわる考え事をしたい人は一読の価値アリかと。 それにしても自分で自分について書く、というのは勇敢な試みだと思ってやまない。果たして「自伝」との区別は如何にして付くのだろう。そこがちょっとピンと来ないのだけれど、「病いによって周囲との関係が一変する」という点について実際の体験談から知ることが出来るという点だけでも、この書籍には価値があることだろう。
Posted by
- 1