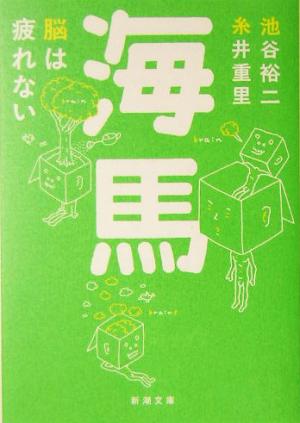海馬 の商品レビュー
糸井重里と池谷裕二との対談 池谷裕二は相当リスクをとった発言をしているなぁという印象。 脳神経でわかっていることは大体この辺というのがわかる。 自分ならもう少し専門性の高い本を読みたいと感じるレベル。 入門書としては良いのでは。 池谷裕二の人柄、人生観なども理解できる(理解した...
糸井重里と池谷裕二との対談 池谷裕二は相当リスクをとった発言をしているなぁという印象。 脳神経でわかっていることは大体この辺というのがわかる。 自分ならもう少し専門性の高い本を読みたいと感じるレベル。 入門書としては良いのでは。 池谷裕二の人柄、人生観なども理解できる(理解したところでなんなんだという気はする)。 自分の精神医学的知見の古さを刷新させるために読んだ本。 まぁ、たぶん、この分野なら、医学部より、理学部生物学科とか、薬学部とかの方が強いでしょう。 扱う内容の技術・専門性が高度で医学部(特に臨床を学ぶ学部として)にフィットしていないのだと感じる。
Posted by
脳は疲れない 脳はモノとモノを結びつける 脳は刺激がないと耐えられない 脳は都合が良いように働く=脳は嘘をつく 人間が整理できる記憶は7つまで=マジックナンバー7 脳を使い尽くす 読了後から、思考の回路を少しでずらしたり、わざと遠回りすることを意識している。 頭の中を、スープ...
脳は疲れない 脳はモノとモノを結びつける 脳は刺激がないと耐えられない 脳は都合が良いように働く=脳は嘘をつく 人間が整理できる記憶は7つまで=マジックナンバー7 脳を使い尽くす 読了後から、思考の回路を少しでずらしたり、わざと遠回りすることを意識している。 頭の中を、スープをゆっくりかき混ぜるようなイメージ。意外に楽しい。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
優しい言い方をする池谷先生と、ちょっときつめの言い方をする糸井先生の掛け合いが面白かったです。もちろん、内容も素晴らしかったです。脳は疲れない、脳は都合よく記憶を改竄するというのが心に残っています。私はこの本の影響で脳科学に興味を持ちました。学者にはなれませんが、この分野は生涯追っていきたいと思います。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
池谷さんもスゴイが、糸井さんの比喩・話の引き出しの多さによって、とても腹オチした。まさに、頭のいい人ってそう言う事。 記憶を作り出す『海馬』(保存していくところは別)と、感情を司る『扁桃体』の連携。 この強さによって、経験が蓄積され、どちらかが欠けた時に、脳は都合良く(錯覚して)解釈する。 脳は疲れない!考え続ける程に答えが出る!30代からでも脳は成長する! アラサーの私はこれを励みに学び続ける( ̄ー ̄)
Posted by
「行列ができているのに銀行の受付の人がのんびり事務処理をしているだとか……いろんな価値観を通すとおたがいにやっていけなくなるので、価値観の「最大公約数」のようなところで通じあっているように思いました。」 脳、特に記憶を司る海馬に焦点を当て、その構造について話し合われた本。クリエ...
「行列ができているのに銀行の受付の人がのんびり事務処理をしているだとか……いろんな価値観を通すとおたがいにやっていけなくなるので、価値観の「最大公約数」のようなところで通じあっているように思いました。」 脳、特に記憶を司る海馬に焦点を当て、その構造について話し合われた本。クリエイティブとは脳内での無関係な出来事同時が組み合わされる事。 夢は記憶の整理。経験した事がないことは夢に現れない、はず。しかし、実際には経験した事ないことも夢に現れる。それは本や映画で追体験しているからか。 脳の役割は、情報の保存と処理。 心とは脳の活動状態。
Posted by
池谷さんの本は何冊読んでも読みやすく、腑に落ちやすい。 海馬とは、情報を取捨選択して脳のどこに保管しておくのかを判断して振り分ける。 記憶の関門となる、脳の真ん中辺りの両側ありタツノオトシゴみたいな形をしている部位。 記憶とはなにをするにも必須なもの。 運動をするにも勉強をす...
池谷さんの本は何冊読んでも読みやすく、腑に落ちやすい。 海馬とは、情報を取捨選択して脳のどこに保管しておくのかを判断して振り分ける。 記憶の関門となる、脳の真ん中辺りの両側ありタツノオトシゴみたいな形をしている部位。 記憶とはなにをするにも必須なもの。 運動をするにも勉強をするにもなにかを考えたりするにも、全てが記憶があっての出来事。 記憶があるから物事を考えられるし、話すことも出来るし運動も出来る。 その記憶に必要な海馬を大きくすることが記憶を強固にするのに繋がる。 海馬を大きくする為の必要なことを抜粋します。 ・生きることに慣れてはいけない、今までとは違う刺激に触れる ・海馬と扁桃体は隣接していてかなりの情報交換をしている。 扁桃体は感情を司る部位だから「好きなことならよく覚えてる」「興味のあることだからうまくやっていける」と言うのは筋が通っている。 ・ストッパーを外すと可能性が広がる(P45) ・センスは磨ける ・タクシードライバーの勤続年数が長いほど海馬が大きい ・アセチルコリンとはやる気の脳内物質。 そのアセチルコリンを抑える作用にあるのが風邪薬だったり下痢止めの薬。 下痢止めを飲むことによって腸の活動は弱められるが、一緒に脳のアセチルコリンも制御されてしまう。 因みにアルツハイマーはアセチルコリンが作用しにくくなる病気だから、アルツハイマーの人には生気や覇気がない顔になってしまう ・問題を解決するには問題を一つずつ書いて一つずつ解いて行く
Posted by
は疲れ知らず。 自分で限界を決めずどんどん刺激を与えて使っちゃおう! 脳もコミュニケーションが大事らしい。 他人とのそれが苦手なので、そこの所はちょっと気が重い。
Posted by
二回目。やっぱりおもしろい。夢は寝ている間に海馬が情報を整理している証拠。夢を見る時間を与えない(寝ない)と脳の成績は落ちる。扁桃体と海馬、つまり感情と記憶は深く関わってる。あと、糸井さんが小学生のときに、ウソの日記を書いていたという話、忘れてた。忘れちゃうからまた読みたい。
Posted by
「心は脳が。活動している状態を指す。物体ではない。脳を細分化していても心はどこにも見出せないだろう。車を部品に解体したところで『スピード』というものがどこにも表れないのと同じ事である。」 いいなぁ♪ 前半1/4くらいまで、イイ感じに噛み合わず、面白くなって来なくて困ったけど、そ...
「心は脳が。活動している状態を指す。物体ではない。脳を細分化していても心はどこにも見出せないだろう。車を部品に解体したところで『スピード』というものがどこにも表れないのと同じ事である。」 いいなぁ♪ 前半1/4くらいまで、イイ感じに噛み合わず、面白くなって来なくて困ったけど、その分響き合ってからはエキサイティングだった!!
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
脳学者の池谷先生と糸井重里の対談本。海馬は脳の記憶をつかさどる部位で、この海馬の機能・特性を軸に人間の脳の特性について様々な分析をしていきます。糸井重里はややしゃべりすぎ。しかしいい意味での素人視点で専門家からうまく引き出しています。脳科学ものとしては茂木健一郎のものよりも面白いかも。
Posted by