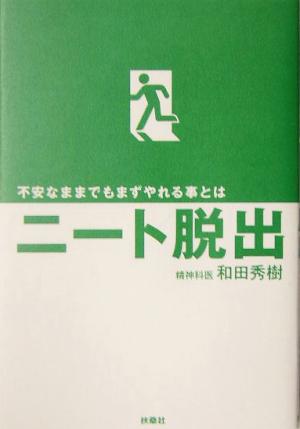ニート脱出 の商品レビュー
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
あくまで個人の感想ですので読んで感じたままに書いてます。 2000年代初頭のデータから「あれが悪い」「こうだからダメなんだ」「こうだからニートになるのだ」という言い回しが多い。 言ってることは正しいが上から目線で、表面だけの情報や数値・統計のデータからこういう人がニートになるという話ばかり。直接ニートと関わったり表面的ではなくきちんと向き合ったことあるのかな?と違和感や偏ったものを感じて読むのやめました。 最後まで読むと変わるのかもしれないけど滲み出るバカにした感じが読む気失せる。 心理学や環境・病気などにはあまり触れず、精神に寄り添ったものというよりはデータ本。
Posted by
『ニート脱出』という本を読みました。 表紙がまさに脱出法という感じで惹かれました。 結構面白かったのでいかに内容をまとめました。 ーーーー ニートは元々はイギリスの「Non in Education Employment or Training」の略で、教育課程でな...
『ニート脱出』という本を読みました。 表紙がまさに脱出法という感じで惹かれました。 結構面白かったのでいかに内容をまとめました。 ーーーー ニートは元々はイギリスの「Non in Education Employment or Training」の略で、教育課程でなく何らかの就業トレーニング中でもない人の意。日本ではアルバイトなどもしていない無職の人がニートとされています。 イギリスでは、18歳から失業保険が適応されるため、このような人々が福祉予算を食いつぶすことで社会問題になったそうです。 アメリカでは校内暴力をなくそうとして問題児にカウンセリングをしてもうまくいかず、厳密な罰則を与えるとうまくいった例を取り上げ、心の問題をそのまま心の問題として取り上げるよりも、行動の面から解決する重要性を説いています。 以下面白かった点 ーーーーーーーーーー ◆自分への飴と鞭の与え方。 例えCD一枚であっても、勝ち取ったものは貴重。その喜びが気持ちを前向きにしてくれる。 意外と楽だったな、これならもう5社くらい訪問できるかも、と思えばそれこそがやる気である。 ーーーー ◆満点主義が強すぎるとニートになる 解けない1問目は捨てよ! 自分にとって難しい問題は、ひとまずスルーして次を解こう。正解できる可能性の低い問題に労力を使うのは無駄。 それにもし、短所を直しても、うまいけどただそれだけの人間になるだけだ。 ーーーー ◆失敗したら、能力がないのではなくてやり方が悪かったと思え。 そして次はもっとうまくやればよい。 ーーーー ◆引きこもりでも仕事が出来ればよい。 これは目から鱗。 本書では引きこもりのままバイク便のバイトを始めた人の例が挙げられているが、今の時代、ネット上でバイトをすることもできるし、確かに会社勤めだけが正解ではないのかも。 ーーーー ◆プライドにとらわれるな アメリカでは高学歴無職でマクドナルドでアルバイト、は普通。 一流大学の大学院やビジネススクールを出た人がマクドナルドで働いてたりする。 理由は、自分の望むような仕事に就けるまでの「つなぎの生活資金」を稼ぐため。それを恥ずかしいと思う風潮はない。 だから堂々とアルバイトを始めるとよいよという話。 ーーーー ◆学歴はうまく使え この仕事は大学出た自分のするべき仕事じゃないとか、そういうプライドはいらない。逆にアルバイトでも、家庭教師などは大学出の方が信頼されやすいのでそういうときはうまく使えばよい。 ーーーー ◆親は上手な突き放しを ニートは甘えが原因だといって、突き放すのはうまくいかないそうだ。逆効果になりやすい。 必要なのは上手な突き放しで、例えば、「寝るところと食事は面倒みるけど」小遣いは一切やらない、といったような感じ。 ーーーー 本書では、主に比較的高学歴なニート向けに書かれているような印象を受けた。 内容はわかりやすく的確だと感じたが、せやかてわかってるけどそれができんのよ、という意見もあると思う。 個人的には、そんなときにこそカウンセラーとか使えばいいのかなと思う。 本書を読んで、目標達成の手助けとしてカウンセラー呼んで、「こうしたいけどこうならない、だから手伝って」といえば彼らも力を発揮でき、ニートではなくなりそう、と本書を読んで思いました。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
チェック項目5箇所。本書では、ニートを社会問題として論じるのではなく、そのような批判を(ときどききついことをいわせてもらっているが)極力廃しながら、私が精神科医や臨床心理士の立場から、そのような問題を抱えてニートとなっている人に、具体的にどのような心持ちになり、どのように生きていけばいいか、そしてまず第一歩を踏み出すにはどうしたらいいかを論じることにした。イギリスでは、就業経験がなくても、18歳になれば無職なら失業手当が給付される、ブラブラしていても、国が養ってくれるというわけだ、それが、ニートを増やす背景になっているともいわれている。「パラサイトシングル」的ニート……いつまでも結婚せず、食住は親に依存し、自分で稼いだカネは自分だけのために使う人たち、まだ仕事をしているだけマシだったかもしれないが、これが仕事もしなくなったら、まさにニートだ、パラサイトシングルとニートとは紙一重でしかない。1995年調査のときに中学2年生だった人たちは、1981年生まれという計算になる、ということは、厚生労働省がニートの数が52万人になったと騒いでいる2003年には、22歳くらい、高校を卒業しているが、大学に入っても卒業で就職を目前にしているか、すでに就職している年齢だ、この年代こそがニートの中心なのだ、学力低下が指摘されはじめた世代が、ニートを急増させていることになる。現在は、一流大学を卒業したからといって一流といわれる企業に入れるわけではない、一流企業に入ったからといって、リストラの対象にされないという保障はどこにもない。ニートの子どもを前にして、子どもの要求に応じるだけではダメだ、ニートは「社会に対する不適応」である、それをなおすためには、「適応できる力」を養わなければならない。
Posted by
タイトルが気になり、読んでみました。 完璧ニートの人が、この本を読んですぐ就職のために行動できるようになるかは正直微妙だと思います。「それが難しいんだって」と思う箇所もいくつかありました。 が、自分がニートになりそうで不安な人、なりかけてる人には効果があると思います。 無意識のう...
タイトルが気になり、読んでみました。 完璧ニートの人が、この本を読んですぐ就職のために行動できるようになるかは正直微妙だと思います。「それが難しいんだって」と思う箇所もいくつかありました。 が、自分がニートになりそうで不安な人、なりかけてる人には効果があると思います。 無意識のうちに世の中・仕事・人間関係・自分自身に対して、理想を高く持ちすぎていることに気づきました。 自分の今までの考え方(ネガティブな思考パターン)が一刀両断されていくのは、読んでいて気持ちが良かったです。
Posted by
「能力じゃなくやり方」や「やりがいへの妄想」のくだりは、わかりやすく脱出の手口になった気がします。 ただニート本人に向けて書かれているのに、読み進めるにつれて親の心構えについての内容になり誰にあてて書かれている本なのかはっきりしません。居ないとはいいませんが、親子で同じ本を貸しあ...
「能力じゃなくやり方」や「やりがいへの妄想」のくだりは、わかりやすく脱出の手口になった気がします。 ただニート本人に向けて書かれているのに、読み進めるにつれて親の心構えについての内容になり誰にあてて書かれている本なのかはっきりしません。居ないとはいいませんが、親子で同じ本を貸しあうほどの仲のニート親子は少ないと思いますし、ニート目線で読んでも、親の立場に立って最初から読んだとしても、ちぐはぐな感が否めません。 また、このような書き方をすることで新たな言い訳をニートにささげてしまっているようで逆にニートから脱出できなくなっちゃうのではないでしょうか。 ニート本人は前半を読み親に向けて書かれているところをあえて読まないことをすすめます。
Posted by
なりたくなくてもニートをやっているヒトもいると思います。 この本を読めばなんとか脱出できるかも??!
Posted by
本屋さんで軽く立ち読みしました。ニートって意外に簡単になってしまうものだと私は感じます。今、『ニートでない』生活を送っている人も、ある日ふとした拍子に『ニート』の生活に転じてしまう。当たり前のことが当たり前に書いてあって、でもそういうことをひとつひとつ丁寧に解きほぐしていくことが...
本屋さんで軽く立ち読みしました。ニートって意外に簡単になってしまうものだと私は感じます。今、『ニートでない』生活を送っている人も、ある日ふとした拍子に『ニート』の生活に転じてしまう。当たり前のことが当たり前に書いてあって、でもそういうことをひとつひとつ丁寧に解きほぐしていくことが必要なんじゃないかなと思い、私は良本に感じました。(by はに〜)
Posted by
- 1