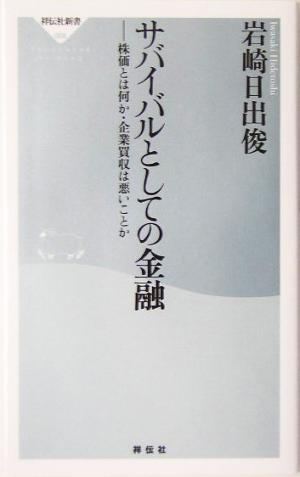サバイバルとしての金融 の商品レビュー
株式投資に負け続けて…
株式投資に負け続けている方には本来の投資の指針を記述した本で、著者の外資系金融機関時代の経験をもとにした内容であり、非常に現実味のあるものである。
文庫OFF
「金融日記」 彼曰く、金融が正しく発達すると、 ●努力した人が報われる ●リスクを取って成功すればリターンが大きい ●経営者は株主に雇われている。経営者のミッションは企業価値の向上にある(株価を上げることができない経営者は退場する) ●従業員が目を輝かせて、生き生きと働いている...
「金融日記」 彼曰く、金融が正しく発達すると、 ●努力した人が報われる ●リスクを取って成功すればリターンが大きい ●経営者は株主に雇われている。経営者のミッションは企業価値の向上にある(株価を上げることができない経営者は退場する) ●従業員が目を輝かせて、生き生きと働いている会社は伸びる ●一部の既得権者が既得権の上にあぐらをかかない。競争のシステムを導入する ●グラスシーリングを撤廃する。能力や実績と関係ない「国籍や男女の別」で差別しない。「入社年次で昇進していく、あるいは出身大学で昇進が左右される」という、おかしなロジックから卒業する
Posted by
最近読んだ「日本人がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門 もう代案はありません」と似てる。個人が頑張って成果を出せば紙の見えざる手が働きトータルでプラスになるよ。というのが筆者の主張。難しい言葉も多くなく読みやすい。ふつうの1冊という印象。
Posted by
『そうだったのか 手塚治虫』 中野晴行 『水族館の通になる』 中村元 『マザコン男は買いである』 和田秀樹 『模倣される日本』 浜野保樹 『「震度7」を生き抜く』 田村康二 『ウチの社長は外国人』 大宮知信 『医療事故』 押田茂實
Posted by
実にやさしい金融の本。 日本には何がかけているのか、 どうして日本の銀行はアメリカの銀行に 遠く及ばないのか… これだけでもかなり分かるはずです。 本当にこの本には学校でも 社会でも教えてくれないことが たくさん出てきます。 お金儲け、というものが決して汚いものではない という...
実にやさしい金融の本。 日本には何がかけているのか、 どうして日本の銀行はアメリカの銀行に 遠く及ばないのか… これだけでもかなり分かるはずです。 本当にこの本には学校でも 社会でも教えてくれないことが たくさん出てきます。 お金儲け、というものが決して汚いものではない というのがわかるはず。 そして余りすぎた人は正しくない、と思えるはずです。 たまに出てくるお金持ちの中にも そういう人居ますよね。 そういう人にはならないように…
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
日本人としての価値観に理解を示しながら、株の売買やM&Aが建設的なものであることを徐々に説明してくれる本。 読み物として面白かった。 *米企業のほうが、少なくとも日系企業よりも、個人の幸せを重視した会社経営であるらしい。(日本は共同体の利益を優先するために、例えば転勤などは言われるまま)
Posted by
真面目な金融リテラシーの本 興銀出身でアメリカのビジネススクールでMBA取得後外資系金融機関経験を積んだ著者の真面目でわかりやすい金融本。 「株価は、その本来の価値を実現する価値に落ち着く」 という考えのもと、企業価値の視点を持つことの大切さ、企業価値を極大化する経営をわかり...
真面目な金融リテラシーの本 興銀出身でアメリカのビジネススクールでMBA取得後外資系金融機関経験を積んだ著者の真面目でわかりやすい金融本。 「株価は、その本来の価値を実現する価値に落ち着く」 という考えのもと、企業価値の視点を持つことの大切さ、企業価値を極大化する経営をわかりやすく説明。 この本が、リーマンショック前に書かれていることが驚きだ。 ライブドアや村上ファンドなどが一世風靡していた中、世界の著名な経営人は意外に質素(真面目)な生活をしている等々、お金にコントロールされずに、お金をコントロールする生き方を伝えており金融リテラシーの大切さも伝えている。 最後にまとめると、 ・努力した人が報われる ・リスクをとって成功すればリターンも大きい ・経営者は株主に雇われている。経営者の役割は企業価値の向上 ・従業員が目を輝かせ、生き生きと働いている会社は伸びる ・既得権者が既得権の上にあぐらをかかずに、競争システムを導入 ・グラスシーリングを撤廃 この本を読めば、金融や資本主義が肯定的に見られるようになると思う。
Posted by
市場は効率的で、株価はその企業の価値と最終的には一致する。 上がりすぎた株価もいつかは落ち着く。 安くみられてる株を探すということですね。 そのためには企業価値から妥当な株価の算出が何より大事。 それができれば失敗はしない。 そして極めて効率的な市場にうまい話は絶対...
市場は効率的で、株価はその企業の価値と最終的には一致する。 上がりすぎた株価もいつかは落ち着く。 安くみられてる株を探すということですね。 そのためには企業価値から妥当な株価の算出が何より大事。 それができれば失敗はしない。 そして極めて効率的な市場にうまい話は絶対にない。 極めて投資家的な視点で見ているので、 日本企業を叩いてる面も多いです。 前述の会社は株主のものという話もですが、 日本に多い企業の多角化。その言い訳のシナジー効果は、 投資家にしては、企業が勝手に事業ごとのポートフォリオを 組んでるのと同じことで、それは投資家自身がやることであり、 無駄であると。 なんか、そこまで投資家視点言われてもねぇ。。。 確かに最近では手広く設けるより、1点集中が見直されてるし、 アメリカなんかでは大分前からそうですし。 今はサブプライムの前に書かれた本の内容なので 今後どういった話になるのかは楽しそうですが。 90~05年ぐらいで日本の株価とアメリカの株価の推移を強調し、 後半は日本の駄目っぷりをこき下ろします。 土地神話の崩壊も、海外企業にはわかりきっていたし、 日本企業は海外でも不動産を買いあさっていた。 価値(将来のキャッシュフロー)も考えずに。 市場原理主義と日本の調整(政府・官僚主体)主義の経済対策にも言及。 これはほんと難しいと思うんです。 民衆は時に見る目がなかったり、無知だったりで誤った選択をする。 優秀な独裁者も時に暴走したりして誤った選択をする。 前者の方が無駄が多く非効率で、後者の方が間違わなければ 効率的にことが運ぶんだが、現時点では人類は民主主義を形成し、 それが最終的な状態なわけですから。 会社にもあてはまるのか? は、わかりませんが。 日本企業というか、本当の資本主義・市場の自由の原理を理解していれば、 それぞれの利益の最適化から、おのずと神の手が働いて、 万人が幸せになるはずです。ということかな。 そりゃなかなか難しいでしょうね。 株価・株主の事どころか、会社の根本的なことも知らずに、 自分の仕事・給与が増える・増えないでしか 働いていない人も沢山いますからねぇ。 なんか本のタイトルとちょっと内容が違う気がしたけど、サブタイトルが 「株価とは何か・企業買収は悪いことか 」だったのね。
Posted by
[ 内容 ] 過去十五年でアメリカの“株価”は四倍に上昇、日本のそれは三分の一に減じた。なぜこれほどの差がついたのか。 そもそも“株価”とは何なのか。 著者は社会を動かす株と金融の基本を驚くほど平易に説き明かしてくれる。 「株を買う=その会社の一部を買う」「株価=その会社の真の価...
[ 内容 ] 過去十五年でアメリカの“株価”は四倍に上昇、日本のそれは三分の一に減じた。なぜこれほどの差がついたのか。 そもそも“株価”とは何なのか。 著者は社会を動かす株と金融の基本を驚くほど平易に説き明かしてくれる。 「株を買う=その会社の一部を買う」「株価=その会社の真の価値」「会社の価値(値段)はこうして決まる」―これらの本質さえ分かれば、将来伸びる会社は予測できる。 同時に世間を賑わす企業の合併・買収(M&A)の仕組みと功罪も見えてくる…。 第一線で活躍する金融のエキスパートが、個人と社会を豊かにするための知恵を満載して贈る、まったく新しい金融入門。 [ 目次 ] 第1章 「金融」はあなたを金持ちにするか 第2章 お金にコントロールされずに、お金をコントロールする生き方 第3章 「儲かる株を見つけることが社会を豊かにする」とはどういうことか 第4章 儲かる株はどうやって見つけるのか 第5章 本来の株式価値を計算する 第6章 株式市場の効率化を助けるM&A(合併・買収) 第7章 企業価値の視点を持つ 第8章 企業の価値を極大化する経営とは 第9章 金融の前線から 第10章 米国投資銀行の現場から 第11章 市場からレッドカードをもらわないために [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
金融初心者向けの入門書。 内容は大まかに 1.株式などの金融商品を購入する際に考慮しなければならない事柄についての概説 (株価・金利・キャッシュフローetc.) 2.日本と米国における企業経営の差異 に分けられる。 1,2を通して平易な言葉で書かれており、また金融の世界での著名...
金融初心者向けの入門書。 内容は大まかに 1.株式などの金融商品を購入する際に考慮しなければならない事柄についての概説 (株価・金利・キャッシュフローetc.) 2.日本と米国における企業経営の差異 に分けられる。 1,2を通して平易な言葉で書かれており、また金融の世界での著名人の興味深いエピソードもふんだんに盛り込まれているため読みやすい。 2ではどの事例に関しても米国の戦略の方が日本より優れているという視点から書かれていたが、これは金融市場での大多数の意見なのだろうか。 物事の優劣を判断するということは、必ず著者の主観が反映されているということなのでこの本に書かれていることを全てを鵜呑みにするのは危ない、と思う。
Posted by
- 1
- 2