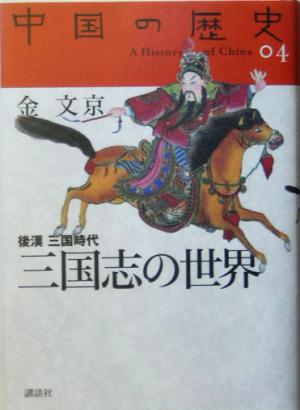三国志の世界 の商品レビュー
良く知られた三国志の時代の話であるだけに、この内容の薄さは残念でした 正史について書かれたものならこれより詳しいものがいくらでもありますので、入門として初めて手に取る以外にこれを読むべき理由は見当たりませんでした
Posted by
学生時代に出逢った本の中で一番三国志について勉強になった本です。解説も分かりやすく全体的に読みやすいのでお勧めです。
Posted by
三国志の本はたくさん有りますが、概説書というと、なかなかないんでないのん? 後漢か魏晋南北朝にドッキングされちゃうといか。 演義と比較しながら史実を説明してくれます。 紙や仏教、今で言うディベートの文化も最新の研究を踏まえながら解説。 さらに、呉の天下二分戦略や、魏、蜀、その他...
三国志の本はたくさん有りますが、概説書というと、なかなかないんでないのん? 後漢か魏晋南北朝にドッキングされちゃうといか。 演義と比較しながら史実を説明してくれます。 紙や仏教、今で言うディベートの文化も最新の研究を踏まえながら解説。 さらに、呉の天下二分戦略や、魏、蜀、その他の外交戦略についても説明してくれます~~
Posted by
三国志初心者も中級者も楽しめる良書。史書だけではなく、考古学観点からも三国時代を検証した章などもあり、楽しめます。
Posted by
文章が読みやすいですね。また、三国時代の歴史的意味、紙の普及や書体革命、「文学自覚」(魯迅)の時代などの観点が提起されています。正統思想に拘らない呉の孫権や魯粛の考えを強調している点が興味ぶかい観点です。彼らの考えをさぐることで天下に縛られないアジアの国際関係も可能なのではないか...
文章が読みやすいですね。また、三国時代の歴史的意味、紙の普及や書体革命、「文学自覚」(魯迅)の時代などの観点が提起されています。正統思想に拘らない呉の孫権や魯粛の考えを強調している点が興味ぶかい観点です。彼らの考えをさぐることで天下に縛られないアジアの国際関係も可能なのではないかと説いていて、なかなか刺激的です。芸能や清談、在野の学者による儒教の総合化や、道教・仏教の普及も興味深く書いてあります。『演義』の成立も横目で睨んでいる所は芸が細かいです。
Posted by
中国の歴史シリーズイェーイ!!珍しく、そう…珍しくも呉を中心に見ている本なのですよ…!それだけで買う価値があるってもんですよ!ヒュウッ!
Posted by
もっと三国志を知りたいアナタへ。 黄巾より前の時代や、孔明が死んだ後の時代も、幅広く知ることができます。 小説ではないので、より三国志を知りたい方向き。
Posted by
中国史の通史を概説するに際して三国期は存外描きかたがむずかしいとおもう。 この時期については、巷間での三国志の人気のおかけで、かなりこまごました人物まで名前が知られている。ほかの時期ならば重要人物に絞ってかきすすめればよいのだけれども、三国期では主要な人物のみの概説では読み物...
中国史の通史を概説するに際して三国期は存外描きかたがむずかしいとおもう。 この時期については、巷間での三国志の人気のおかけで、かなりこまごました人物まで名前が知られている。ほかの時期ならば重要人物に絞ってかきすすめればよいのだけれども、三国期では主要な人物のみの概説では読み物としての魅力に缺けてしまう。もちろん、史実と小説は違うのたけれども読者としてどうのように感じるかは別の問題なのだろう。 本書は、そうした知られすぎてかえって描きにくい時代をうまく工夫して概説書にしあげている。正史三国志、小説『三国志演義』では、ともに低く扱われている呉を切り口にしてみたり、宗教にとりわけ注目したり、アジア史のなかでこの時代がどうであったかと問うてみたり、という具合である。 そうであっても第1章〜第4章いわゆる三国志演義の範囲は淡々としたものになってしまっている。だが、第5章以降は最近の考古学の成果を利用したり、社会状況、社会の階級、宗教、視野を東アジア全域にうつしてかきすすめられており、人物描写中心になりがちな三国期ものとしては出色の概説書となっている。 もっともおもしろいのは末尾の部分である。秦漢期で形成された「中国の唯一無二の正統な皇帝とその王朝こそが世界全体の支配者である」(p.345)という正統論(つまりは中華思想であろう)がこの三国期での各国の存在理念として各々に都合がよいようにとらえられ、また後代北方異民族の支配下におかれた際には北方の魏を異民族になぞられ漢を自称した蜀に正統を冠するような民間での抵抗というような民族問題的な側面もあったする。さらには、この正統論(中華思想)が東アジア諸国にひろく浸透した結果、日本は天皇を中心とし、朝鮮もまた中華文明の後継者を自任するという自らに都合良く正統を理解した。これは現代史においてもつづいており、大陸と台湾は各々が中国の統治者を自任し、大韓民国と朝鮮人民共和国も同様に理念上互いを無視する。 著者は、三国期を「現代中国の起点」(p.17)としているが、末尾における東アジア各国の正統論の行を読むに中国だけでなく「現代東アジアの起点」であることがみえてくる。 著者は最後に次の一文で本書の筆をおいている。 「現在の世界はグローバル化の波の中、欧州連合(EU)、東南アジア諸国連合(ASEAN)など歴史的に関係の深い文化圏の連合かが大きな潮流となりつつある。その流れの中で、世界でもっとも交流の歴史が長く、かつ今でも漢字をはじめとする多くの文化を共有する日本、中国、朝鮮・韓国の三国が、連合化への第一歩さえ踏み出せずにいるのは、なぜであろうか。多くの人々はその理由を、日清戦争、日中戦争あるいは日本による台湾、朝鮮の植民地化という19世紀以来のこの三国間の不幸な歴史に帰するであろう。しかし問題の根は、それほど浅くはない。1800年前の三国時代の歴史を、今日的な視点からもう一度見つめなおす必要があるのはそのためである。」(p.357) 追:呉を重視する姿勢は六朝へとつながり、名士階級中心の国家運営も六朝へ、文史哲の発展も直後の六朝で大きく昇華していくことを考えると、前半部分の三国志部分がいかにも余分のような気すらしてしまいます。六朝についてはこのシリーズの第5巻の範囲ということはわかっているのですが、魏晋南北朝として著者のとらえ方を読んでみたくなりました。
Posted by
- 1