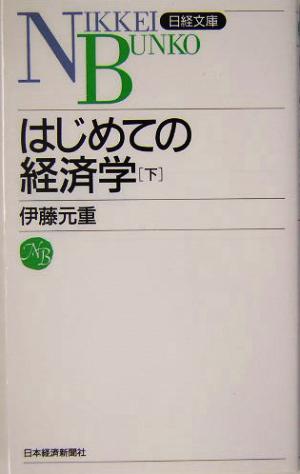はじめての経済学(下) の商品レビュー
上巻と同じく200ページ弱のボリュームの新書。 その中で「公共部門の経済学」「金融システムを理解する」「人と組織の経済学」「国際経済学を見る目」の4テーマが扱われている。上巻では「マクロ経済学」「ミクロ経済学」「経済学史」「戦後日本経済の流れ」「ゲーム理論」を扱っており、どちらか...
上巻と同じく200ページ弱のボリュームの新書。 その中で「公共部門の経済学」「金融システムを理解する」「人と組織の経済学」「国際経済学を見る目」の4テーマが扱われている。上巻では「マクロ経済学」「ミクロ経済学」「経済学史」「戦後日本経済の流れ」「ゲーム理論」を扱っており、どちらかと言えば全体の理屈的なものだったのに対して、下巻では現実の経済の各論を扱っている。 上巻・下巻ともに、それぞれのテーマのエッセンスがコンパクトに分かりやすく書かれていた。本当に基本的な経済学の概説なので、別に目新しいことが書かれているわけではないが、経済学の全体をもう一度整理して理解しておこうという人にとっては、良い本だと思った。
Posted by
頑張って読みました。 世界について、うっすらわかったような気がしますが、まだまだ難しいです。 もっと勉強したいので、また経済学の本読みます。
Posted by
弟の教科書を読んでみたのだが、つまらない。 もっと楽しく書いてもらわないと困る。 しかし教科書とは往々にしてこういうものだ。
Posted by
▼福岡県立大学附属図書館の所蔵はこちらです https://library.fukuoka-pu.ac.jp/opac/volume/287978
Posted by
下巻では、公共経済学や金融、労働と企業、国際経済などに関する諸問題が分かりやすく解説されています。 ただ、せっかくビジネスの現場に降りて経済学という道具を使いこなすことに定評のある著者だけに、たとえば流通の具体的な事例なども参照しながら説明をしてほしかったように思います。とはい...
下巻では、公共経済学や金融、労働と企業、国際経済などに関する諸問題が分かりやすく解説されています。 ただ、せっかくビジネスの現場に降りて経済学という道具を使いこなすことに定評のある著者だけに、たとえば流通の具体的な事例なども参照しながら説明をしてほしかったように思います。とはいえ、上巻同様、たいへん分かりやすい説明には違いなく、他の経済学入門書を読む前に、本書によって大まかなイメージを得るといったニーズには最適の本ではないかと思います。
Posted by
上巻の基礎をベースに財政・金融・国際経済などの具体的な分野の経済問題を扱うことで考え方を学べる。日本銀行とか株とか信用取引とか「知らなくてもできるけどなんか気持ち悪いキーワード」をやさしく解説してくれている。個人的にはパレート均衡や比較優位等の概念が出てきて、経済学におけるゲーム...
上巻の基礎をベースに財政・金融・国際経済などの具体的な分野の経済問題を扱うことで考え方を学べる。日本銀行とか株とか信用取引とか「知らなくてもできるけどなんか気持ち悪いキーワード」をやさしく解説してくれている。個人的にはパレート均衡や比較優位等の概念が出てきて、経済学におけるゲーム理論の重要性を再認識した。
Posted by
新しいものかと思ったら、意外と古いものだった。 普遍的なことは背景も含めてよく分かりやすくコンパクトにまとめられている。 もう一息まとめて一冊にしてくれていると更に良かったのだが。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
上巻は経済学の基礎概念的な話が多かったが、下巻はより具体的な経済事象も解説している。 1. 公共部門の経済学 ・先進国は経済全体に占める公共部門の割合が非常に大きい ・公共部門には、三つの機能がある。①所得分配を公平化する機能、②資源配分において民間経済を補完する機能、③マクロ経済の調整機能 ・①生活保護、失業保険、公共サービス、地域間の財政配分による ・②民間経済に任せた場合に起こる「市場の失敗」として、外部効果(自動車による大気汚染等)、公共財(電波等)、費用逓減産業(鉄道等)の三つが代表的 ・③公共投資や政府消費の活動を拡大させたり、抑制させることにより、景気に影響を及ぼす(財政政策) ・日本の債務比率は約250% 2. 金融システムを理解する ・銀行間の決済は日本銀行の口座を通じて行われ、口座のことを預金準備という。日本銀行は国債などの売り買いを通じて預金準備額を調整し、金融政策を行う。 ・決済性の高い預金のみを入れた現金と預金の和である「M1」から、もう少し貯蓄性の高い預金まで含めた「M2」など、貨幣の総量をマネーサプライと呼ぶ ・中央銀行はハイパワードマネー(現金と預金準備)を増減させることにより、短期金利を調整し、金融政策の運営を行っている 3. 人と組織の経済学 ・企業は財・サービスの供給者、労働者にとっての働く場、金融市場の資金の貸し手・借り手、CSRを行う市民としての役割などがある。 4. 国際経済を見る目 ・国際収支表を読むと、日本経済の変化が読み取れる。①経常取引、②資本取引、③金融取引 ・①経常取引はモノ、サービス、所得、移転取引に分類される ・日本は貿易大国から次第に投資から利益を得られる収益大国になっている ・中央銀行や政府は、為替レートの動きを見ながら、外貨準備を調整することにより、為替介入を行う。 ・比較優位
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
①公共の経済学:市場配分機能を補完する、外部効果・景気安定化機能・政府財政・プライマリーバランス ②金融システム:銀行決済機能・紙幣の機能(価値尺度・価値貯蔵・取引媒体)・金は天下の回りもの・中央銀行の役割・株式の動き ③人と組織:企業の役割・垂直統合・失業とは・独占市場・ ④国際経済を見る:国際収支表・経常収支・為替レート(固定化・国境を越えた自由な取引・自国のマクロ経済を維持)・政府の介入・為替ヘッジ・輸入企業&輸出企業・比較優位(リカード)
Posted by
下巻は応用篇。公共部門、金融システム、人と組織、国際経済、をそれぞれ扱う4章からなる構成です。ニュースなどで目にする経済政策のキーワードがどういう意味を持つのか、なんとなく分かるようになったような、気がします....
Posted by