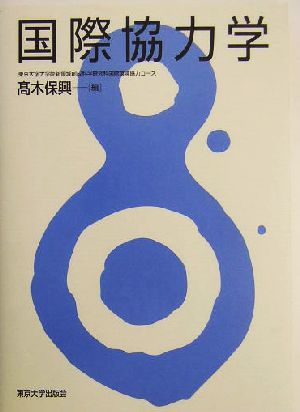国際協力学 の商品レビュー
国際協力に関する言説を、体系的にまとめた本。国際協力学というと曖昧だが、本書では、国際政治学と国際経済学からの視点を織り交ぜ、グローバル化しつつある世界において、どのように国際協力の概念が変わってきたのかという点に焦点を当てている。 グローバル化が引き起こした、国際政治学上の...
国際協力に関する言説を、体系的にまとめた本。国際協力学というと曖昧だが、本書では、国際政治学と国際経済学からの視点を織り交ぜ、グローバル化しつつある世界において、どのように国際協力の概念が変わってきたのかという点に焦点を当てている。 グローバル化が引き起こした、国際政治学上の最も重要な点は、アクターの多様化である。すなわち、国家を最も重要なアクターとする古典的な考えから、企業やNGOなど多様なアクターが、国境を越えて活動しているということである。国際協力のフィールドにおいても、これまで国家というアクターが、安全保障・経済的メリットのために開発途上国に対してODAを実施していたものが、グローバル化が引き起こしたアクターの多様化にために、NGOや企業も開発途上国の場で、何らかの貢献ができるようになったのである。 開発途上国が抱える問題は多様である。言い換えれば、解決すべき最上位の中心問題が「貧困削減」だとか「経済発展」というものだとしても、それに付随する副次的な問題は、教育・保健・インフラ等多様な分野にわたっている。従って、中心問題の解決には様々なアプローチが必要なのである。国際協力というものは、アクターが違えばその目的も、対象とする分野も異なる。つまり、先進国家が実施するODAと、企業やNGOによる活動は、その原資も違えば目的も違うのである。一見、個々に自由に活動しているように見受けられるが、クロスセクトリアルだからこそ、開発途上国が多様化した副次的な問題を効率的に解消できる可能性がある。ここに、企業・NGOと国家が、課題解決のために協力関係を結ぶインセンティブが発生すると筆者は説く。そして、今後はどのようにそれを深化すべきかを考えるべきだと主張する。
Posted by
東京大学大学院新領域創生科学研究科国際環境協力コース所属の教授陣による「国際協力学」の教科書で、非常にお堅い内容のマクロ視点な一冊です。キーワードとして「戦略的思考」を打ち出しているけれども、それぞれの先生がたの専門領域(環境法学、開発経済学、統計学、農業工学など)以外のアプロー...
東京大学大学院新領域創生科学研究科国際環境協力コース所属の教授陣による「国際協力学」の教科書で、非常にお堅い内容のマクロ視点な一冊です。キーワードとして「戦略的思考」を打ち出しているけれども、それぞれの先生がたの専門領域(環境法学、開発経済学、統計学、農業工学など)以外のアプローチ方法にほとんど触れられていないのが残念でした。 最近教育開発関係の本ばかり読んでいて、国際協力全般について書かれたものを読んでいなかったので、その意味では新鮮でした☆
Posted by
- 1