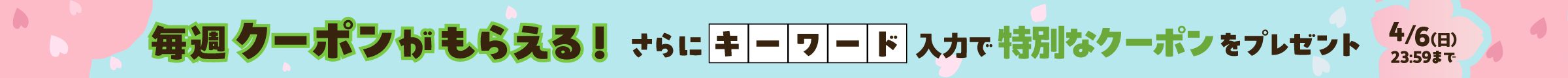エドマンド・ウィルソン批評集 文学(2) の商品レビュー
骨太で、実務的、力でぐいぐい押しまくり、自説を主張して倦むことがない。裏表紙にある著者の写真(太い眉、ぎょろりとした眼、への字に固く結ばれた口許)から受ける印象そのままの文学批評集である。 もっと評価されてもいいはずだと思うのに他の批評家が評価しない作家(「プーシキン礼賛」「デ...
骨太で、実務的、力でぐいぐい押しまくり、自説を主張して倦むことがない。裏表紙にある著者の写真(太い眉、ぎょろりとした眼、への字に固く結ばれた口許)から受ける印象そのままの文学批評集である。 もっと評価されてもいいはずだと思うのに他の批評家が評価しない作家(「プーシキン礼賛」「ディケンズ-二人のスクルージ」)やその傾向(「フローベールの政治観」)、逆にそれほどでもないと思うのに多大な評価がなされている作家(「カフカについての異議申し立て」)や作品(トールキンの『指輪物語』)傾向(「探偵小説なんかなぜ読むのだろう?」)について、自分の思うところを訴えようと力を入れて書いた文章が中心。そのため、文章が適度な熱を帯びている。そこらあたり、ジャーナリストをもって任じる著者が、学者上がりの批評家とちがうところ。その論に賛成するにせよ反対するにせよ、読む側としては引き込まれて読まされる仕組みだ。 専門的な文学愛好者向けに書くわけではなく、つねに雑誌という場に文章を発表してきたジャーナリストとして、ウィルソンの書くものは素人にも分かりやすい。ディケンズを例にとれば、その生い立ちから晩年にかけて、作品と実生活上のできごとを対比させながら、じっくりとその業績の全貌を明らかにしてゆく。読者としてはよくできた伝記でも読んでいるような軽い気分で、ウィルソンならではの視点で構成されたディケンズ論を読まされることになる。 ディケンズは幼少時に家が窮乏して靴墨工場に徒弟奉公にやられた経験がある。それまでの境遇とかけ離れた一年半にも及ぶ屈辱的な経験が、ディケンズの社会に対する〈反抗的〉な面を形成したというのが、ウィルソンの立論である。ここからも分かるように、ウィルソンの文学論は、あくまでも人間中心。テクスト論の出る幕はない。「カフカについての異議申し立て」などは、ほとんど、カフカに意気地がなさすぎる、もっと戦えと言っているようなもので、自分の性向に対する無意識さといい、その素朴な人間観には微笑ましさを覚えるほど。文学が世界や人間と今より直截に結びついていた時代の幸福な文学批評、とでも言えばいいだろうか。 いくつもの外国語が読め、特にロシアには滞在もしていたウィルソンである。ロシア文学に対する言及が多いのは当然かもしれない。「プーシキン礼賛」などは、『エウゲニー・オネーギン』一巻をまるで読み聞かされているような感銘を受ける。映画『オネーギンの恋文』で見たレイフ・ファインズの端正な面立ちを思い出した。しかし、いくらロシア語が堪能なウィルソンにしても、あのナボコフの『オネーギン』英訳を槍玉に挙げた(「プーシキンとナボコフの奇妙な事例」)のは勇み足だった。 ナボコフがアメリカの出版界に受け入れられるまでにウィルソンの果たした役割の大きさを考える時、この批判が引き起こした論争と、その後の二人の仲違いは本当に残念である。よく読めば、ナボコフの文学の持つ価値についてもかなりの部分が割かれているとはいえ、本質的には亡命ロシア人の英語力に対する揶揄と受けとめられても仕方のない調子の文章に、ナボコフから痛烈な批判が返されたことは言うまでもない。 どちらかといえば、ウィルソンの方に分が悪かったこの論争。文学の中にあくまでも人間を読み取ろうとするウィルソンが、文学を言語で構築されたゲームと考えていたナボコフの土俵にまちがってのってしまったというのがその敗因だろう。革命によって亡命を余儀なくされたリベラル派政治家の息子と、西欧におけるマルクス主義受容の跡を追った『フィンランド駅へ』の著者が友情を結べたこと自体、もともと奇蹟のようなものだったのかもしれない。
Posted by
- 1