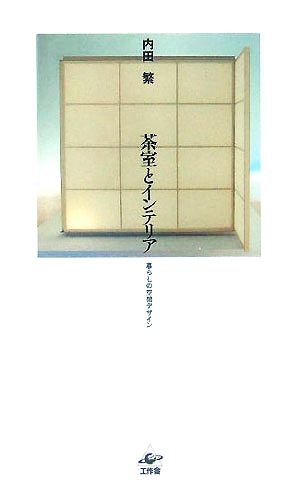茶室とインテリア の商品レビュー
インテリアデザイナーの著者が日本の暮らし、建物、インテリアの歴史をたどり、暮らしの空間デザインのありようを模索し、問いかけるもの。
Posted by
建築に詳しくない身としては、家や茶室という空間を通しての日本文化論のように感じた。読みやすく、わかりやすい。
Posted by
和風建築のしつらえを考えるとき、さまざまな写真やディテールの本などを参照するものだが、「なぜそのデザインか」という哲学的観点では、いまのところこの本が私にとっての教科書です。
Posted by
日本人のもつ「沓脱ぎの文化、床座の文化」。この根源となる精神性は、茶室という形式で究極に純化され、そこから現代の日本の住宅空間へとつながっている。その流れを、平易な文章で綴っており、とても分かりやすい。 モダニズムのテーマであった「能率」。しかしこれはあくまで身体性にとっての能...
日本人のもつ「沓脱ぎの文化、床座の文化」。この根源となる精神性は、茶室という形式で究極に純化され、そこから現代の日本の住宅空間へとつながっている。その流れを、平易な文章で綴っており、とても分かりやすい。 モダニズムのテーマであった「能率」。しかしこれはあくまで身体性にとっての能率であった。精神にとっての能率は、まったく評価軸が異なる。 珠光の言葉を借りる。 空間をつくる、一建築家として、「和漢の境をまぎらかす」ことのないよう、地に足つけて、和の感性を大事にしていきたいと思う。
Posted by
-和洋の境をまぎらかすということは、表層的表現を融合することではない。その文化的背景の根源性を融合させることだろう。二十一世紀の文化は、日本文化の根源的性格に多くのヒントがあるのではないか・・・といった視点が、今日、ヨーロッパの哲学者、デザイナーなどから浮かび上がっている- か...
-和洋の境をまぎらかすということは、表層的表現を融合することではない。その文化的背景の根源性を融合させることだろう。二十一世紀の文化は、日本文化の根源的性格に多くのヒントがあるのではないか・・・といった視点が、今日、ヨーロッパの哲学者、デザイナーなどから浮かび上がっている- かの"桑沢デザイン研究所"の所長であり、紫綬褒章、藝術選奨文部大臣賞受賞など、日本を代表するインテリアデザイナーの内田繁さんの著作。2005年に出版されたもの。 山本耀司さんのブティックも内田さんなんですよ~ 内田繁さんの代表作をあげると凄すぎてレビューのスペースがなくなりそうです(~~;) 本書の構成は 座、間、風、水、火、談、飾、祀、色、心、と10もの章にわかれ、さらに、一つの章を4~9に見だし分けしていて、大変読みやすい。章の言葉がたった一文字からなっているのと同様、本文にも必要最低限の言葉で成り立っている。 「茶室とインテリア」というタイトルのとおり、日本家屋(家具も含む)の歴史を文化と共に語っていて、日本を語る上で欠くことのできないキーワードについては、欄外で補足している。 インテリアのみならず、建築を志す人にとってはまたとない教科書でしょう。同時に、インテリアにも茶室にもまったく興味がない人も、手に取って、ちょっと読み始めると、「あれ?」と気になってハマってしまうと思います。 相当お勧めです。
Posted by
素晴らしかったです。随所で人生の生き方と照らし合わせることが出来るような深い言葉が綴られてます。 過去の文化を保守的な立場で評価するのではなく現代の最前線と言い張って評価する姿勢が良かったです。もちろん説得力もあります。 久しぶりに建築関連の本が読みたいと思って買ったのに、気づい...
素晴らしかったです。随所で人生の生き方と照らし合わせることが出来るような深い言葉が綴られてます。 過去の文化を保守的な立場で評価するのではなく現代の最前線と言い張って評価する姿勢が良かったです。もちろん説得力もあります。 久しぶりに建築関連の本が読みたいと思って買ったのに、気づいたら人生について考えさせられてました。
Posted by
- 1