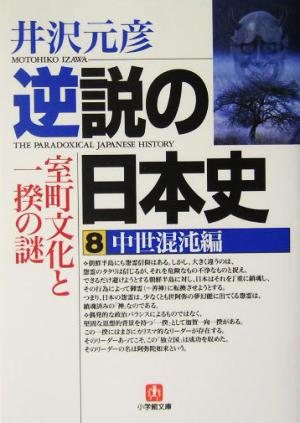逆説の日本史(8) の商品レビュー
一揆が起こった理由に…
一揆が起こった理由について、宗教的的な面から説明がなされているので納得しました。
文庫OFF
シリーズ8巻。通説に…
シリーズ8巻。通説に疑問を持っている人などは一度目を通してみてもいいだろう。
文庫OFF
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
①③足利尊氏と後醍醐天皇との争い、南北朝に日本が分かれていく過程を書いていたような・・・ ②太平記から①③の内容+筆者の主張の補完のイメージ ④足利義満について、天皇になろうとした将軍という視点で書かれていて、面白かった ⑤足利義教=魔王として君臨した独裁政権のパイオニア、織田信長の先輩としての視点でこれも興味深かった
Posted by
応仁の乱は東軍と西軍が入り乱れていて解りづらい。本書に接して理解が進んだ。 山城国一揆と加賀の一向一揆についても勉強になった。 「将棋、この日本文化の最高峰」は一将棋ファンとして嬉しく読んだ。
Posted by
本巻では、応仁の乱から山城の国一揆および加賀の一向一揆までの歴史と、能を中心とする室町文化について説明がなされています。 本書のような読みやすい日本史の解説本のばあい、無責任極まる室町幕府八代将軍の足利義政と、恐妻の日野富子というキャラクターに焦点があたってしまいますが、本書で...
本巻では、応仁の乱から山城の国一揆および加賀の一向一揆までの歴史と、能を中心とする室町文化について説明がなされています。 本書のような読みやすい日本史の解説本のばあい、無責任極まる室町幕府八代将軍の足利義政と、恐妻の日野富子というキャラクターに焦点があたってしまいますが、本書では政治的混乱を生み出した背景についてもかなり立ち入ってていねいに説明がなされており、興味深く読みました。 将棋をモノポリーにたとえるなど、著者の連想が大きく飛躍しているように感じられるところもありますが、それも含めてこのシリーズのおもしろさなのではないかと思います。
Posted by
日本史を授業とは別の視点から読み解くシリーズ第八弾。 今回は、室町時代の終焉から戦国時代への突入まで。 足利義政が将軍になるところから始まるわけだけど、なんせ似たような名前や読みづらい名前が多いので訳がわからん。誰が誰の子供で誰とどういう関係なのかが、油断すると頭に入ってこない。...
日本史を授業とは別の視点から読み解くシリーズ第八弾。 今回は、室町時代の終焉から戦国時代への突入まで。 足利義政が将軍になるところから始まるわけだけど、なんせ似たような名前や読みづらい名前が多いので訳がわからん。誰が誰の子供で誰とどういう関係なのかが、油断すると頭に入ってこない。 でもまあ要約すると、政府の責任者(この時代だと将軍(家)ね)が責任を取らず逃げ回っている、約束を守らない(どっかで聞いたような)、私腹を肥やす等からモラルが下がり、それならと言うことで各地の守護が勝手なことを始め、戦国時代へと突入していくと言う話。応仁の乱もこの時期だけど、これも将軍が約束を守らなかった事による跡目争いが発端。 それはそれとして、今の日本文化と言われる部分の原型ができた時代だったよう。
Posted by
今回の出張でも、例に漏れず出張のお供「逆説の日本史」を読んだ。 あまり人気のない時代の室町時代、さらにマイナーな足利義政が中心の巻だったが、目に鱗の話が目白押しだった。 懶惰の帝王義政と妻日野富子の関係性の面白さ。 将棋、折り紙、風呂敷、花道、茶道など室町時代を起源とする驚き。 ...
今回の出張でも、例に漏れず出張のお供「逆説の日本史」を読んだ。 あまり人気のない時代の室町時代、さらにマイナーな足利義政が中心の巻だったが、目に鱗の話が目白押しだった。 懶惰の帝王義政と妻日野富子の関係性の面白さ。 将棋、折り紙、風呂敷、花道、茶道など室町時代を起源とする驚き。 勉強になりました。
Posted by
流し読みのため第4章のみ通読。能が怨霊との絶縁体として面を用いている、将棋は死穢の思想を反映した戦争ゲームではなく経済ゲームになっている、などなど。鋭い洞察が随所にみられる。筆者と読者の温度差を多少感じつつも歴史を振り返ることができる良書。 第1章 「懶惰の帝王」足利義政編 第...
流し読みのため第4章のみ通読。能が怨霊との絶縁体として面を用いている、将棋は死穢の思想を反映した戦争ゲームではなく経済ゲームになっている、などなど。鋭い洞察が随所にみられる。筆者と読者の温度差を多少感じつつも歴史を振り返ることができる良書。 第1章 「懶惰の帝王」足利義政編 第2章 日野富子と傀儡政権編 第3章 国一揆と一向一揆編 第4章 室町文化の光と影編
Posted by
実は、このレビュー、読後ずいぶん立ってから書いてるのですが、この巻は印象が薄い。 この時代に始まった文化への興味がないせいかもしれない。
Posted by
おなじみの『逆説の日本史』 第8巻では室町八代将軍・足利義政の時代(応仁の乱)や室町文化、一向一揆の発生などがメインテーマ。 応仁の乱という、十年以上も続いた未曾有の戦乱の中、現在の日本文化のルーツとも言える室町文化が花開いたのは不思議な感じがする。和室、お茶、懐石料理、生け花...
おなじみの『逆説の日本史』 第8巻では室町八代将軍・足利義政の時代(応仁の乱)や室町文化、一向一揆の発生などがメインテーマ。 応仁の乱という、十年以上も続いた未曾有の戦乱の中、現在の日本文化のルーツとも言える室町文化が花開いたのは不思議な感じがする。和室、お茶、懐石料理、生け花、能、将棋・・・この時代に始まったといわれるものは数限りない。 知らなかった・・・。
Posted by
- 1
- 2