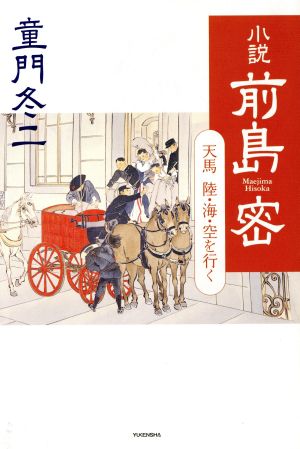小説 前島密 の商品レビュー
一読した感想は,「これは小説とは言えない。伝記だ」ということです。 小説というからには,なにか,著者の気持ちが着色されていたり,たとえば主人公の家族のにおいがしたりするものですが,そういうのは,ほとんど感じられません。あくまでも密の自伝に忠実に描かれていて,それはそれで,いい...
一読した感想は,「これは小説とは言えない。伝記だ」ということです。 小説というからには,なにか,著者の気持ちが着色されていたり,たとえば主人公の家族のにおいがしたりするものですが,そういうのは,ほとんど感じられません。あくまでも密の自伝に忠実に描かれていて,それはそれで,いいんじゃないかな。『知られざる前島密』よりも詳しく描かれているものもあったので,読んで損はしませんでした。 「郵研社」という出版社名は初めて聞きました。書籍にはさまれていた「出版案内」を見ると,『日本の郵政』『郵便局POPの達人』『郵政事業の新展開』『これさえあれば大丈夫!郵便局英会話110』など,郵便事業に関する書籍をたくさん扱っているようです。そう,この出版社は,郵便局に勤務する方々への本を出版している会社なんです。 このように郵政専門の出版でやっていけるだけの需要が現場にはあるというわけでしょう。確かに,郵便局は,それこそ,田舎の津々浦々までちゃんと存在しているのですから,考えてみるとすごい制度です。 密は,郵便制度を全国展開するときに,地方のある程度お金と地位のある家に,郵便の事業を任せる「郵便取扱所(のちに郵便役所→郵便局)」を設けました。その名残が,地方に点在している今の郵便局なのですね。 当時の事情について,著者が次のように述べています。 地方に設けられた郵便取扱所の責任者,すなわち後の郵便局長はかなり協力的だった。かれらは,「政府の誠意と公衆の便益のために,奮ってその任に当たります」といってくれた。これは,藩政時代でも,大名から,「名字帯刀を許され,何人扶持の給与を与える」といわれれば大変名誉なことだったことに通ずる。今度は,朝廷から給与を支給され,政府の職員に任命されるのだから,命ぜられた局長たちにとっては,「無比の大栄誉」だったのである。(265p) 国家的な制度として出発した郵政は,小泉構造改革により民営化されてしまいます。それでも,ちゃんと地方で成り立っているのは,全国一律の郵便運賃(切手)の制度など,前島密が西洋から学んで作った制度がしっかり根付いているからでしょう。このまま,どんな遠隔地にも,同一料金で葉書や手紙が届く時代が続いてほしいものです。たとえ,メールが普通になっても…。
Posted by
- 1