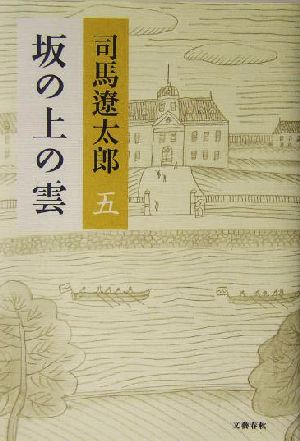坂の上の雲(5) の商品レビュー
不利な条件下での外債発行で最低限の戦費を調達し、軍事、外交、諜報の限りを尽くして国家の総合力を発揮して辛勝を勝ち得る日露戦争において、本巻は特にロシア革命を策動する諜報部分と陸軍の辛勝を重点に描かれている。物語の構成上軍事作戦が中心になるのは当然であるが、諜報や外交など軍事作戦...
不利な条件下での外債発行で最低限の戦費を調達し、軍事、外交、諜報の限りを尽くして国家の総合力を発揮して辛勝を勝ち得る日露戦争において、本巻は特にロシア革命を策動する諜報部分と陸軍の辛勝を重点に描かれている。物語の構成上軍事作戦が中心になるのは当然であるが、諜報や外交など軍事作戦以外が丁寧に描かれており、明治日本がいかに日露戦争を勝ち得たかの全体像を俯瞰できる。 また現代も含めて太平洋戦争やその後の日本の停滞との比較や、日露戦争で辛勝できたことの負の側面が後の歴史に与える影響まで思いを至らせる司馬史観の集大成と思える小説である。
Posted by
日本が最も熱かった時代、明治。先進国に追いつけ追い越せという風潮の中で経験した日清、日露という二つの戦争。中でも日露戦争について同時代を生きた2人の軍人の兄弟と1人の俳人の人生を通じて同時代を鮮やかに描き出す。言わずと知れた司馬遼太郎の代表作。詳細→http://takeshi3...
日本が最も熱かった時代、明治。先進国に追いつけ追い越せという風潮の中で経験した日清、日露という二つの戦争。中でも日露戦争について同時代を生きた2人の軍人の兄弟と1人の俳人の人生を通じて同時代を鮮やかに描き出す。言わずと知れた司馬遼太郎の代表作。詳細→http://takeshi3017.chu.jp/file7/naiyou23903.html
Posted by
本人の典型的な気質のひとつとして存在するおべっかを含めたなれなれしさ、というより相手に子猫のようにじゃれさせたいために、つまりは相手の心をこのような形でとりたいために、自分の属する上部高層の無知、臆病もいあものを卑屈な笑顔でぶちまけてしまうという心理あり。 日本人は情景が劇的で...
本人の典型的な気質のひとつとして存在するおべっかを含めたなれなれしさ、というより相手に子猫のようにじゃれさせたいために、つまりは相手の心をこのような形でとりたいために、自分の属する上部高層の無知、臆病もいあものを卑屈な笑顔でぶちまけてしまうという心理あり。 日本人は情景が劇的であればあるほど、その主観的な要素を内部にしまいこんでしまうところがあり、東郷平八郎のこの光景は能に似ていた。 戦争というのは過ぎてしまえばつまらないものだ。軍人はそのつまらなさに耐えなければならない。 黒木為もと 小説とは要するに人間と人生につき、印刷するに足りるだけの何事かを書くというだけのことであり、それ以外の文学理論は私にはない。司馬遼太郎
Posted by
第5巻は、アフリカ東岸のマダガスカルの田舎ノシベに2カ月も留まらされたバルティック艦隊の話から始まり、ヨーロッパで諜報活動を大々的に行って、ロシア国内の内乱に大きく影響したといわれる明石大佐、旅順を辛くも攻略して、漸く北進して奉天戦線に参加する乃木軍、修繕を終え、韓国沖で周到な砲...
第5巻は、アフリカ東岸のマダガスカルの田舎ノシベに2カ月も留まらされたバルティック艦隊の話から始まり、ヨーロッパで諜報活動を大々的に行って、ロシア国内の内乱に大きく影響したといわれる明石大佐、旅順を辛くも攻略して、漸く北進して奉天戦線に参加する乃木軍、修繕を終え、韓国沖で周到な砲撃、艦隊訓練を繰り返した東郷艦隊までが描かれる。 乃木軍は、囮としてロシア軍を引き付ける作戦を受けることで、再び苦しい戦いを強いられる。しかし、乃木将軍は相変わらずおこることもせず、粛々と作戦を遂行。前と変わらず、周囲の観戦外国士官や新聞記者の尊敬を集める。旅順で降伏したロシア軍のステッセルも彼の態度には感銘を受けたようです。そういう不思議な雰囲気を持つ人だったのでしょう。そしてそれらの賞賛が、日露戦争の勝利と相まって、後に陸軍が予想もしなかった乃木将軍の神話へ昇華していくのですから、不思議ものです。 さらに、戦力では圧倒的だったロシア軍が奉天会戦でなぜ再び負けたのか?その理由は、司令官の資質の問題と兵士一人ひとりの気構え、洞察力の差というのは、面白い分析だと思った。寡兵の日本軍は、リスクの大きい包囲作戦に賭け、ロシア軍司令官クロパトキンは結局日本軍の計略に嵌り続けた事が最大の要因というわけです。それにしてもよくも勝ち取ることができた薄氷の勝利であった訳です。 すでに物語の中心は、秋山兄弟から日本陸軍、海軍、ロシア陸軍、海軍へと組織の話に移っており、如何に組織というのは、人一人の意識を超えて動くものなのかを物語っている。それにしても、明治の人の骨太さ、芯の強さはどうだ。これが、日本人の原型なのか?!それゆえに、その後の悲劇を招いたのか?そのあたりを紐解く必要はありそうです。
Posted by
面白いんだけど、集中して読まないとただ文字を目で追うだけになってしまって、読むのにかなり時間がかかった。戦争は参謀長の能力が重要。そして、それ以外でも諜報活動や、アメリカと講和条約へ持っていく為の準備を水面下で行ったり色々な仕事があるのだと知った。ラスト6巻に突入!
Posted by
[○2008/11/22完読]ついに二百三高地。「国家は貴官を大学校に学ばせた。貴官の栄達のために学ばせたのではない」と兒玉源太?が発言する場面には感動しました。バルティック艦隊航海を「人類の集団がなしうる最大のエネルギーがここに使われていることはまぎれもないことであった。・・・...
[○2008/11/22完読]ついに二百三高地。「国家は貴官を大学校に学ばせた。貴官の栄達のために学ばせたのではない」と兒玉源太?が発言する場面には感動しました。バルティック艦隊航海を「人類の集団がなしうる最大のエネルギーがここに使われていることはまぎれもないことであった。・・・」というくだりで表現している部分、なんだかぞくっとしました。確かにこういう規模で発せられるエネルギーには(戦争だけに限った話ではないけど)人間を突き動かす、すごい何かを感じます。普通に生きていてそんなことに巡り合う機会は皆無かもしれません。
Posted by
バルチック艦隊、マダガスカルのノシベに足止め〜ロシア革命への誘導、スパイ(明石元二郎、シリヤスク、カクトレン)、「血の日曜日」(ガボン)〜乃木軍北上、津野田是重〜バルチック艦隊出発、日本海軍訓練・奉天会戦(右翼鴨緑江軍、左翼乃木・騎兵)
Posted by
- 1