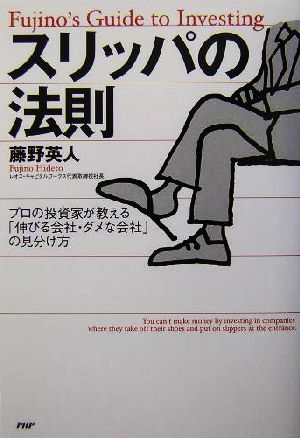スリッパの法則 の商品レビュー
感想 投資家の目に耐えられる会社。ビジョンにコミットしているか。実はオペレーション以外の部分に現れている。どう見極めるかが重要。
Posted by
かつて大きな話題になった、企業の目利き術に関する藤野さんの著作。タイトルは秀逸だけど、本質は、当たり前のことを当たり前に評価するということ。同時に、常識に捉われず本質を見抜くこと。銀行員や投資家だと、思わずあるあると思ってしまう内容が盛りだくさん。金言・名言とマーフィーの法則の中...
かつて大きな話題になった、企業の目利き術に関する藤野さんの著作。タイトルは秀逸だけど、本質は、当たり前のことを当たり前に評価するということ。同時に、常識に捉われず本質を見抜くこと。銀行員や投資家だと、思わずあるあると思ってしまう内容が盛りだくさん。金言・名言とマーフィーの法則の中間くらいの戒めかな。
Posted by
良い会社に投資をすることで、 一緒に世の中を良くすることに 参画していこうという意識を強く持つことにこそ 意味があるのだという言葉が心に響きました。
Posted by
書中ではほんの1ページ半程度しか触れられていない、玄関でスリッパに履き替える会社は投資しても儲からないという経験則の話をタイトルにした本。著者も冒頭で言っているようにマーフィーの法則のような経験則なので、半分冗談でもあるが、大体は皆がなんとなくそう思っているような事、例えば受付が...
書中ではほんの1ページ半程度しか触れられていない、玄関でスリッパに履き替える会社は投資しても儲からないという経験則の話をタイトルにした本。著者も冒頭で言っているようにマーフィーの法則のような経験則なので、半分冗談でもあるが、大体は皆がなんとなくそう思っているような事、例えば受付が美人ばかりの会社や相談役がいる会社、役員の数が多すぎる会社など、納得はできるものが多い。しかし、実際の投資に使えるような話は少ない。よくあるブログ程度の内容の本。
Posted by
2004年出版なので、少しふるが、藤野社長の経験則によって書かれた内容で、なかなか面白い。仕事がら参考になった。藤野さんの講演会に今度は行ってみたい。。
Posted by
要は形にこだわる会社は大したことない。大事なのは中身だよ、中身。っていう。2004年の本、先見の明はあった。 ライブドアがすごいって言ってるのは時代を感じる。確かにすごいことになったなぁ。 ここに出ているような合理的な会社がだいぶ浸透してきて、やっぱなんだかんだ言っても...
要は形にこだわる会社は大したことない。大事なのは中身だよ、中身。っていう。2004年の本、先見の明はあった。 ライブドアがすごいって言ってるのは時代を感じる。確かにすごいことになったなぁ。 ここに出ているような合理的な会社がだいぶ浸透してきて、やっぱなんだかんだ言っても日本人は「カイゼン」出来る人たちだなぁ。と思った。南国の人間とは根本的に違うよね。 今ならスタートトゥデイ(ZOZOTOWN)とか特集されるんだろうな。無駄を省くっていう点では。 ゼロ年代では合理性にとがっている企業がトレンドになった。 10年代、20年代では、合理性を追及した先に見える、抽出された人間性が大事になるだろう。そうおもう。 その点で、AI市場が期待できる。人間の不合理の研究が進んで、合理的なコンピュータにあえてノイズである非合理な判断基準を搭載することで円滑に社会が機能する。それをAIが学習する。そうすると、人もまた一つ精神構造が進化できるとおもう。 会社訪問でスリッパに履き替えるような会社は無駄が多い精神がある。だから業績は伸びないだろうと判断する。なんか非常に人情的なことを言っている本で、若干の矛盾を感じた。しかし、言ってることは納得できることだから、、、 この人のほかの本も読もうと思います。 投資だけじゃなく、人としての思想を見直すのにも役立つなぁと思います。
Posted by
ファンドマネージャーの会社を見分ける哲学がわかりやすく説明されていて参考になった。 株って相場と業績で左右される。相場って誰にも読めないで業績を地道に調査していくということがわかって自分的には参考になった
Posted by
著者の体験ベースの定性的な経験則が書かれた本。 まさか著者もこのようななんの裏も検証もない体験則をベースに投資をしているわけではあるまい。 これを読んで投資をするとよいカモになれる。
Posted by
ロボットが社長を務めたり、労力の一部をロボットやコンピュータが代替していても全従業員がロボットという会社はない訳で、会社は「人」で成り立っていて、そして、その人たちが「未来」を創っていることを再認識した一冊でした。 十人十色。個々人の色が如何に輝いているか。個人が輝くと同時に、...
ロボットが社長を務めたり、労力の一部をロボットやコンピュータが代替していても全従業員がロボットという会社はない訳で、会社は「人」で成り立っていて、そして、その人たちが「未来」を創っていることを再認識した一冊でした。 十人十色。個々人の色が如何に輝いているか。個人が輝くと同時に、他の人を如何に輝かせるか。そして、その集合体という「会社」をどのように輝かせるのか。 その会社の「らしさ」を表すカラーを、従業員たちがきれいにグラデーションで彩っていたら、なんてステキなことなんだろう。
Posted by
2004年の本なので、ちょっと内容は古いかな。関連する仕事に関わってきたからか、特に目新しい話はなかった。
Posted by