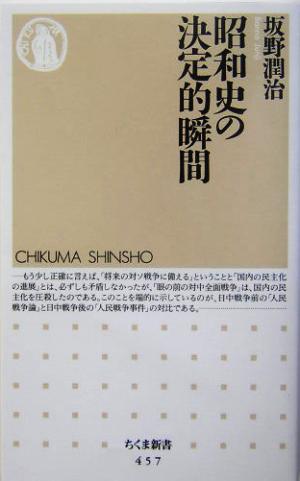昭和史の決定的瞬間 の商品レビュー
戦前日本に関して一般に抱かれているイメージは、昭和11年の2・26事件により軍ファシズムの時代が到来し、その軍ファシズムの手によって,翌12年7月7日の盧溝橋事件が惹き起こされた、というものである。その大前提となっているのは、まず国内政治においてファシズムが民主主義を押しつぶし、...
戦前日本に関して一般に抱かれているイメージは、昭和11年の2・26事件により軍ファシズムの時代が到来し、その軍ファシズムの手によって,翌12年7月7日の盧溝橋事件が惹き起こされた、というものである。その大前提となっているのは、まず国内政治においてファシズムが民主主義を押しつぶし、国民は戦争に向かう日本政府の動向について全く情報を与えられず、戦争を予期し反対しようとした人々には、反対行動はもとより言論の自由も全く与えられなかった、という歴史認識である。しかし本書を読むと昭和12年7月の日中戦争直前の日本では、軍ファシズムも自由主義も社会民主主義もすべて数年前と比べようもなく、力を増していると筆者は述べている。つまり政治が活性化していて、民主化の頂点で日中戦争が起こり、その戦争が民主化を圧殺していったという論なのだ。その詳しい真偽は本書を読んでもらうしかないが、従来の通説でない新しい視点だと思った。詳細→ https://takeshi3017.chu.jp/file10/naiyou28003.html
Posted by
昭和11から12年にかけて生じた日本近代史における危機ないし転換点の実態を明らかにしている本です。 昭和11年の二・二六事件以来、軍によるファシズムが支配的となり、民主主義が押しつぶされて日中戦争へ突入していくことになったという見かたがひろく流布していますが、著者はそのような歴...
昭和11から12年にかけて生じた日本近代史における危機ないし転換点の実態を明らかにしている本です。 昭和11年の二・二六事件以来、軍によるファシズムが支配的となり、民主主義が押しつぶされて日中戦争へ突入していくことになったという見かたがひろく流布していますが、著者はそのような歴史像が誤りであることを論証しようとしています。たとえば、マルクス主義経済学者の大森義太郎による人民戦線論が発表されており、そのなかで彼が選挙を通じて国政を変えていくことをひろく国民に訴えかけていたことからも、言論の自由が完全にうしなわれていたわけではないと著者は主張します。 その一方で、大森の国民戦線論は、まったくべつの理由によって現実性をうしなってしまったことを、著者は示しています。民政党と政友会の二大政党が、それぞれの置かれている状況のなかで憲政のありかたについての主張をおこない、美濃部達吉の天皇機関説も純粋な憲法学的観点からではなく、そうした政治的な状況のもとでそれぞれの態度が決定されていきます。とりわけ著者は、美濃部が議会を軽視した円卓巨頭会議の構想をいだいていたことを指摘し、民主主義の擁護者とみなすことができないと論じています。そのうえで、小泉内閣の政治状況に触れつつ、「改革」と「平和」というディレンマが当時においても存在していたという問題を提起しています。 また盧溝橋事件から十五年戦争へと入り込んでいく展開についても、作家の中野重治や哲学者の戸坂潤、軍事評論家の武藤貞一などが、その後の展開についての見通しを示していたことに触れて、国民にはこのときの危機について知るすべがなかったとはかならずしもいえないことを指摘しています。
Posted by
昭和11年2月20日第19回総選挙から、昭和12年7月7日盧溝橋事件までの1年5ヶ月に絞って書かれた本。 ポイントは宇垣内閣の失敗にあるとみた。
Posted by
昭和戦前と言うと軍部の膨張ばかりがイメージとしてあるが、自由主義も社会民主主義も含め様々な勢力が政治の舞台で蠢いていた。広田内閣後の宇垣一成への大命降下、石原莞爾らの工作による組閣流産から趨勢が変わったが、それでも日中戦争前夜まで日本では民主主義がそれなりに機能していた、とのこと...
昭和戦前と言うと軍部の膨張ばかりがイメージとしてあるが、自由主義も社会民主主義も含め様々な勢力が政治の舞台で蠢いていた。広田内閣後の宇垣一成への大命降下、石原莞爾らの工作による組閣流産から趨勢が変わったが、それでも日中戦争前夜まで日本では民主主義がそれなりに機能していた、とのこと。いままでの理解がガラッと変わる分析で新鮮だった。
Posted by
著者は歴史家には珍しく?単なる叙述ではなく概念化する事に特徴がある。満州事変→515という戦争→テロの前期の危機と、226→日中戦争というテロ→戦争の後期の危機を比較し、後期に着目し論じている(226はテロではなくクーデターではないか?と思うが)。この辺は井上寿一の「昭和デモクラ...
著者は歴史家には珍しく?単なる叙述ではなく概念化する事に特徴がある。満州事変→515という戦争→テロの前期の危機と、226→日中戦争というテロ→戦争の後期の危機を比較し、後期に着目し論じている(226はテロではなくクーデターではないか?と思うが)。この辺は井上寿一の「昭和デモクラシー」に通じるものがある。肝は第5章であり、戦争と民主主義を考える上で、社会大衆党の躍進をどう捉えたらよいのか?という点については今後考察を深めていきたいと考えている。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
史学雑誌の論文を読んでいるようで、新書としては読みづらい。内容的に面白い題材だっただけに、もう少し読みやすく書いていただけたら、もっと楽しめたのに…。残念。 でも、日中戦争突入前には、反ファッショだとか反戦だとかが国会や論壇でまだ自由に話せていたということには驚き。
Posted by
選挙結果という名の民意から昭和30年代の政治を読み解こうとしているのが面白い。 社会大衆党の支持が日中戦争の前に厚くなったのは、民主主義への支持というよりも社会主義的な体制への支持や、反既成政党という意思表示だったのだと思う。 そして民意が求める社会主義的な体制は、総力戦体制を求...
選挙結果という名の民意から昭和30年代の政治を読み解こうとしているのが面白い。 社会大衆党の支持が日中戦争の前に厚くなったのは、民主主義への支持というよりも社会主義的な体制への支持や、反既成政党という意思表示だったのだと思う。 そして民意が求める社会主義的な体制は、総力戦体制を求める軍部と極めて親和性が高かったのだろうと思う。そのシンクロ度合いが軍部をして、戦線の開設と拡大を後押ししたのかなという想像ができる。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
自分が持っている戦前政治史の常識が意外なほどに間違っていることに驚きを覚えた。戦前民主主義は北支事変(日中戦争)の勃発ですべてが吹っ飛んだと結論付けながらその理由が説明されていないため著者の考えは次著を待たねばならないが、ヒントは保阪康正「昭和史7つの謎」や半藤利一「昭和史」、「戦争の日本近現代史」と合わせ読めば自ずと見えてくるだろうか、また一方で戦争という熱狂の時代に突入していく人々の心理など同時代性を持ってしても意識できないだろうか。
Posted by
混沌とした政治と経済の行方を探りたい POINT 「戦前の日本に国民の言論の自由がなかった」は誤り 民主主義が戦争を望み、戦争が民主主義を抑圧した 過去を正しく認識し、現在の視座に生かす
Posted by
[ 内容 ] 民政党議員だった斎藤隆夫の「粛軍演説」は、軍部批判・戦争批判の演説として有名である。 つまり、輸出依存の資本家を支持層に持つ民政党は、一貫して平和を重視していたが、本来は平和勢力であるべき労働者の社会改良の要求には冷淡だった。 その結果、「戦争か平和か」という争点は...
[ 内容 ] 民政党議員だった斎藤隆夫の「粛軍演説」は、軍部批判・戦争批判の演説として有名である。 つまり、輸出依存の資本家を支持層に持つ民政党は、一貫して平和を重視していたが、本来は平和勢力であるべき労働者の社会改良の要求には冷淡だった。 その結果、「戦争か平和か」という争点は「市場原理派か福祉重視か」という対立と交錯しながら、昭和11・12年の分岐点になだれ込んでいく。 従来の通説である「一五年戦争史観」を越えて、「戦前」を新たな視点から見直す。 [ 目次 ] プロローグ―「昭和」の二つの危機 第1章 反乱は総選挙の直後に起こった(前史としてのエリートの二極分裂 総選挙と二・二六事件) 第2章 陸軍も大きな抵抗にあっていた(特別議会での攻防 「保守党」と「急進党」の「人民戦線」) 第3章 平和重視の内閣は「流産」した(広田弘毅内閣の退陣(昭和一二年一月) 宇垣一成の組閣失敗 ほか) 第4章 対立を深める軍拡と生活改善(「狭義国防論」の登場 「広義国防論」の反撃) 第5章 戦争は民主勢力の躍進の中で起こった(「民主主義」と「戦争」 「戦争」と「民主主義」 ほか) エピローグ―後世の常識と歴史の真実 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
- 1
- 2