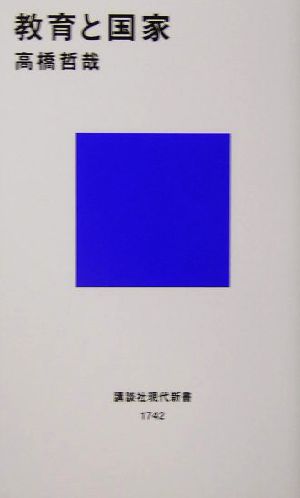教育と国家 の商品レビュー
国家とはなにか。教育…
国家とはなにか。教育とはなにか。安倍内閣が掲げる「教育」政策に批判的・建設的な意見を持ちたい。
文庫OFF
教育は国家権力から自由でありえるのか?教育基本法がその砦であると捉え、教育基本法改正への懸念を左派系の哲学者として語りおろし、2004年に上梓された。が、著者の提言も空しく2年後の2006年に教育基本法は改正され、「伝統文化の尊重」や「国と郷土を愛する」といった文言が追加された。...
教育は国家権力から自由でありえるのか?教育基本法がその砦であると捉え、教育基本法改正への懸念を左派系の哲学者として語りおろし、2004年に上梓された。が、著者の提言も空しく2年後の2006年に教育基本法は改正され、「伝統文化の尊重」や「国と郷土を愛する」といった文言が追加された。これを新国家主義的で戦前回帰だと否定的に評価するのか、普遍主義から脱却し左右のバランスが取れたと肯定的に評価するかは意見がわかれるところだろう。 著者は哲学らしく旧教育基本法や戦後教育にもアポリアがあると論じる。「真理と正義を愛する」というのは「愛の法制化」である(ちなみに改正版では「真理と正義を希求する」に変更)とか、「つくる会」の国家主義的教科書の排除に向けて、国家権力作用に期待する家永裁判支持者の矛盾とか。この辺は哲学者の面目躍如である。 しかしながら、総じて左派系のイデオロギー色が強いので、その辺は留意して読む必要はあるだろう。もう少し価値中立的で相対主義的に論じればよかったのにとも思うが、あくまでも語りおろしの新書であり学術書でもないし、これが著者の政治的スタンスなので、そこから離れられないのは仕方ないのかもしれないが。
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
2004年刊。著者は東京大学大学院総合文化研究科教授(哲学)。本書はシンプルな戦後教育擁護論。本書が言うように、公教育は自覚するか否かは別として権力作用の一例。権力側が強調する道徳や倫理がいかに綺麗事か、つまらぬ道徳の授業を受けさせられた学生経験者なら判ろうもの。すなわち、時の権力者がルールを作っている中で、内面への介入は余計なお世話で、本著者に共感。他者に迷惑にならない意見表明を教育機関が妨害する要なく、これは社会生活のルールは教えるべきこととは次元が違う。また、意見内容が左・右如何によらないのは勿論。
Posted by
著者は天皇制の否定。左派系。 本文はAさんたちが~~すべき→いやそれはダメです。なぜなら~~という論調で進んでいく。 読みやすいけれど、結局どうすべきなのか、書かれていないような気がした 最後の歴史教科書を巡る議論は疑問点が多く残る。 p200に近現代史に関する歴史認識につ...
著者は天皇制の否定。左派系。 本文はAさんたちが~~すべき→いやそれはダメです。なぜなら~~という論調で進んでいく。 読みやすいけれど、結局どうすべきなのか、書かれていないような気がした 最後の歴史教科書を巡る議論は疑問点が多く残る。 p200に近現代史に関する歴史認識についての著書の紹介があるので読んでみたい。 公教育とは誰のためにあるのかな
Posted by
愛国教育が日本を滅ぼす その通りだろう 憲法13条にある「個人の尊重」がないがしろにされる 愛国にもとづく支配は楽で効率的 行政国家にはもってこいだろう しかしそこに「人」が存在しない 国家の三要素「国民」が消え去るのではないか 『すばらしき新世界』を思い出す 1人のエリートだけ...
愛国教育が日本を滅ぼす その通りだろう 憲法13条にある「個人の尊重」がないがしろにされる 愛国にもとづく支配は楽で効率的 行政国家にはもってこいだろう しかしそこに「人」が存在しない 国家の三要素「国民」が消え去るのではないか 『すばらしき新世界』を思い出す 1人のエリートだけでいい 効率を求めて、自ら人間をやめていく現状 いつか現実のものになりそうで怖い 教育と国家 もう一度みんなが考えるべきだろう
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
教育と国家の関係について、哲学を専門とする左派の著者が論じた本。 「戦後教育が不登校、引きこもり、学級崩壊、学力低下などを招いた」という論には論理の飛躍が多いこと、愛国心を持つことと、愛国心教育を推進することは違うということ、戦時中でも礼儀や道徳を重んじず、国策に無関心な国民が多かったなど、主張は大体分かった。予想はできたが。 面白いのは、教えて良いものは『心のノート』にあるような愛国的道徳ではなく、倫理思想であるというもの。これは「正しい道徳」を教えるのではなく、「正しいとはどういう状態なのか」、「道徳とは何か」、「どうして人を殺してはいけないのか」といったことを自分の頭で考えるというもの。 ここまではいいけど、日の丸や君が代にかわる国旗と国歌の方がいいという論には賛同できない。式典での日の丸と君が代の強制と、法律で日の丸と君が代を正式な国旗と国歌として定めることとはまた別の話だと思う。
Posted by
[ 内容 ] 戦後教育は本当に間違っていたのか? 国が推進する「愛国心」教育改革のウソを検証し、教育基本法改正の危険を衝く。 いまこそ教育と国家権力を根本から考え直そう。 [ 目次 ] 第1章 戦後教育悪玉論―教育基本法をめぐって 第2章 愛国心教育―私が何を愛するかは私が決め...
[ 内容 ] 戦後教育は本当に間違っていたのか? 国が推進する「愛国心」教育改革のウソを検証し、教育基本法改正の危険を衝く。 いまこそ教育と国家権力を根本から考え直そう。 [ 目次 ] 第1章 戦後教育悪玉論―教育基本法をめぐって 第2章 愛国心教育―私が何を愛するかは私が決める 第3章 伝統文化の尊重―それは「お国のため」にあるのではない 第4章 道徳心と宗教的情操の涵養―「不遜な言動」を慎めという新「修身」教育 第5章 日の丸・君が代の強制―そもそもなぜ儀式でなければならないのか 第6章 戦後教育のアポリア―権力なき教育はありうるか [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
「昔は良かった…」 果たしてその昔はいつなのでしょうか?戦前?戦後? 教育基本法の改正が目指すものは実は戦前なのではないか。愛国心教育や君が代・日の丸の強制そしてゆとり教育。過去と現在は状況が違う。昔にすがっているだけでは本当の打開策なんて見つからない。 内容の割に厚すぎたので...
「昔は良かった…」 果たしてその昔はいつなのでしょうか?戦前?戦後? 教育基本法の改正が目指すものは実は戦前なのではないか。愛国心教育や君が代・日の丸の強制そしてゆとり教育。過去と現在は状況が違う。昔にすがっているだけでは本当の打開策なんて見つからない。 内容の割に厚すぎたので★2
Posted by
国を思う気持ち、父母を敬愛する気持ちは多かれ少なかれだれにでもあるものだ。しかし、それを国家が押しつけてきたときには警戒が必要だ。そんなことをいろいろ考えさせてくれる本。
Posted by
- 1