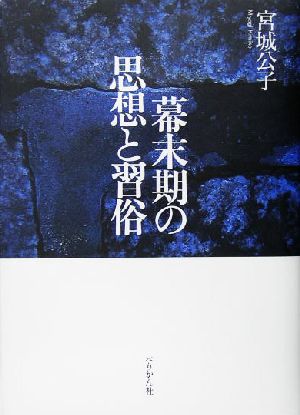幕末期の思想と習俗 の商品レビュー
儒学と国学と自由民権運動の中に残った儒学思想についての論文集。フェミニズムの観点が散りばめられている。国学者、六人部是香の思想について論じた論文「幕末国学の性格――六人部是香の場合」(246-269頁)、「幕末国学の幽冥観と御霊信仰」(270-294頁)を読むために借りて一応通読...
儒学と国学と自由民権運動の中に残った儒学思想についての論文集。フェミニズムの観点が散りばめられている。国学者、六人部是香の思想について論じた論文「幕末国学の性格――六人部是香の場合」(246-269頁)、「幕末国学の幽冥観と御霊信仰」(270-294頁)を読むために借りて一応通読したが、著者が述べる幕末儒学についての問題意識が私に足りないためか、本書全体としてはいまいち頭に入ってこなかった感がある。中江兆民の中の儒学思想に非西洋的な近代像を見出した「一つの兆民像――日本における近代的世界観の形成」(133-170頁)や、自由民権運動の壮士の姿について論じた「民権志士の政治文化」(321-347頁)などは、儒教の遺産が自由民権運動にまで連続していたことを示唆しており、とりわけ後者の論文に出てくる反生活者的な明治半ばの民権志士像は、まるで大正時代のギロチン社のアナキストのようで興味深いが(339頁を参照)、私自身が著者の専門領域に明るくないことと、本書で論じられていることが20世紀の日本にどう繋がってくるのかが余り明瞭ではないため、今の時点では全体像への感想が出てこない。本書に収録された論文を通じて六人部是香について考える材料にしたい。
Posted by
ここで宮城氏は、尾藤正英『江戸時代とはなにか』に対する批判を行っている。それは次のような論旨である。 尾藤正英は江戸時代の寺檀制の下の仏教を中心とした祖霊崇拝と地域社会の氏神信仰との習合形態を「国民的宗教」と名付ける。さらにその特色は、この宗教意識の上は将軍家・皇室から、下は庶...
ここで宮城氏は、尾藤正英『江戸時代とはなにか』に対する批判を行っている。それは次のような論旨である。 尾藤正英は江戸時代の寺檀制の下の仏教を中心とした祖霊崇拝と地域社会の氏神信仰との習合形態を「国民的宗教」と名付ける。さらにその特色は、この宗教意識の上は将軍家・皇室から、下は庶民にまでの「平等性」を強調している点である。しかし、仏教民俗学の教えるところによれば、祖霊崇拝は「家」社会の形成という中世から近世への社会構造の変化を背景とする大きな宗教史上の転換の中で、重層する多様な民族的心性の中から「家」にまつわる「祖霊」のみを特権的に取り上げたものである。つまり近世社会での「祖霊崇拝」とは、「家」から疎外された人々、死穢にたずさわる人々、周縁的な宗教者などへの普遍的な差別の宗教である。言い換えるとそれは「亡魂」にまつわる民俗的心性の中で「祖霊」とそれ以外のおびただしい無縁仏・未成仏霊を分割するものであった。したがって尾藤は、最終的に近現代社会の宗教意識を念頭においた「国民的」に帰結するための「平等性」を強調するあまり、様々な民俗的心性の中から祖先崇拝に吸収されないものは無視し、あるいは切り捨てたと宮城氏は言う。 一般的に江戸中期以降、「家」社会の再編成の過程で、寺檀制下の仏教はその比重を低下させ、様々な民俗的心性が活性化する傾向にあった。そうした中、聖人は鬼神祭祀の礼楽を制作し、文化と人倫秩序のもたらし共同体的統一を作り上げたと説いたのは荻生徂徠である(子安宣邦『鬼神論―儒者知識人のディスクール』)。そして多様に拠る民を統合するために「天祖」=天照大御神への祭祀を必要を説いた後期水戸学に徂徠学の影響を見たのは尾藤正英であったはずである。そうした「多様性」ゆえの統一という側面を全く無視し、祖霊崇拝と氏神信仰との習合形態における「平等性」のみに目を向けているのが本書なのである。 ※「宗教史のためのノート―尾藤正英『江戸時代とはなにか』に寄せて」のみの要約。
Posted by
- 1