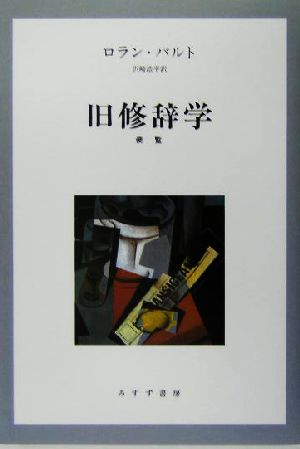旧修辞学 便覧 の商品レビュー
旧修辞学ってことは,新しい修辞学があるかどうかって話なんだけど,私もまだ未読なグループμの『一般修辞学』が思い浮かぶが,実はこれは1977年の出版。バルトの本書は1970年出版だから,グループμの試みはバルトによる影響が大きいのかもしれない。 などとよく知らない情報を書くのはよく...
旧修辞学ってことは,新しい修辞学があるかどうかって話なんだけど,私もまだ未読なグループμの『一般修辞学』が思い浮かぶが,実はこれは1977年の出版。バルトの本書は1970年出版だから,グループμの試みはバルトによる影響が大きいのかもしれない。 などとよく知らない情報を書くのはよくないですね。ともかく本書はかつては主要な学問分野の一つだった「修辞学rhethoric」について,その歴史を概観したもの。基本的には知らないことばかりで,いつものバルト作品の楽しみとは少し違った,「耐えの読み」が続くが,やはりクライマックスは待っていた。「B・1・18 場所,topos,locus」と題された節以降の議論だ。ギリシャ語起源の場=toposと話題=topicが同じ語源を持つことは現代英語圏の地理学者も論じているが,アリストテレスの『自然学』における場所=トポス論と『トピカ』との関連を論じたものはいないように思う。ともかく,ここ以降20ページくらいがメチャクチャ面白く,なぜ本書をもっと早く読まなかったかを公開する次第。でも,アリストテレス全集2巻『トピカ 詭弁論駁論』を読む楽しみができた。こういう議論がさらっとできるバルトの博識と引き出しの多さには驚かされる。未だにバルトを賞賛するような研究者はあまりいないだろうが,そう簡単に彼の仕事を越えたとか,忘れ去るなんてことはできないように思う。 そして,フランス語のできない私にとっては,既に亡くなってしまった(もう20年経ちます)沢崎浩平氏のような訳者の仕事にも多大なる恩恵を被っています。
Posted by
- 1