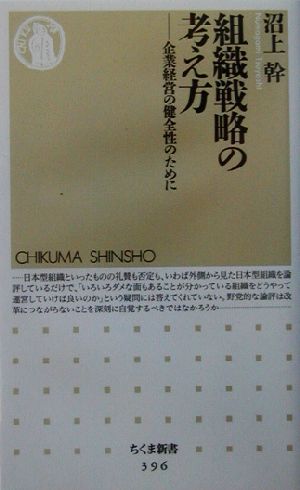組織戦略の考え方 の商品レビュー
作中でザ・ゴールを紹介してたり、やや繋がりがある。やはり良い。推薦本の中で読んだやつに外れがないし、他にも手を出してみよう。この本は読むたび頭の中がシンプルにクリアになる感じある。
Posted by
組織の問題を解決するには? →まず仕事の多くをプログラム化し、そのプログラムで対応できない例外をヒエラルキーによってその都度上司が考えて解決するのが基本中の基本 短期的には分業が効果的だが、長期的には緩やかなオーバーラップ型の分業が効果的 ボトルネックは短期と長期では異なる 何...
組織の問題を解決するには? →まず仕事の多くをプログラム化し、そのプログラムで対応できない例外をヒエラルキーによってその都度上司が考えて解決するのが基本中の基本 短期的には分業が効果的だが、長期的には緩やかなオーバーラップ型の分業が効果的 ボトルネックは短期と長期では異なる 何らかの判断を下して最終的に問題解決をするのはヒトであり、組織構造それ自体ではない
Posted by
日本型経営の最大の特徴である終身雇用制度を軸に、組織のマネジメントについて論じる。組織論を考える上での入門書として最適。事例が豊富なことも素晴らしい。
Posted by
冒頭では現場への権限委譲の話などあって期待したのですが、後半はどんどん組織腐敗の話になっていって、ちょっと私の期待とは違っていました。この本が Amazonで★4.4 というのは、、苦労している人が多いということですね。
Posted by
・日本企業には日本企業なりの組織戦略がある。安易に欧米に右に倣えをし、中途採用・解雇をスタンダードにしてもうまくいかないだろう。 ・組織の基本は官僚制。官僚制はよく槍玉にあがるが、基本を押さえてこそ、アレンジが機能する。守破離。 ・優秀な人間が根回しなどの内部政治に奔走されないよ...
・日本企業には日本企業なりの組織戦略がある。安易に欧米に右に倣えをし、中途採用・解雇をスタンダードにしてもうまくいかないだろう。 ・組織の基本は官僚制。官僚制はよく槍玉にあがるが、基本を押さえてこそ、アレンジが機能する。守破離。 ・優秀な人間が根回しなどの内部政治に奔走されないようなマネジメントが必要。 ・会社の何かがうまくいっていないとき、組織がスケープゴートとして挙げられるが、それは結局組織を槍玉に挙げれば誰も責任を背負わないから。組織を構成するのは人で、人が変わらなければ組織は変わらない。 ・マズローの欲求階層説は誤解され、生理的欲求から自己実現欲求に飛躍しがち。低位の階層の欲求が満たされることで、次の欲求が生じるというもので、自己実現の前に現代は承認・尊厳欲求を満たすべき。 ・従って、褒める、ということが最も安く最も価値のある報酬。これを忘れがち。 ・経営者とは、決断することが仕事。たとえ皆にとって痛みを伴う決断であっても、皆のためになることを自分で考え決断しなければならないのが経営者。 ・キツネの権力が現れたら、トラに直接会いにいく。その勇気が必要。 →結論、どんなことがあっても表に出て闘えるだけの能力と勇気を持ち合わせていなければ組織をよくしていくことはできない。その勇気を裏付けるものとして、いつでも転職して食べるのに困らないスキルやネットワークを作り続けることが大切だと再認識した。
Posted by
前半は経営組織論の話で、組織の基本は官僚制にあり、これをベースに様々な組織形態を取るべきだと主張する。 後半はエッセイで、組織の足を引っ張る様々なタイプの人間について(ここでは本来の役割を認識していないトップマネジメントも批判の的に)。 なぜ組織にしょうもない人間が現れてしまう...
前半は経営組織論の話で、組織の基本は官僚制にあり、これをベースに様々な組織形態を取るべきだと主張する。 後半はエッセイで、組織の足を引っ張る様々なタイプの人間について(ここでは本来の役割を認識していないトップマネジメントも批判の的に)。 なぜ組織にしょうもない人間が現れてしまうのか、彼らをどう扱えばいいのかについて社会学的な視点から解説する。 他のレビューでは「ただの愚痴だ」とも書かれているが、 組織の理論面と実際のドロドロとした面の両方に目が配られていて、いい本だと思う。 ただ、後半は分量調整のためか、内容がくどい。学生のレポートのような姑息な手を使ってきたことに腹が立った。
Posted by
なるほど、「企業経営とは、このような発想をもとにしているのか」が本書を読んでの感想である。 「企業」を外部から見るとき、一般には「社会的責任」などの外部からの視点と「労働問題」などの内部問題は注目されるが、「企業組織」をじっくりと考察する機会はあまりない。 本書は、その企業...
なるほど、「企業経営とは、このような発想をもとにしているのか」が本書を読んでの感想である。 「企業」を外部から見るとき、一般には「社会的責任」などの外部からの視点と「労働問題」などの内部問題は注目されるが、「企業組織」をじっくりと考察する機会はあまりない。 本書は、その企業の組織戦略の考察なのだが、その精密さには瞠目した。 とくに「企業組織の基本はまず官僚制である」との視点には感心した。「官僚制」という言葉は多くの場合組織の欠陥を指摘する時に使われる悪いイメージがあるが、「組織戦略」をつきつめて考察する場合は、まったく違うということか。 しかし、読者が本書を読む場合には、自分の会社への批判の論理的根拠を本書の論理構成の中に探してしまうのではないか。どのような会社でも完璧ではなく、改革の必要性は常にある。本書はその論理を提供できるだけの分析力に満ちていると思えた。 しかし、会社組織を分析・評価する視点は、本書の視線以外にも「社会性」や「共同体」など多様にある。 本書を構成する分析力には敬意を表するが、これのみで「組織戦略」のすべてとはいえないのではないかとも思った。
Posted by
http://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480059963/
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
最近教わったビジネス書の読み方で、『「はじめに」「おわりに」「目次」だけを読んで、大事そうな章だけ読む!』『周りの章は、結果的に読みたくなったら読む』で読んでみました。 この本は3部構成で各部の中に章があるので、初心者としては第2部を読むことに。 非常に読みやすいので、その流れで第3部もさらっと…ということで上述の読み方としては理想的。 前置きが長くなりましたが、以下、印象に残ったところです。 組合を始めとするフリーライダー問題はなるほど!という感じ。 自分も安易に、組合のユニオン・ショップ制はどうかと思っていましたが、ユニオン・ショップ制をやめてしまうと、組合員でなくても組合の恩恵が受けれる(例えば、組合による職場環境改善等)のでそんなに簡単ではないですね。 また、社内で落としどころを探ろうとしてしまうのが、内向き志向を強め、組織を腐敗させるは自身にも反省させられるものがありました。 最後に、組織の腐敗の対策として紹介されている方法を備忘録がてら。 ①複雑怪奇化したルールや仕組みは全廃 ②成熟事業部から優秀な人材を、強引に新規事業に引き抜く ③仕事ができる人を暇にする業務改善(つまらない仕事をさせない)
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
タイトルは極めて固いのですが、組織はもっとどろどろしたものだということを改めて感じさせる人間の醜さを心理的に分析し、それが組織の腐敗、組織の非活性化にどのようにつながっているかというメカニズムを説得力を持って書いています。フリーライダーとはぶら下がり人間。フリーライダー比率が一定以上になれば組織は危機的になる。解決への基本方針、信頼出来る中間層の育成のために。トラとキツネの権力、スキャンダルと宦官の跋扈、会社の寿命30年という言葉がなぜ肯きを持って説かれるのか、それは組織が次第に腐敗しているという実感を誰もが持っているため、なるほどという感じです。これは我々よりも、正直な声が入らなくなりつつある経営トップ層にぜひ読んで欲しい本です。
Posted by