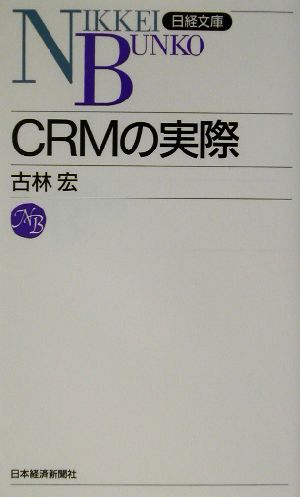CRMの実際 の商品レビュー
2003年と古い本だけどCRMのほんとの入り口だけだけど ネットのあちこちに散らばっているような内容をコンパクトに分かりやすく書いてあると思う でも「実際」ではなく「入門」ではないか
Posted by
いつ買ったのか覚えてないぐらい前に買ったまま読んでなかった本。 やっと読みました。 去年ゲーミフィケーションから、 ユーザーの動機付けの方法について考えてたんだけど、 その文脈でちょっと立ち返ってCRMの文章をこのタイミングで読んでみよう、と。 で、読みながら考えてたのは、 ...
いつ買ったのか覚えてないぐらい前に買ったまま読んでなかった本。 やっと読みました。 去年ゲーミフィケーションから、 ユーザーの動機付けの方法について考えてたんだけど、 その文脈でちょっと立ち返ってCRMの文章をこのタイミングで読んでみよう、と。 で、読みながら考えてたのは、 ゲーミフィケーションで目指すユーザーの動機付けとか、 サービスのコアバリューの伝え方とか。 そこら辺とは、またちょっと視点が違う話ですね。CRMというのは。 顧客分析と分析の上での優良顧客との関係強化や、 具体的施策としてのポイントインセンティブとその運用・活用について。 基本は小売業を想定して書いてあって、 それはまぁオフラインであってもオンラインであっても生かせるものだと思うんだけど、 小売業以外のとこへの応用があまり整理できなかった。 それはこの本のせいではないけれど。 ポイントインセンティブシステムは、 販促ツールというか購買データの収集・分析に使われて、 それを商品構成に活かしていく、という流れが想定されるけれども、 じゃあ例えば、インセンティブのポイント自体が商品となってる場合のことを考えたり、とか。 もう、頭ぐっちゃぐちゃです。 でこの本2003年に出版された本なのですが、 当然スマホやら何やら色々ないわけで、 大げさなシステムやらその導入コストの話やら、 取れる情報幅からそのための手間まで、 時代を感じてなかなか楽しかった。 最新の話題についてくのも大事なんだけど、 急にポンっと違う文脈を眺めてみるのもやっぱ面白いもんです。
Posted by
もともと百貨店のIT部門の方が書かれた本であり、通りいっぺんとうの入門書。コンサルよりは企業でCRMを担当するかたが読み出すような本と位置づけられるかな。
Posted by
CRMに興味があり、読んでみた。【CRMは単純なポイントシステムではない】■顧客の分析・ポジショニング ・基礎的な分析手法についても詳細な説明 ・下位の顧客を切り捨てることになっても 優良顧客を優遇することが重要■自社の弱みを知る ・優良顧客ですら手を出さない自社商品・部門を ...
CRMに興味があり、読んでみた。【CRMは単純なポイントシステムではない】■顧客の分析・ポジショニング ・基礎的な分析手法についても詳細な説明 ・下位の顧客を切り捨てることになっても 優良顧客を優遇することが重要■自社の弱みを知る ・優良顧客ですら手を出さない自社商品・部門を 洗い出し ⇒その部分を強化・販促することでより強固な 顧客関係を構築■CRMから得られた結果をアクションにつなげることが重要 ・「出口発想」 ・現場で具体的にどういうアクションにつなげるか、を設計時点で 考慮しておく必要がある。
Posted by
これから得意先を体系的に管理していこうという企画を出すために読みました。うちの会社が一般顧客相手ではないので少し当てはまらないですが、ヒントはいっぱいありました。 最後のインセンティブの部分はあまり参考にならなかったかな。
Posted by
CRMの実践方法について考え方から示されている本。何故CRMが重要か、顧客の順位付け、顧客への働きかけ、インセンティブについてから構成されている。CRMの基本的な考え方がわかりやすくまとまっていて読みやすい本だと思う。実践方法についても、これだけで取り組めるとはいえないものの、...
CRMの実践方法について考え方から示されている本。何故CRMが重要か、顧客の順位付け、顧客への働きかけ、インセンティブについてから構成されている。CRMの基本的な考え方がわかりやすくまとまっていて読みやすい本だと思う。実践方法についても、これだけで取り組めるとはいえないものの、取り組みの考え方がきちんと書かれているという印象を受けた。 CRMの重要さについては、企業がマス・マーケティングからワン・トゥ・ワン・マーケティングへ移行する必要があること、そしてそれを実現するためにCRMが必要であるということが述べられている。どうしてワン・トゥ・ワン・マーケティングが必要なのかというと、売り手市場から買い手市場へと変化しているという理由だけでなく、顧客のライフスタイルが多様化しているという側面もあることを指摘している。同じ年齢・性別であっても購買傾向は、「個」人によって全く変わってきているので、それに合わせたマーケティングを実施する必要があるということ。上位顧客を特別扱いするというのは「えこひいき」という感じがするが、上位3割の顧客が7割の売り上げを占めており、さらに上位顧客は利益率の高い商品を購入する傾向もあるということ。上位顧客に焦点を当てることは企業としては当然、そして上位顧客のニーズに対応していくことで企業の「個」性が育成されるという側面もあるということ。この本で明示的に書かれていた訳ではないが、顧客が企業を育てるという側面は興味深い。 顧客情報の収集について、例えば「子供がいるか」「共働きか」などを顧客に尋ねても、あまり意味が無いということ。顧客の状況は常に変化するという面もあるし、「子供の居る両親」と「孫の居る祖父母」はマーケティング上は同じ対応が必要かもしれない。そこでこのような情報を顧客に尋ねるのはやめて、購入する曜日や時間帯で共働きか否かを判断、過去に子供向けの商品を購入したかどうかで判断をする。ここは素直に「なるほど」と感じた。その判断方法が100%正確かというと必ずしもそうとは言えないけれど、分析を行うための情報としては十分だと思う。この本にも書かれていたが、DBを作ることが目的となっては本末転倒で、何を分析する必要があるかを考えて集める情報を決めるということは大変重要なことだと思う。
Posted by
リピーターを生む最強「顧客システム」 小売業に限らず、幅広く参考になる内容だった。 「入るを図り、出るを制する」
Posted by
- 1