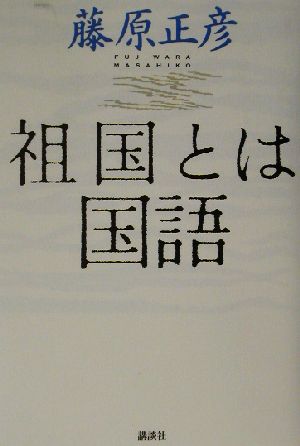祖国とは国語 の商品レビュー
■国語はすべての知的活動の基礎。 読書は教養の土台、教養は大局観の土台。 家族愛、郷土愛、祖国愛 を身につけるためにも日本語を学ぶ必要ある。 ■英語は、国民の5割が学習し20%程度がなんとか使え 5%くらいのエリートが流暢に操れるくらいで良い。 残り5割は英語を全く学ばないか...
■国語はすべての知的活動の基礎。 読書は教養の土台、教養は大局観の土台。 家族愛、郷土愛、祖国愛 を身につけるためにも日本語を学ぶ必要ある。 ■英語は、国民の5割が学習し20%程度がなんとか使え 5%くらいのエリートが流暢に操れるくらいで良い。 残り5割は英語を全く学ばないか、英語以外の中国語・ 韓国語等アジアの言語を学べば良い。 上記2点は賛成. ■しかし、俺は学生時代、国語が嫌いだった。 著者も書いているが、"わかりきった文章を段落に分けたり、「それ」が何を示すのか等の作業。著者の気持ちや意図を問われ、教師の見解と異なる場合は批判され、時には笑われたり、結局は教師の見解をおしつけられる"というのは俺自身学生のころ感じた。 結局、読む、書く、話す、聞くのうち、読む力を子供につけさせることが重要で、そのため、国語は子供を読書に向かわせる契機・引き金として国語の授業は使われるべきということか。。。。。 誰か正しく有効な国語教育を考えてください。
Posted by
国語はすべての知的活動の基礎である ノーベル賞の湯川博士が幼少の頃四書五経を素読させられた為漢字が怖くなくなった。 国語の基礎は文法ではなく漢字 インターネットの知識は切れぎれ、読書には及ばない。 読書は教養の土台、教養は大局観の土台。 倫理は十全な情緒があってはじめて有効となる...
国語はすべての知的活動の基礎である ノーベル賞の湯川博士が幼少の頃四書五経を素読させられた為漢字が怖くなくなった。 国語の基礎は文法ではなく漢字 インターネットの知識は切れぎれ、読書には及ばない。 読書は教養の土台、教養は大局観の土台。 倫理は十全な情緒があってはじめて有効となる。 高次の情緒 他人の悲しみを悲しむ もののあわれは日本人の誇り。 勇気、誠実、正義感、慈愛、忍耐、惻隠、名誉と恥、卑怯を憎む→親や教師が説教により教える。 家族愛、郷土愛、祖国愛、人類愛も育てるべき。 地球市民なんてものは通用しない。
Posted by
著者の他著作と同様に、教育、文化、郷土愛を説く。巻末の満州再訪記では、太平洋戦争に至る背景に若干触れつつ、著者のルーツを辿り、数学者としての美意識と、生誕地の荒廃との対比に葛藤している。
Posted by
国語の大切さに気づかされました。とてもわかりやすく、納得の行くように書かれた藤原正彦さんの文章は凄いです。これからは国語を重要視して、語彙を増やして、もっと思考力をアップさせます。 また「満州再訪記」ですが、「流れる星は生きている」のその後、いや藤原ていさんのその後がわかり、と...
国語の大切さに気づかされました。とてもわかりやすく、納得の行くように書かれた藤原正彦さんの文章は凄いです。これからは国語を重要視して、語彙を増やして、もっと思考力をアップさせます。 また「満州再訪記」ですが、「流れる星は生きている」のその後、いや藤原ていさんのその後がわかり、とても興味深く読ませて戴きました。 藤原家のストーリーとは別に、(ソ連の)日ソ中立条約の本当の狙い、アメリカが大東亜戦争終結を急いだ理由など、意外な事実も知る事ができ、目から鱗が落ちました。 そしてイギリスと言う国の見方もちょっと変わったし、それは結局、国語力の違いと言う事になるんですね。何か本書から、目新しい情報をたくさん与えた貰った気がします。 ありがとうございます。 以下、本書で共感した箇所です。 (page.42) 押しつけられたものを自らの価値観としてとりこむにせよ、反発して新しいものを探すにせよ、あらかじめ何か価値観を与えられない限り、子供は動きようがないからである。 (page.61) 「若いときの苦労は買ってもせよと言うが、必ずしもそうでない。ことに幼いときの苦労は生涯癒えない傷を残す」・・・「身辺清潔の人は、何事もしない人である。出来ない人である」 (page.70) 知的活動とは語彙の獲得に他ならない。 (page.86) 国語力の低下は、(二)で述べた知的活動能力の低下、(三)で述べた論理的思考力の低下、(四)で述べた情緒の低下、(五)で述べた祖国愛の低下、を同時に引き起こしている。 (page.95) 基本的に英語は、必要にせまられている人やエリートを目指す人々が猛勉して身につければよいものである。 (page.104) 豊かな時代だからこそ、親や教師は、我慢力養成のため子供に厳しく当らねばならぬのに、今や子供と友達関係になり果て、甘やかし放題である。 (page.118) この日本には自然や神仏に「ひざまずく心」があった。金銭を低く、名誉や「もののあわれ」などを高く見る「精神性」もあった。四季に恵まれた「美しく繊細な自然」と、それに対する世界でも図抜けた感受性があった。 (page.125) 改善になるか改悪になるかよくわからない改革に憂き身をやつすより、しきたりや伝統に身をまかせながら穏やかな心でいたい、というのが当時の人々の気持ちだった。 (page.131) 情報社会でもっとも大切なのは、いかに情報を得るかでなく、いかに情報に流されず本質を掴むかである。大局観を持つことである。活字文化は情報時代にこそ重みを増すのだと思う。 (page.135) その場その場の局地的最善が大局的最善とは限らない。小さな国益を重ねた後に、大きな破局が待っていることもある。
Posted by
藤原正彦のエッセイ。数学という普遍を研究する生業だからこと、国語というゲシュタルトな価値構造の大切さを感じるのだろう。使われることで価値が増大するのは言語くらいではないだろうか。金庫に入れられた言語は価値がない。
Posted by
この人の主張はわかりやすくて良い。「小説は読まなくてもいい、実用書を中心に本を読め!」という人たちより好感もてる。
Posted by
一つ一つのお話がコンパクトにまとまっていて読みやすい。「求む踊り子」面白かった。なかなか聞く機会のない満州のお話は、歴史を感じられてもっと知りたいなと思わせてくれる。著者の母が書いたという、引き上げのときの話『流れる星は生きている』という本もぜひ読んでみたいと思う。
Posted by
目からうろこの面白さ!!今からもう一度やり直して、数学者になりたい、大学教授になりたい、ケンブリッジに教授として行きたい、こんな頭脳明晰スポーツ万能な人間に生まれ変わりたいetc.最後のほうの国語〜論が非常に面白かった。あとで、著者が非常に有名な国家の品格の著者と同一人物であると...
目からうろこの面白さ!!今からもう一度やり直して、数学者になりたい、大学教授になりたい、ケンブリッジに教授として行きたい、こんな頭脳明晰スポーツ万能な人間に生まれ変わりたいetc.最後のほうの国語〜論が非常に面白かった。あとで、著者が非常に有名な国家の品格の著者と同一人物であると知り、ただものではないことが証明された。非常によみごたえがあった。
Posted by
ベストセラーになった「国家の品格」の著者で数学者の藤原正彦さんのエッセイ集です。とても読みやすくておもしろい。この国の将来を、本気で憂い、本気で考える著者が国語教育の重要性を訴えます。昔、国語の教科書に「最後の授業」ってありましたよね。フランスアルザス地方にナチスドイツが侵攻して...
ベストセラーになった「国家の品格」の著者で数学者の藤原正彦さんのエッセイ集です。とても読みやすくておもしろい。この国の将来を、本気で憂い、本気で考える著者が国語教育の重要性を訴えます。昔、国語の教科書に「最後の授業」ってありましたよね。フランスアルザス地方にナチスドイツが侵攻してきたため、フランス語の授業ができなくなる話ですが、その話も踏まえると、母国語がすなわち国民のアイデンティティにつながる、という理解も、さほど極論に思えない説得力です。 あとは短編のエッセイが多数。奥様や子供さんとの日常のやり取りが、ほのぼのとして楽しいです。こういう方が学校の先生としてたくさんおられたら、日本の教育もずいぶん違うんじゃないかな、と思います。
Posted by
この方は数学者だけあって実に論理的で明快な主張です。「国家の品格」はまだ読んでないけど、読まれるわけがわかった気がする。でも一番の驚きはこの人が新田次郎と藤原ていの息子だったということだわ。
Posted by
- 1