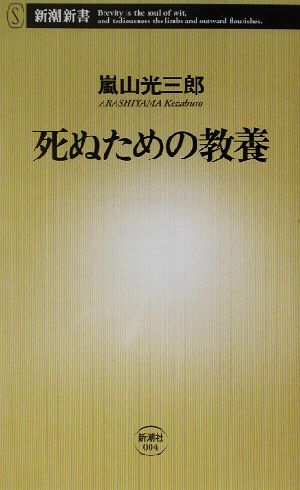死ぬための教養 の商品レビュー
五度も死に瀕した著者が選んだ本のジャンルは硬軟、洋の東西、人文科学から自然科学まで多岐に渡る。果ては漂流記まで含まれている。懇意にしていた作家の死に際して、その著書も選ばれ、思い出が語られる。
Posted by
人生で何回も死を間近に感じる体験をした著者が、そのたびに手に取って死について考えた本の紹介。こんなに何回も危険な体験をされていたとは。。 ブックレビューとして読むには、やや不十分な広さ深さか。著者が死についていろいろと考えた断片集というところ。
Posted by
Posted by
講談社エッセイ賞の受賞歴もある作家・エッセイストである嵐山光三郎(1942年~)が、自らの5度にも及ぶ死にかけた体験に触れながら、平素から「死」について考えるために、参考になる書籍を紹介したもの。 紹介されているのは、キューブラー・ロス『死ぬ瞬間~死とその過程について』、『夜と霧...
講談社エッセイ賞の受賞歴もある作家・エッセイストである嵐山光三郎(1942年~)が、自らの5度にも及ぶ死にかけた体験に触れながら、平素から「死」について考えるために、参考になる書籍を紹介したもの。 紹介されているのは、キューブラー・ロス『死ぬ瞬間~死とその過程について』、『夜と霧』の著者・ヴィクトール・フランクルの『死と愛』、坂口安吾『堕落論』、深沢七郎『楢山節考』などの古典的な作品に加え、養老孟司『唯脳論』、松井孝典『地球・宇宙・そして人間』、山崎章郎『僕のホスピス1200日~自分らしく生きるということ』や、冒険ノンフィクションのスティーヴン・キャラハン『大西洋漂流76日間』、松田宏也『ミニヤコンカ奇跡の生還』など、幅広いジャンルからの計46冊。(既に絶版となっているものも少なくない) 著者の死生観が語られたものというより、手軽なブックガイド的読み物として楽しめる。 (2006年2月了)
Posted by
タイトルにつられて購入……本書は、嵐山氏の「死」にまつわる自叙伝であり、「死」にまつわる書評である。 なので読み進めていってもいまいちピンとこない部分が存在するのは、致し方ないことだろう、と考えたのだが本書の中の嵐山氏の言葉がすべてを物語っていたように思う。 「人は、不慮の事故や...
タイトルにつられて購入……本書は、嵐山氏の「死」にまつわる自叙伝であり、「死」にまつわる書評である。 なので読み進めていってもいまいちピンとこない部分が存在するのは、致し方ないことだろう、と考えたのだが本書の中の嵐山氏の言葉がすべてを物語っていたように思う。 「人は、不慮の事故や、急病などによって病院に入って自分が死ぬかどうかというぎりぎりのところに身を置かないと、生と死ということについてなかなか考える時間がない。」 当たり前と言われれば当たり前なのだが、われわれはつい「死」というものに想いを馳せてしまう。興味を持ってしまう。 しかしながら、「死」というものは、じっさいその淵に立たないと理解しうるものではないということが一貫して綴られていたように思う。 さすれば、氏のいう「死ぬための教養」にははたして意味があるのだろうか……?ということで、☆3。
Posted by
これも結構流し読みかな。死については自分もよく考えるから、ここに挙げられているような書物のうち、いくつかは気になったりもしましたけど。
Posted by
ラ・ロシュフーコー 太陽と死は直視できない 深沢七郎 山田風太郎 人間臨終図巻 やさしい遺言のはなし 法学書院
Posted by
正確には、作家・嵐山光三郎氏と宗教社会学者・大村英昭氏の共著『上手な逝き方』の感想です。 先日、この新書が著作権、著作者人格権を侵害し、絶版、回収が決定したというニュースを知り、今後もう読めなくなるかもしれないと思って読んでみました。 すでにブクログからも情報は消えていたため、同...
正確には、作家・嵐山光三郎氏と宗教社会学者・大村英昭氏の共著『上手な逝き方』の感想です。 先日、この新書が著作権、著作者人格権を侵害し、絶版、回収が決定したというニュースを知り、今後もう読めなくなるかもしれないと思って読んでみました。 すでにブクログからも情報は消えていたため、同著者による類似書と思われるこちらのページに載せました。 タイトルから、もの静かなトーンの内容かと思いきや、のっけから「千の風になって」批判で始まったことが意外で驚きました。 対談者はどちらも結構ざっくばらんに、思ったことをポンポン話していっています。 作家と僧侶の対談。浄土真宗の僧侶なので、また宗派に寄った独特の慣習もあるようですが、通常は『おくりびと』のように顔に死に化粧を施さないという話に驚きました。 あれは、エンバーミングとしてはやりすぎのようです。 確かに、仏様になって旅立つという意味を考えれば、むしろ洗い清めてまっさらの状態で送り出すほうがよいような気もしますが、常に穏やかな死に顔というわけではないでしょうから、やはり死に化粧は遺族にとって大切なのではないかと考えながら読んでいきました。 戒名とは、亡くなると坊主にしてあの世へ送るという意味だと初めて知りました。 また、人形のこけしは子消しだと聞いて、ぞっとしました。 間引きされ、消された子の供養だそうで、そんな風に考えたことがなかったので、なかなか衝撃的でした。 だから貧しい風土だった東北地域で生み出されたのでしょうか。 日本人は、骨に非常にこだわる民族だという話も出ていました。 海外の埋葬についてわからないため、比較論としてそういうものかと思います。 アメリカの焼却施設は、とても強力で、美しい骨として残らず、粉末になってしまうのだそうな。 日本の施設は絶妙な焼き加減だと評価しており、その着眼点がユニークでした。 死に関連して、自殺の話も採り上げられました。 近代文学者の三大自殺は、芥川、太宰、三島とのこと。 "芥川は「文学」をアリバイにし、太宰は「女」をアリバイにし、三島は「思想」をアリバイにした。"という文章には、なるほどと思いました。 ただ、それに続く"川端の自殺は日本人に向けた呪詛"という言葉の意味は、よくわかりませんでした。 これを知るには日本文学の素養が必要のようです。 瀬戸内寂聴が「自殺すると著書が売れるから、自殺しようかな」と言ったというエピソードはなんだか笑えました。 死についての観念的な定義や捉え方に関しては、よく目にしますが、この本ではむしろ遺体の埋葬法について語られており、知っているようで知らない話が次々に語られていきました。 昔は、年越しの借金は許されなかったため、誰もが年末にはツケを返し切ったものですが、今では借金をそっくり子供に残すようになってしまった点など、なかなか生きにくい社会になっているものだと思ったりもしました。 残念な結果となった本ですが、内容はなかなか興味深いものでした。
Posted by
[ 内容 ] 死の恐怖から逃れるための最大の処方箋だった宗教が力を失った今、「自分の死を平穏に受け入れる」ために必要なものは、「教養」だけである。 単なる知識ではない、「死ぬための教養」こそが、「自己の終焉」を納得するための武器となるのだ。 五度も死にかけた著者が、宇宙論から闘病...
[ 内容 ] 死の恐怖から逃れるための最大の処方箋だった宗教が力を失った今、「自分の死を平穏に受け入れる」ために必要なものは、「教養」だけである。 単なる知識ではない、「死ぬための教養」こそが、「自己の終焉」を納得するための武器となるのだ。 五度も死にかけた著者が、宇宙論から闘病記まで四十六冊を厳選! これが、「死」を自己のものとして受け入れる教養である。 [ 目次 ] 第1章 一九八七年、四十五歳。生まれて初めての吐血(血を吐いた程度じゃ死ねない(『ミニヤコンカ奇跡の生還』) 物としての自分か、あるいは生命としての自分か(『死をめぐる対話』) ほか) 第2章 一九九二年、五十歳。人生を一度チャラにする(全勝なんて力士には興味ない(『人間 この未知なるもの』) 芭蕉が最後にたどり着いたのは、「絶望」(『芭蕉の誘惑』) ほか) 第3章 一九四五年、三歳。初めて死にかけた(作家が書いたものはすべて、小説という形を借りた遺書である(『豊饒の海』) 川端康成の小説にせまりくる人間の死(『山の音』) ほか) 第4章 一九九八年、五十六歳。ふたたび激しく吐血(そうだ、生きていたいのだ(『大西洋漂流76日間』) 死ぬときは、みんな一人(『たった一人の生還』) ほか) 第5章 二〇〇一年、五十九歳。タクシーに乗って交通事故(人の一生も国の歴史も川の流れと同じ(『日本人の死生観』) 遺族には、長い悲しみが待っている(『死ぬ瞬間』) ほか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
著者が影響うけた死を題材とした46書を厳選。 芭蕉からビートたけしまで幅広い。奥行きもある。読みやすい。 ぼくも妻の膝枕で逝きたいです。 満足度6
Posted by
- 1
- 2