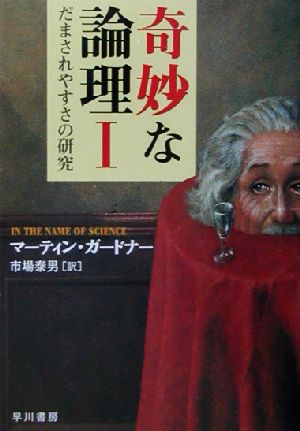奇妙な論理(1) の商品レビュー
エセ科学を論破する書…
エセ科学を論破する書物です。現代でも、星占い・血液型性格判断などが流行っていますが、他愛の無い遊びであるあいだはよいにせよ、これが就職などにも影響するとなると、人権侵害の疑いもあるわけです。そんな「似非科学」は昔からあり、今でも命脈を保っているものもあるのですが、エセ科学と昔から...
エセ科学を論破する書物です。現代でも、星占い・血液型性格判断などが流行っていますが、他愛の無い遊びであるあいだはよいにせよ、これが就職などにも影響するとなると、人権侵害の疑いもあるわけです。そんな「似非科学」は昔からあり、今でも命脈を保っているものもあるのですが、エセ科学と昔から戦って来た著者の書です。
文庫OFF
おもしろかったが・・…
おもしろかったが・・・。専門知識(ある程度の)がないと読むことが苦痛になる箇所がある。すらすら読めるタイプの本ではない。
文庫OFF
1952年に書かれた、トンデモさん研究の嚆矢。 いまでも、似たようなトンデモさんの活躍は続いている。
Posted by
原書は50年以上前に刊行された本だが、現代にも通じる普遍的な内容を含んでいると思う。 「なぜ勉強しないといけないのか」と子どもに質問されたら、「他人に騙されないように」というのが、悲しいことだがもしかすると現代ではもっとも説得力のある答えなのかも知れない。 それにしても、今日...
原書は50年以上前に刊行された本だが、現代にも通じる普遍的な内容を含んでいると思う。 「なぜ勉強しないといけないのか」と子どもに質問されたら、「他人に騙されないように」というのが、悲しいことだがもしかすると現代ではもっとも説得力のある答えなのかも知れない。 それにしても、今日に至ってもなお「誰かエライ人が顕れてこの世を救ってくれる」などというまやかしを信じたがる人がまだ多くいるのには驚かされる。そしてそういう欺瞞を流布するための講演会のポスターが臆面もなく貼られていたりするのを見ると、腹立たしささえ覚える。 悪意があるかどうかは別として、人を騙そうとする言説には様々なトリックが仕掛けられている。本の紹介とは趣旨がずれるが、この機会にいくつか紹介したいと思うのである。 まず、われわれ自身ついつい犯してしまいやすいのが、【根拠のトリック】である。 これは、簡単に言えば、主張にとって都合の良い事実だけを採り上げて根拠とするやり方である。 岩波現代文庫の『ご冗談でしょう、ファインマンさん』はとってもお茶目な本であるが、その中でファインマン教授がここだけは真面目な口調で述べている個所がある。 “たとえばもし諸君が実験をする場合、その実験の結果を無効にしてしまうかもしれないことまでも、一つ残らず報告すべきなのです。” (下巻・p295) それから、【確率のトリック】。 『奇妙な論理〈1〉』の最終章に登場するあわれなライン教授は、このトリックの呪縛から抜け出せなかった人だ。 百万回に1回という奇跡がもし身近で起こったら、誰でも奇跡を信じてしまうだろう。だがその背後には、同じ条件の下でも99万9999回の「奇跡は起こらなかった」という事実があることを忘れてはいけないのだ。 三番目に紹介したいのが、【論理のトリック】。 「AであればBである」が真実なら「BでなければAではない」もまた真であるが、「AでなければBでない」とは必ずしも言えない。 そこの論理をうまくすり替え、巧みな文章で飾り立てることによって納得させてしまおうとする輩もいる。 四番目が、【定理のトリック】。 経済や歴史の通説(定説)には、それに反する事実や文献がいくらでも見つかる。それをことさらクローズアップし、数学や物理学の法則や定理(矛盾や反例を許さない)に対するのと同じ考え方をもって通説や定説をひっくり返そうとする例がよくある。 以上、とりあえず思いつくものを掲げたが、たぶん他にもあると思う。 実はセールストークのテクニックとしても、このようなトリックは往々にして使われる。だがそれを排除して客観的に正しいとされたことだけを話題にしなければならないとしたら、私たちの会話はとんでもなくつまらないものになってしまうだろう。 私たちは、こうしたロジックやトリックとうまくつき合う術を学ばなければならないのだと思う。 最後に、かのニュルンベルク裁判における、ある証言を掲げておく。 “国民にむかって、われわれは攻撃されかかっているのだと煽り、平和主義者に対しては、愛国心が欠けていると非難すればよいのです。 このやりかたはどんな国でも有効ですよ。” (ヘルマン・ゲーリング)
Posted by
疑似科学批判のための基礎的な本。ハヤカワから文庫化。 人に貸して返ってこないなーと思っていたら家の中から出てきた。返してもらってたのだった。
Posted by
1950年代の出版だが、現在も同じような疑似科学が存在しているので、参考になる書籍である。カール・セーガンの同様な本も出ている。
Posted by
この本を読もうと思ったきっかけは、世に出回るうまい話、特に人間(医療)系に関して、これは効かない、インチキだという面での主張を知りたかったから。 この点では、医療の四大宗派、「同種療法(ホメオパシー)」、「自然療法(ナチュロパシー)」、「整骨療法(オステオパシー)」、「脊椎指圧...
この本を読もうと思ったきっかけは、世に出回るうまい話、特に人間(医療)系に関して、これは効かない、インチキだという面での主張を知りたかったから。 この点では、医療の四大宗派、「同種療法(ホメオパシー)」、「自然療法(ナチュロパシー)」、「整骨療法(オステオパシー)」、「脊椎指圧療法(カイロプラクティック)」について、出自及びその背景とする理論の怪しさ、証明の怪しさなどから排除している。科学的な実証に重きが置かれず、ふわふわした感じのまま、うわさが広まって、それなりに支持を受けている点を糾弾しているのだが、科学的実験も統計学的には、完全性が保証されるわけではなさそうだし、これらすべてを排除するのは、どうなのか?という感じを受けた。 だまされたことをわからずだと困った話だと思うのだが、これを受け入れつつ、効果が実感できる場合、どうしたものか? 地球空洞説とか、オルゴン理論、ダイアネティクスなど、前提となる知識が全く違う人っていうのがある一定数存在することや、言葉巧みな誘導などのテクニックによってだまされるってことがあるという事を認識しておく必要があるということは、知っておいて損はないかもしれないと。 この本って、科学的見地に立ったマーティン・ガードナーが、世界中のおかしな説を紹介しているのだが、ここがおかしいということを並べて、章が終わるので、そこから先は、読んだ人が感じたり考えたりして欲しいという事なのだろう。
Posted by
上下2巻、一気に読んだと言いたいところだけど、実は読むのに少し時間がかかった。書かれた時代が少し前で、現代の感覚と合わないところもあったのだと思うけれど、それ以上に作者の語り口がもうひとつ肌に合わなかった。 以前「ト学会」の本を楽しんでいた。まさに「奇妙な論理」を振り回すお...
上下2巻、一気に読んだと言いたいところだけど、実は読むのに少し時間がかかった。書かれた時代が少し前で、現代の感覚と合わないところもあったのだと思うけれど、それ以上に作者の語り口がもうひとつ肌に合わなかった。 以前「ト学会」の本を楽しんでいた。まさに「奇妙な論理」を振り回すおかしな本たちを「トンデモ本」と呼び、それらの書評をする本を何冊か出していて、僕も「とんでもないな」と思いながら、笑いながら読んでいた。この「奇妙な論理」という本は、そういう読書の中から知った本で、読むのを楽しみにしていたものである。が、実際読んでみたらもうひとつ肌に合わなかった。 理由はたぶん簡単なことで、「ト学会」の人たちは楽しんでいたけれど、作者ガードナーは怒っているのである。数学者のガードナーにとって、論理に合わないことを振りかざしている輩は許すまじ存在なのかもしれない。あるいは、そういう不可思議な論理を振り回すことで詐欺同然に大もうけをしたり他人を迷わすことが許せないのかもしれない。その怒りには共感できる。 が、同時代の新聞記事を読んでいるわけではない僕にとって、その怒りは共感こそすれ、好んで読みたいものではなかった。正直、現代の日本には、こういう形ではないにしても、もっともらしい論理を振りかざし他社の利益を損ない自己の利益を求めるものがいくらもいるからだ。 実際のところ、作者は、僕のような読者を対象に本を書いているのではないはずだ。この本が書かれた時代・場所の中では、大いに怒り論破する理由があったのは、本を読めばわかる。同時代で読んでいれば、溜飲が下がる思いがしたかもしれない。 いい本だと思うけど、ちょっと期待が高くて少しずれていた僕の勝手な事情で、思ったほど楽しめなかったのである。
Posted by
東大教授おすすめ 超自然現象、超能力がいかにして人々の中に浸透していき、ブームが際限なく繰り返されるかを分析
Posted by
奇妙な論理を列挙している。どんな論理があるかを知ることが目的なら良いが、すべてに詳しい反証がついているわけではないのでいまひとつ。
Posted by
- 1
- 2