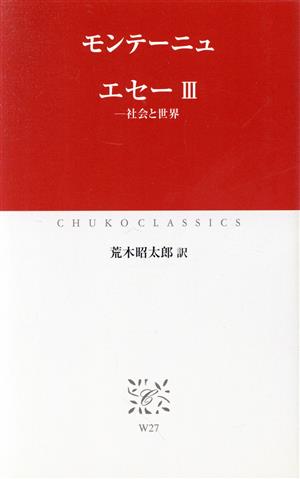エセー(Ⅲ) の商品レビュー
ユマニスムとは人間中心主義という意味らしいが、これは必ずしも人間理性の手放しの礼讃ではないだろう。ユマニストとて神に比して人間が不完全であることを疑わなかったはずだ。むしろその不完全性をありのまま受け入れ享受する精神的態度と考えたい。これがユマニスム理解として正しいかどうか自信は...
ユマニスムとは人間中心主義という意味らしいが、これは必ずしも人間理性の手放しの礼讃ではないだろう。ユマニストとて神に比して人間が不完全であることを疑わなかったはずだ。むしろその不完全性をありのまま受け入れ享受する精神的態度と考えたい。これがユマニスム理解として正しいかどうか自信はない。渡辺一夫のユマニズムとも少し力点は違うかも知れない。ただ「エセー」全巻に流れるモンテーニュの精神はそういうものだと思うし、「社会と世界」を扱ったこの第三巻でも、不完全な人間による設計主義的な社会変革をきつく戒め、長い時間をかけて維持されてきた習慣と秩序の重要性が説かれている。現実政治の世界にも身を投じ、宗教改革とそれに伴う混乱を嫌悪したモンテーニュは、200年後にフランス革命に抗し、近代保守主義の始祖とされるエドマンド・バークとその思想的核心を共有していた。「われわれは、すべてをこわしてしまうのでなければ、彼らをねじ曲げて、その習慣となっている癖を取り去ることはほとんどできない。」「(国家という)これほど大きい建物の土台を取りかえようと企てるのは、垢を落とそうとして地肌の色まで消し、・・・死によって病気を癒そうとする人々のすることだ。」至言である。
Posted by
中公クラシックス モンテーニュ 「 エセー Ⅲ 」 ギリシア哲学やローマ皇帝などの言葉から、穏やかに生きるコツを筆に随って綴った名著。体系や中心思想はないが、どこから読んでも啓蒙される内容 人間中心主義ではあるが、個人の自由とは少し距離をとっている。社会の中で埋没しない...
中公クラシックス モンテーニュ 「 エセー Ⅲ 」 ギリシア哲学やローマ皇帝などの言葉から、穏やかに生きるコツを筆に随って綴った名著。体系や中心思想はないが、どこから読んでも啓蒙される内容 人間中心主義ではあるが、個人の自由とは少し距離をとっている。社会の中で埋没しない自分を強調しているように感じる 「孤独について」「むなしさについて」は 名言満載。孤独や老いを 肯定的に捉えている われわれの情念はわれわれよりも先へ越えていく(1巻3章) セネカ「未来のことを気づかう精神は不幸だ」 一方の利益は他方の損だ(1巻22章) 「一つのものの誕生や増殖は、もう一つのものの変化や腐敗である」 習慣について、またうけいれられている法は簡単に変えないほうがいい(1巻23章) 「慣れることは、われわれの判断力の眼力を眠らせてしまう」 良心について(2巻5章) 「よくない考えは、それを考える人間にもっともよくない結果を与える」 われわれの欲望は困難によって大きくなる(2巻15章) 「欲望は、手の中にあるものを軽蔑 し〜持っていないものを追いかける」 「われわれに何かを完全にまかせることは、それに対する軽蔑を湧かせる。足りない状態とありあまる状態は、同じ不都合におちいる」 「あらゆる防備は戦争の顔つきを見せる」威圧的な防衛の態勢そのものが攻撃を招き寄せる 孤独について(1巻39章) 「孤独の目的は〜それによって一層悠々と、楽な気持ちで生きていくということ」 「他人との結びつきを引き離し、自分だけで生き、そこでわれわれの好きなように生きる力をかちとろう」 「もしできれば、われわれは妻、子ども、財産、健康を持つべきだが、われわれの幸福が、それらのものに依存してはならない〜まったく自分の持ち物である、まったく干渉されない店裏の部屋を自分に確保しておかなければならない」 「世の中でもっとも大切なことは、自分自身に所属する仕方を心得ることだ」 ソクラテス「老人たちは、あらゆる市民の仕事から身をひき、自分の思い通りに、任務に対する拘束もなしに生きるようにしなければならない」 自分の意志をだいじに使う(3巻10章) 「他人のために多少とも生きようとしない人は、自分のためにも生きることはない」 人食い人たちについて(1巻31章) 「人間の評価と価値は 心ばえと意志のはたらきの中にある。そこに人間のほんとうの名誉が宿る」 むなしさについて(3巻9章) 「好運が良心と両立しないかのように、人びとは不運の中にいないと、いい人間にならない」 「わたしの仕事は、人生を用事に追われてせわしく送るより、ゆったりと呑気に送ること」 「必要にせまられることが、人間たちを結びつけ寄せ集める」 「外科医の最終の目的は、わるい肉を死なせることでなく〜本来の肉を再生させ、その部分を本来の状態にかえしてやること」 「わたしは誰も必要としないように努力している。わたしのすべての希望はわたしのなかにある」 「老衰は孤独を求める資質だ〜自分の存在を世間の目の触れないところにひっこめ〜亀のように自分の殻の中にひきこもり、思いをめぐらすのが道理にかなった仕方だろうと思う」 キケロ「人生を支配するのは運命であり、知恵ではない」
Posted by
- ネタバレ
※このレビューにはネタバレを含みます
中立という立場、 それは当時の人たちにとっては 理解できないものだったことでしょう。 それゆえにこのエセーは禁書扱いにされたと 言われています。 この本は難しいです。 哲学や古典を参考に書かれているので 引用文を見ても、どのような意味か 取りかねる部分もあるのです。 だけれども、欲は際限のないもので 難儀なものですし、 攻撃しようとする相手には 相手にしないということ… それに尽きるんですよね。 ただ、後者はSNSの台頭で、 これすら通じない人もいるので 注意が必要ですが… (今の時代を哲学者が見たら 冷ややかな目で見られることでしょうね) 死に関しても ここでは触れられています。 著者は59歳でこの世を去りました。 残念ながら子供運には恵まれませんでしたが 今でも、彼の家系は残存していると聞きます。 年を取ったら次世代に託す… 本当に大事なことですね。
Posted by
モンテーニュさんは「おれは自分のしたいようにしかしねーぜ(`_´)」って言いながら、周りを総てを受け入れようとしてらっしゃるのではないかと思った。孔子の「われ十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知る。六十にして耳従い、七十にして心の欲する所に従...
モンテーニュさんは「おれは自分のしたいようにしかしねーぜ(`_´)」って言いながら、周りを総てを受け入れようとしてらっしゃるのではないかと思った。孔子の「われ十有五にして学に志し、三十にして立ち、四十にして惑わず、五十にして天命を知る。六十にして耳従い、七十にして心の欲する所に従いて矩(のり)を踰(こ)えず」の七十歳の境地みたいに…矛盾を矛盾じゃなくするための修練。そんなことを目指そうとする人間の凄さ!貴さ。 そんなふうになれたらいいなぁ~とは思うけれどもモンテーニュさんは財産もあって血統もいい貴族だし、わたしは時給いくらのどこの馬の骨ともわからない根無し草。しかもなんら突出した能力のない平凡な人。ちょっと出発地点が違うからな… でもまぁ純粋な憧れとか尊敬とかを抱けるというのも老後の慰みにはなるかもしれないのでまた読んでみようと思う。その時はまた違った滋養が得られるような気もするし。 「エセー」を読むことで宗教とか経済とか政治とかの皮が一枚めくれそうな気がする。わたしの場合はその予感だけがあってまだめくれてはないけれど。 考えたら400年も前の本だった。引用されているのはギリシャやローマ。こちらは2500とか2000年前。 当時フランスは宗教戦争中。今タイではクーデター。人間ってつくづく変わっていないんだなぁ~。 自分だけに集中するのにもそれなりの関係や経験が必要なんだろうな。でもまぁ人それぞれ苦にならない程度にやっていけばいいかな。 Mahalo
Posted by
[ 内容 ] [ 目次 ] 社会の組みたて(われわれの情念はわれわれよりも先へ越えていく;一方の利益は他方の損だ;習慣について、またうけいれられている法は簡単に変えないほうがいいこと ほか) 他者とかかわる(孤独について;子どもたちにたいする父親たちの愛情について;有用さと公...
[ 内容 ] [ 目次 ] 社会の組みたて(われわれの情念はわれわれよりも先へ越えていく;一方の利益は他方の損だ;習慣について、またうけいれられている法は簡単に変えないほうがいいこと ほか) 他者とかかわる(孤独について;子どもたちにたいする父親たちの愛情について;有用さと公正さについて ほか) ひろがる時空(人食い人たちについて;むなしさについて) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
- 1