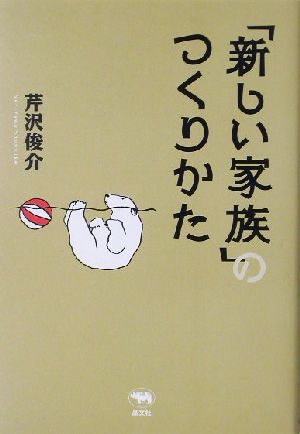「新しい家族」のつくりかた の商品レビュー
家族のエロス(=受け止める力)は失われた。受け止める役割りの人を<母>と呼ぶ。これは、生物学的な母親とは区別される。女性である必要もない。家族の構成メンバーをありのまま受け止める存在である。 生物学的な母親である女性が「自分」に気づき、<母>であることが「自分」を阻害することで...
家族のエロス(=受け止める力)は失われた。受け止める役割りの人を<母>と呼ぶ。これは、生物学的な母親とは区別される。女性である必要もない。家族の構成メンバーをありのまま受け止める存在である。 生物学的な母親である女性が「自分」に気づき、<母>であることが「自分」を阻害することであると認識した時、家族のエロスは失われた。 グループホームという形に新しい家族の在り方がある。グループホームはアパートではない。ふたつを分けるのは帰属感と<母>という存在である。 ----------- 猫は<母>という存在になれるかな?生物学的な母親はともかく、<母>になれない、なる機会を奪われているという感覚が私を苛立たせているのかもしれない。
Posted by
『We』177号で、映画「隣る人」の監督・刀川さんが読んだという本。芹沢が1990年代の終わりから2000年代の初めに書いた文章が編まれている。 「12歳の性と死」、長崎の「幼児誘拐殺人事件」をはじめ、さまざまな事件と、そこからうかがえる子ども、家族の姿が書かれてゆく。10年...
『We』177号で、映画「隣る人」の監督・刀川さんが読んだという本。芹沢が1990年代の終わりから2000年代の初めに書いた文章が編まれている。 「12歳の性と死」、長崎の「幼児誘拐殺人事件」をはじめ、さまざまな事件と、そこからうかがえる子ども、家族の姿が書かれてゆく。10年ほど前の事件の記憶をたどりながら、〈いい子〉のこと、〈母〉という存在のこと、〈教育〉の縛りと、ありのままの存在ということ、ありのままで受けとめられる/受けとめることを考えたりした。 芹沢が、かつて〈いい子〉であったという人から聞いた話が書きとめられている。 ▼自分が[知らない子どもを殺すという残酷なイメージの]空想に終始し、実際に子どもをあやめずにすんだのは、ものごころのつきはじめた少年期の入り口で出会った年上の女性に、注意も説教もされずに、存分に自分のまるごとを受けとめられた記憶があったからだ。 たった半日の交流にすぎなかったのだが、肯定されたことの幸福感にはじめて満たされたのだった。殺さなかったのは、その人への信頼を通しての自己肯定感の記憶に支えられたことによる…(pp.24-25) 長崎の事件の加害者が12歳の少年だということがわかったとき、当時の鴻池防災担当相(政府の青少年育成推進本部の副本部長でもあった)が、子どもの犯罪はまず親の責任だと言い、「親を引きずりだして、市中引き回しのうえ、打ち首にすべき」とぎょっとするような発言をしたことも、あらためて思いだす。 「世間の声」と連続しているであろう鴻池発言のようなのが、この10年くらいの間にもっと増え、それに公然と共感する声もいっそう大きくなった気がする。こういう声が、"自分でなんとかしろ"そうでなければ"身内になんとかしてもらえ"という生活保護バッシングにも、つながってると思える。 芹沢は、かつて住んでいた地区で起きた殺人事件に際し、はじめて「世間の声」を間近に聞いたとして、その経験を経て、こう書いている。 ▼世間の陰のひそひそ声と大きな声とは一枚の紙の表裏のような関係にあること。すなわち大きな声の裏には囁き交わす声が張りついているということ。 世間の声とは、事件の第三者であることの余裕から、自分を正義の位置に置き、そこから行う加害者と被害者の落ち度の裁定なのである。私が〈加害-被害〉の二元論に立ち、われ先に被害者意識を組織することによってこしられられた船に乗り込み、その安全な場所から、決して射返されることのない非難と攻撃の矢を安心して加害者に向けて射ることにためらいを覚えることの理由の一つは、こういう経験を経たことにある。(p.31) 大きな声は、子どもを殺した加害者に向けられていた。そして、ひそひそ声は、暗に親を責めるものだった。芹沢は、そのひそひそ声を聞いたときに「ひでえ話」だと思い、しかし自分のなかに親を非難する気持ちが皆無かと考えるとまるきり自信がなくなってしまった、そういう声は自分のうちにもあることを認めざるを得なかった、と書く。 「家族を〈外〉から見ると-あとがきに代えて」で、光の子どもの家のこと、そして施設長の菅原さんが「隣る人」という言葉でとらえた存在のことが書かれている。たぶん、「隣る人」は、芹沢が本文でくりかえし書く〈母〉と同じような存在なのだろう。 家族における子どもを受けとめる力を「家族のエロス」という言葉でとらえ、その受けとめの主体=受けとめ手を〈母〉と呼ぼうと、芹沢は提案する。「子どもの表出をまるごとある期間、持続的に受けとめる特定の主体」(p.108)が〈母〉なのだと。〈母〉には原理的に誰でもなることができるが、産みの親=母親であっても受けとめる力のないものを〈母〉と見なすことはできない、とも書いている。 母親と〈母〉を分離したかったと芹沢は書くのだが、"母"という同じ字をつかった言葉は、ちょっとくるしい気もする(アタマでは分かるといっても、読んでいるうちに、ごちゃごちゃしてくる)。その点、この芹沢のいう「受けとめ手」の表現として「隣る人」というのは、かなりうまいものだと思う。 こんど菅原さんの『誰がこの子を受けとめるのか』も読んでみたい。 (6/17了)
Posted by
- 1