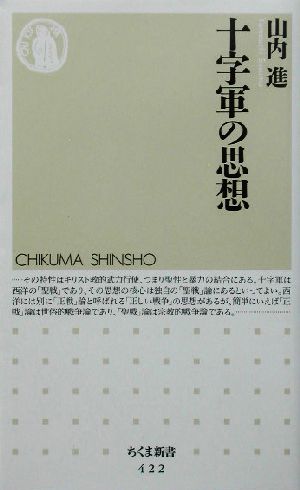十字軍の思想 の商品レビュー
●内容(「BOOK」データベースより) 「聖戦」という言葉は、今ではイスラムのテロ行為を正当化するための代名詞となっている。しかし、それが歴史の中で形となって現われたのは、中世ヨーロッパのカトリック世界においてであった。そこでは、異教徒に支配されている「聖地エルサレム」の奪還を旗...
●内容(「BOOK」データベースより) 「聖戦」という言葉は、今ではイスラムのテロ行為を正当化するための代名詞となっている。しかし、それが歴史の中で形となって現われたのは、中世ヨーロッパのカトリック世界においてであった。そこでは、異教徒に支配されている「聖地エルサレム」の奪還を旗印として、「十字軍」が構想された。ローマ教皇と教会法学者は、十字軍による非ヨーロッパ世界の征服・略奪を、道徳的にも法的にも正当化していた。その流れの中から登場したのが、「新しいイスラエル」アメリカである。今日、アメリカの突出した行動を支える思想として甦りつつある「十字軍」と「聖戦」思想の歴史をたどり、キリスト教世界の深層心理を探る。 門外漢なので主張の成否は分からないけど面白かった!「十字軍」てそもそも漠然とした知識しかなく、=テンプル騎士団=エルサレム奪還の為の軍、という認識しかなかったけど、もっとしっかりした定義があって、その精神は今日まで影響を及ぼし続けている…(かもしれない…) 学び…。 十字軍の歴史を追っていく中で、ローランの歌のモデルの話、カール大帝、千夜一夜物語等、どちらかというと「ファンタジー」の分野で知名度をあげたものがたくさん出てくるのすごく面白い。今更だけどキリスト教を追うことって中世の歴史を追うことでもあるんだな。 宗教が今よりも密接に人々の中に生きて、役割を果たしていた中世の話もめちゃくちゃ面白かったし、それらの精神は現代でも役割を変え生き続けているはずだ、という作者の主張も面白かった。 増補・改訂版があるみたいなのでそれも読みたい。
Posted by
十字軍の考え方が今のアメリカの考え方につながって、国際情勢に影響を与えていることがよくわかった。 アメリカ人がよくjusticeという理由もわかった。思想の底に流れているものを知っていることが相手をより理解することに通じる。
Posted by
[ 内容 ] 「聖戦」という言葉は、今ではイスラムのテロ行為を正当化するための代名詞となっている。 しかし、それが歴史の中で形となって現われたのは、中世ヨーロッパのカトリック世界においてであった。 そこでは、異教徒に支配されている「聖地エルサレム」の奪還を旗印として、「十字軍」が...
[ 内容 ] 「聖戦」という言葉は、今ではイスラムのテロ行為を正当化するための代名詞となっている。 しかし、それが歴史の中で形となって現われたのは、中世ヨーロッパのカトリック世界においてであった。 そこでは、異教徒に支配されている「聖地エルサレム」の奪還を旗印として、「十字軍」が構想された。 ローマ教皇と教会法学者は、十字軍による非ヨーロッパ世界の征服・略奪を、道徳的にも法的にも正当化していた。 その流れの中から登場したのが、「新しいイスラエル」アメリカである。 今日、アメリカの突出した行動を支える思想として甦りつつある「十字軍」と「聖戦」思想の歴史をたどり、キリスト教世界の深層心理を探る。 [ 目次 ] 第1章 主の剣 第2章 「神がそれを望み給う」 第3章 十字軍、北へ―新しいマカバイ 第4章 神の鞭・悪魔の僕・ピューリタニズム 第5章 “新しいイスラエル”アメリカ 第6章 近代の十字軍思想 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
Posted by
十字軍とそれを支える思想がどのように形成され、どのように“現代までに”継承されていったのか丹念に説明されています。“背景”の考察に力を入れる歴史家は、表に出てくる「大義名分」よりも「本音」つまり経済的・政治的要因など俗っぽい動機を探ることに力を入れてきました。しかし、戦争に参加す...
十字軍とそれを支える思想がどのように形成され、どのように“現代までに”継承されていったのか丹念に説明されています。“背景”の考察に力を入れる歴史家は、表に出てくる「大義名分」よりも「本音」つまり経済的・政治的要因など俗っぽい動機を探ることに力を入れてきました。しかし、戦争に参加する大部分の一般兵たちは「大義名分」を信じ、それに酔い、命をかけていったのです。最近こうした「心性」に関する研究が増えてきているようですが、それは確かに経済的・政治的な要因など上の立場の人間が考えることで、“二等兵”達には関係のないことです。彼らには彼ら専用の「理由」が必要となったのです(戦前の日本が「アジア解放」を掲げたように)。それで、十字軍を突き動かした背景について著者は「異教徒との共存に不潔感をおぼえる、潔癖な浄化思想」であり、最終的に十字軍はその感覚が異教徒との関係が“国家理性”によって構築される16世紀の国際政治によって「汚染」の「浄化」への強い欲求が無くなっていったことで終わりを迎えた、とした。しかしこのような思想は完全に消滅したのではなく、ピューリタニズムに継承され、新大陸の「異教徒」の地を「神の支配する国」に変えることを使命としたアメリカ人に継承されたとする。そして世界で最も合理的なアメリカ人に潜むこうした「信仰」と「浄化思想」「聖戦的思考」からブッシュ大統領jのイラクへの行動を「新十字軍」と言えるのではないかと論を結んでいる(ブッシュ自身も不用意に自分たちの行動を「十字軍」と表現してしまった)。私は「過去」の思考を「現在」の行動に結びつけることにあまり賛成はできないのですが、多角的という観点からそれも必要だと思うようになりました。
Posted by
- 1