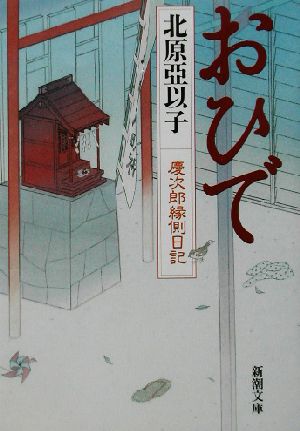おひで の商品レビュー
この「おひで」は慶次…
この「おひで」は慶次郎縁側日記シリーズ第3弾となります。本当にこのシリーズにハズレはないです。タイトルにもなっている「おひで」が出てくる「佐七の恋」という話には泣きました。作者の北原亞以子さんが「もう登場人物が勝手に動き出す。」と語られていますが、本当にそうです。おなじみの登場人...
この「おひで」は慶次郎縁側日記シリーズ第3弾となります。本当にこのシリーズにハズレはないです。タイトルにもなっている「おひで」が出てくる「佐七の恋」という話には泣きました。作者の北原亞以子さんが「もう登場人物が勝手に動き出す。」と語られていますが、本当にそうです。おなじみの登場人物たちがとても良い味出してます。
文庫OFF
著者の作にひかれるの…
著者の作にひかれるのは、江戸情緒溢れる文体や個性的な登場人物などいろいろあるが、どうにもならないことにもがきながらも必死に生きている様々な人生模様が魅力なのだと思う。
文庫OFF
慶次郎シリーズ三作目。 最初は物足りないと思っていたけれど、言い切らない良さを思い出させてくれた作品。 人生白黒だけで割り切れるもんじゃないんだよと、改めて教えてくれる。 嬉しい限りだと思う。
Posted by
慶次郎縁側日記シリーズ第三作。再読 『仏の慶次郎』という同心時代の異名がクローズアップされる話が多かった。 『仏の何のと言われたって、たまたま手前の目についた者を助けてやるだけじゃないか。仏だというなら、小伝馬町の奴らを全部、助けてやれってんだ』 「からっぽ」より 『ちょ...
慶次郎縁側日記シリーズ第三作。再読 『仏の慶次郎』という同心時代の異名がクローズアップされる話が多かった。 『仏の何のと言われたって、たまたま手前の目についた者を助けてやるだけじゃないか。仏だというなら、小伝馬町の奴らを全部、助けてやれってんだ』 「からっぽ」より 『ちょっと厄介な女だが、ここでひきとっておけば、また仏の慶次郎の名が上がるってもんだ、そう考えてるよ』 「おひで」より 『仏の慶次郎という同心時代の異名も、悪人を捕まえるというお役目にどこか中途半端なところがあったがゆえに、つけられたのではないか』 「あと一歩」より 『人に罪を犯させまい』と奔走した慶次郎の三十年。だがそのことが『無為』だったと思える空しさもある。 慶次郎はあくまでも人間、神でも仏でもない。人を救えるのはその人自身、慶次郎が出来るのはせいぜいその背中を後押ししてあげることと『大福が食いたくなったら、根岸へくりゃあいい』と話を聞いてあげることくらいなのだ。 今回は辛い話が多い。 孤独、ままならない人生、分かっていても悪い方向へ走るのを止められない自分…。 表題作に出てくるおひでと佐七に共通する孤独は、後に佐七にもっと押し寄せる。何とか彼の辛さを埋めてくれる人間が現れたらと思うのだが。 逆にモテモテの晃之助。切れる老人にまで『狐が化けたのではないか』とうろたえさせるほどの男ぶりを見せている。 だが彼もまた『仏の慶次郎』という偉大すぎる養父の重みに苦しんでいたことが分かる。 その引き合いに出されるのが歌川豊国の息子・直次郎。実在の人物がシリーズに出てくるのは珍しいが、豊国と並び称されるほど慶次郎の名前は知れ渡っている。 その慶次郎もまたモテている。五十近いらしいが見た目は四十前の若々しさ。晃之助・皐月夫妻に八千代という初孫が生まれて爺馬鹿になっている一方で、花ごろものお登世との『色恋』に突き進めないじれったさを感じている。 岡っ引連中からも慕われ幸せそうな慶次郎だが、彼もまた先に抜粋したように『仏の慶次郎』と呼ばれるだけの達成感とは程遠い。胸のうちには『夜叉』を棲まわせているし、『生き甲斐』だった娘・三千代を奪われた苦しみはいまだ続く。 『これから、わたしはどうすりゃいいんですか。(中略)あとには何にもないんですよ』 『みんな同じだよ』 「風のいたずら」より 巻末は北原さんと児玉清さんの対談。慶次郎が誕生した理由、北原さんが作品を通じて伝えたいこと、興味深いことがいろいろあった。
Posted by
久しぶりに時代物を読みたくなって、本棚から選ぶ。何年ぶりかで、慶次郎に触れ、相変わらずいい男だと思う。 北原亞以子は、お話の終わりを引き摺らず、音が聞こえそうなくらいにストンと幕を引く。だから余計に、登場人物たちの心情を思いやってしまうことになる。登場人物は大抵、脛に傷持つ身だ。...
久しぶりに時代物を読みたくなって、本棚から選ぶ。何年ぶりかで、慶次郎に触れ、相変わらずいい男だと思う。 北原亞以子は、お話の終わりを引き摺らず、音が聞こえそうなくらいにストンと幕を引く。だから余計に、登場人物たちの心情を思いやってしまうことになる。登場人物は大抵、脛に傷持つ身だ。…いや、人は誰しも、特に長く生きていれば尚更、そうなのだろう。読み進むにつれて、自分の来し方を振り返り、重ね合わせて、しみじみと傷痕を撫でることになる。 余談だが、半分くらい読んだあたりから、お煎餅が食べたくて仕方なくなる。影響されやすい方はご注意を。 また、巻末には作者と児玉清氏の対談があり、幸せな気分になる。
Posted by
2019年7月15日、読み始め。 2019年7月20日、気付いたこと。 慶次郎縁側日記は、NHKテレビで2004年に連続10回放映されたようだ。 2019年7月20日、読了。 ●2022年12月20日、追記 この小説の舞台は何時頃なのか気になったので調査。 ある記事に...
2019年7月15日、読み始め。 2019年7月20日、気付いたこと。 慶次郎縁側日記は、NHKテレビで2004年に連続10回放映されたようだ。 2019年7月20日、読了。 ●2022年12月20日、追記 この小説の舞台は何時頃なのか気になったので調査。 ある記事によると、慶次郎の父が定町廻り同心のころが寛政のころ、とある。 したがって、1800年代と推定する。 ちなみに、寛政は、ウィキペディアには次のように書かれています。 ---引用開始 寛政(かんせい)は、日本の元号の一つ。天明の後、享和の前。1789年から1801年までの期間を指す。この時代の天皇は光格天皇。江戸幕府将軍は第11代、徳川家斉。 ---引用終了 ●2022年12月29日、追記。 ウィキペディアによると、全作は、次のような感じ。 1.傷(1998年9月) 2.再会(1999年5月) 3.おひで(2000年1月) 4.峠(2000年10月) 5.蜩(2002年1月) 6.隅田川(2002年11月) 7.やさしい男(2003年10月) 8.赤まんま(2004年9月) 9.夢のなか(2005年11月) 10.ほたる(2006年10月) 11.月明かり(2007年9月)シリーズ初の長編 12.白雨(2008年10月) 13.あした(2012年4月) 14.祭りの日(2013年7月) 15.雨の底(2013年12月) 16.乗合船(2014年3月) ●2022年12月31日、追記。 登場人物メモ ・森口慶次郎---定町廻り同心だった。根岸にある酒問屋 の寮で暮らしている。 ・森口晃之助(こうのすけ)---慶次郎の養子。 ・辰吉---岡っ引き。 ・弥五(ヤゴ)---辰吉の下っ引。 ・玄庵(げんあん)---医者。
Posted by
淋しさに包まれてしまったような時、元気が無く落ち込んでいる時「大丈夫だよ」と主人公の慶次郎のように優しく包み込んでくれる人情話だな。
Posted by
巻末の著者、北原亞以子さんと児玉清さんの対談が秀逸。 児玉 「僕にはね、北原さんの描く江戸に住んでみたいという気持ちがあるんです」 全く同感です。
Posted by
3 慶次郎縁側日記 いくら慶次郎の縁側日記といっても慶次郎が関わらない話はどうなのよ。出てくるのは根性ひんまがった女ばかりだし。どうなのよ。終盤は慶次郎バリ前回でよかった。切ない話もあったし。そうそう、いい男だよね。
Posted by
慶次郎シリーズは もちろん慶次郎も良いのだけれど それにも増して 周囲の人たちが魅力的。 七っつぁんの淡い?老いらくの恋 吉次の胸の内 など そうなんよ=人はお互いに胸の内に沢山の思いを抱えて その思いがからみ合って 生きとるんよ と思う一冊。 スーパーヒーローが活躍する話しも面...
慶次郎シリーズは もちろん慶次郎も良いのだけれど それにも増して 周囲の人たちが魅力的。 七っつぁんの淡い?老いらくの恋 吉次の胸の内 など そうなんよ=人はお互いに胸の内に沢山の思いを抱えて その思いがからみ合って 生きとるんよ と思う一冊。 スーパーヒーローが活躍する話しも面白いけれど ともすれば 脇役 の人たちの思いを置いてけぼりにしてしまう。 でも、この慶次郎シリーズは お互いがお互いを思い、 その思いがすれ違ったり ふれあったりするのが良い。 悪者は悪者なのか。 悪意とは何か。 人の心が面白い。 そして文庫はあとがきが楽しみ。 この本では対談になっているのも面白かった
Posted by
- 1
- 2